�@�����E�G�b�Z�C�Ȃ�(�ǂ݂�����������j�@�Ɓ@���܂��̕��E�ӌ����Ȃ�
|

�@
���N(2011�N�j�A�����E�U���ǎ�Â̢�q�O�}�ߊl�Z�p���C�v�Ƃ����̂������āA�����ߊl���f�̘b�����Ă���`�������Ă���������A���̍ہA�������ɢ���H�I�����ҁv�ƏЉ�ꂽ�B���Ƃ��Ă̓q�O�}��̢�p�S�_�v����R���T���v���邢�͢�R�[�f�B�l�[�^�[�v�̃X�^���X�ł���ė����B�������A�q�O�}�Ƃ������R�ɑ��鏃���Ȓm�I�D��S���������A�p�S�_�Ȃ�p�S�_�Ȃ�̒m���E�F���E�Z�p��v����̂ŁA�K�R�I�ɒ��������E���������Ȃ����ƂɂȂ�B��w�̐����w���ł��̂܂܌����E�ɏA�����l�Ƃ܂������قȂ�o�H�ŗ������߁A�����Ă��܂��A�s�V���悭�Ȃ��B�k�C������уA���X�J�ł̊�������n�܂�A�q�O�}�ւ̎��s�����e�X�g�E�ώ@�́A�����k���ɗ��Ă��炳��ɂ���ǂ����@�ƂȂ�A���̂Ԃ���S�m�ہE���X�N�}�l�W�����g�͐��x���グ���Ƃ͎v�����A�����ɂ͂��Ȃ�s�V�̈����g���C&�G���[���֗^���Ă���B�t�L�̑�ɓ�������O�}���������_�b�V���Œǂ��đ҂��\����̂͂܂��悵�Ƃ��āA����̔ӂɎ��̏�ɓo���ė����Ȃ��悤�ɃU�C���Ŏ����̐g�̂��}�Ɍ��т��A�钆�C�^�Y�������ɗ���q�O�}�����w������A�N�}����Ɂu����܂��]�v��A�C�z�������Ė؉A����V�J�̘e�����w�ł��Ă݂���\�\�\�v����ɁA�����̌����҂��炷��ƁA�����Ȃ��Ƃ͂�߂܂��傤�v�ƌ��������Ȃ�悤�ȃe�X�g��ώ@�𐏕������Ȃ��Ă����悤�Ɏv���B�V�J�̘e���͖��Ӗ����Ǝv�����낤�B���ꂪ�����ł��Ȃ��B�܂��A�쐫��������ɂ������Đڋ߂���ɂ́A����Ȃ�ɋZ�p���v��B���̋Z�p�́A�A���X�J�̌���ŃV���b�g�K���̎����Ċw�B�����āA���W�J�ł�����Ȉُ�Ȃ��Ƃ������Ίp���Ȃ����ŃO���O���U�����Ă��邪�A���̍U���́A�q�O�}��real
charge�i��real attack��PanicCharge�j�̖{���������ɕ�����Ă���B���낢���L�@�I�Ɍ��т���\�͂�������A�쐫��������́u���Ƃ�v�ɖ��ʂȂ��̂͂Ȃ��B
�@���H�I�����҂Ƃ����̂͌������Ė������A�q�O�}�����҂̑��l���A�܂�A���������l�ނ����܂ɂ͋��Ă����̂ł͂Ȃ����H�Ƃ����������𖧂��ɂ��āA�s�V�E��@����ɓ���邱�Ƃ́A���Ǖ��������܂܂��B
�@���͂����錤���҂̏o�������ʂ��ł������z���グ�ė����͂��邪�A�ł́A���̉Ȋw�I�ɗ����ꂽ�����݂̂ŁA�Ⴆ�q�O�}�Ƃ̃o�b�^���������ɑΉ��ł��邩�Ƃ����ƁA����͂܂������s�\���B�����܂ŁA�܂��q�O�}�̉Ȋw�͐i��ł��Ȃ��B�Ȋw�I�����ŃN�}�����Ă邩�Ƃ����ƁA������ہB����́A�l���̃��X�N�}�l�W�����g�ł��܂��������l�B�܂�A����ŋN���Ă��邱�Ƃ��A�Ȋw�I����҂��Ă���Ȃ���������R�Ƃ���B����ŁA���s����E�e�X�g�E�ώ@����A�Ȋw�I�ɖ������Ȃ��悤�ɂ��낢���L�@�I�Ɍ��т��A�����E���_���\�z���A����ɉ����Č���Ŏ��H���Ă��������Ȃ��킯���B�����ɐ��l���������蔺���A��������Ƃ����ꍇ������B
�@���̂�������������āA���̃y�[�W��ǂ�ł��炦����K���ł���B
�������\�\�\
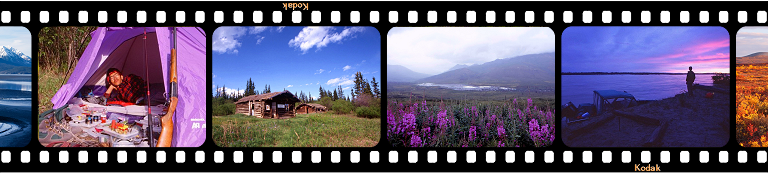
|
|
�_�̂悤�ȃV�J�Ɋw���Ɓ\�\�\�I�r�f�B�G���X�E���]�P��
�@
�@2009�N��11���Ŋ@����ɂȂ����B
�@��2010�N�̏t��A���̔N���߂Ẵq�O�}�̑��Ղ��U���R�[�X�Ŋm�F���A�����������q�O�}�̑��̖т�T���Ă�����A�@�����ɉ�����k���Ƃ�A�T�b�Ƒ����ĎΖʂ��삯�オ�����B�g�h�}�c��}�^�^�r�̃c�������Ă��āA�@�̑����������ɉ�������̂��������Ȃ��B���͋}���Ŋ@��ǂ�������������A�@�̚X������ɖڂ��Â炵�Ă���ƁA�����̖ؗ��̉e�ɒ��F���傫�ȉe���`�����Ɠ������̂��������B��������I�v�@���́A�̂ǂ��ȓ~�̎U���Ɋ��炳��āA���̓��N�}�X�v���[����������Ă��Ă��Ȃ������B�����鎸�ԁB
�@��Ԃ�Ńq�O�}�Ƃ��Ƃ���s���̂͋v���Ԃ肾���d���Ȃ��B���͋�g�Ŋ@�̌��ǂ��ăg�h�}�c�̎Ζʂ��葫���g���Ċ������ɂȂ�Ȃ���K�V�K�V�o�������A�}�ɂƂ肩�������Ƃ��A�e�̎傪�傫�ȗY�W�J�ł��邱�Ƃ��悤�₭���Ď�ꂽ�B�V�J�͋}�̎Ζʂ̒����̊��ɒǂ��l�߂��A�m�������ɂȂ��Ď���O�b�Ə�ɂ������Ċ@�������낵�Ă����B
�@���͓~���J���̃q�O�}�łȂ����Ƃɂ�����ƈ��g�̋C��������������A�����ɋC���������߂��B�Y�W�J�̊p�͒��C�Ȃ�A��̈�U��ŃX�p�b�Ɛ�قljs���ŁA���������Y�W�J�ɂȂǁA���i�̎��Ȃ��ɋ߂Â��Ȃ����낤�B�V�J�����E�ɓ��ꂽ���́A���̃V�J�̊p�����ɔO����Ɍ����o���Đ���Ă���悤�Ɍ������B�@�̓I�X���̊댯���܂��m��Ȃ��B����܂ʼn��x���q�O�}�ɂ͐��ʂ���Λ������o�������邪�A�Y�W�J�ɂ͏��߂Ă������B������A�I��100�s���z����厭�B���������Ɩ��C�Ȏ�O�}����قNJ댯�����m��Ȃ��B�Ƃɂ����A40�s�̊@���܂�ŏ������������B
�@����40m�قǂ܂ŋ߂Â��āA�s���Z���@�̖������сA�ӂ������ČĂт��������B��@�ICOME�I�I�v�@�@�͈�u�V�J����ڂ𗣂��A��`�O�����̕��ɖ߂肩�������A�_���������B�����ɃV�J�ɖ߂��čĂшЊd����B����ŁA�����x�����B�������Ăт������Ă��A�ʂ��Ȃ������㈫�����ʂɂ����Ȃ�Ȃ��B�����ĉ����A�@���S�O�����u�ԂɃV�J�̍U��������Ɗ댯�Ȃ��߁A���͂ł��邾��������яo���鋗���ɂ܂œ̓����ɐڋ߂��āA�Êς��邱�Ƃɂ����B�ǂ����@�����̂����O���邩���m��Ȃ��ƁA��]�I�ϑ��������Ă������Ƃ��������B
�@���͊@���Ăі߂����Ƃ���A�̓����̓����ƐS���̊ώ@�Ɏ葁����ւ����B���Ɋԍ������B�@���A�V�J�̓����������Ɍ��ɂߊԍ��������ނ��A������Ԃ��Ɋώ@�����B�ǂ����Ă�ł��߂�Ȃ��̂Ȃ�A������_���@�Ɍ��o���P���ɐ����������B�������͍l�����B
 �@�������āA���͍��𐘂��Ċώ@�ɓ��������A���ꂱ��20�������Ă��@�͏W�����������ƂȂ��A�����͎��܂�Ȃ��B�V�J���������Ƃ���T�b�Ɖ�荞��őޘH��f���A�p�������čU�������Ό��ɔ�ёނ����B�e���̂����ɁA�厭�̓����������Ȃ܂łɕ�������ł���B���́A�����̂��Ƃ�Ɍ��������B�������A�V�J������ł�Ă��đ��Ő����������A�p��O�ɓ˂��o������A�U���I�ȑԓx���ڗ����Ă����B�V�J�͒ǂ��l�߂��Ă���B���������������u�ԁA�V�J�̓������ɂ킩�ɉs���Ȃ�A�ԍ�����������@���V�J�ƍ������A�}�Ζʂ�]�������Ă������B��@�I���v���I�v���͌����t�����@��ǂ����Ƃ������A���̏u�ԁA�̐��𗧂Ē����ĎΖʂ��킯���@�������B����܂ł̗͎���������ጢ�Ƃ͕\��ς���Ă���B���͋}�̐[����R�U�炩���ăV�J�Ɗ@�̊Ԃɖ�������荞�݁A���ł̂Ƃ���Ŋ@���ʂɉ���������Ń��[�h�����A�Ζʂ̏�R�����猩���낷�V�J����˂��A�u�����͎e�����B���فI�v�Ǝc���āA�@����������}��]����悤�Ɋ���~�肽�B�V�J�̖ڂ͕s�v�c�������B�S�Ă����ʂ����悤�əz�R�Ɨ����A���ɉ�����@���悤�ɂ����������B �@�������āA���͍��𐘂��Ċώ@�ɓ��������A���ꂱ��20�������Ă��@�͏W�����������ƂȂ��A�����͎��܂�Ȃ��B�V�J���������Ƃ���T�b�Ɖ�荞��őޘH��f���A�p�������čU�������Ό��ɔ�ёނ����B�e���̂����ɁA�厭�̓����������Ȃ܂łɕ�������ł���B���́A�����̂��Ƃ�Ɍ��������B�������A�V�J������ł�Ă��đ��Ő����������A�p��O�ɓ˂��o������A�U���I�ȑԓx���ڗ����Ă����B�V�J�͒ǂ��l�߂��Ă���B���������������u�ԁA�V�J�̓������ɂ킩�ɉs���Ȃ�A�ԍ�����������@���V�J�ƍ������A�}�Ζʂ�]�������Ă������B��@�I���v���I�v���͌����t�����@��ǂ����Ƃ������A���̏u�ԁA�̐��𗧂Ē����ĎΖʂ��킯���@�������B����܂ł̗͎���������ጢ�Ƃ͕\��ς���Ă���B���͋}�̐[����R�U�炩���ăV�J�Ɗ@�̊Ԃɖ�������荞�݁A���ł̂Ƃ���Ŋ@���ʂɉ���������Ń��[�h�����A�Ζʂ̏�R�����猩���낷�V�J����˂��A�u�����͎e�����B���فI�v�Ǝc���āA�@����������}��]����悤�Ɋ���~�肽�B�V�J�̖ڂ͕s�v�c�������B�S�Ă����ʂ����悤�əz�R�Ɨ����A���ɉ�����@���悤�ɂ����������B
�@�@�͌��r�ɐ[�������J���A���͎��ŕG���˂����ČÏ����Ĕ����������A�@�Ǝ����������_���[�W�����A���ꂼ�ꂪ�w���Ƃ̕����傫�������Ǝv���B�@�͗Y�W�J�Ƃ̊ԍ������w�сA�~�X������Ƒ��������邱�Ƃ�m�����B�����āA�����Ċm�F�������ƁA���ꂪ�I�r�f�B�G���X�A���]�P�����B��̓I�ɂ͂��̎��Ɏ��s������Ăѣ�ł���B���i�̐����łȂ�A�@�ɑ���Ăт́A���悻�����B�������A�쐶��������ɋ���������Ԃ̊@�����S�Ɏ����̂Ƃ���ɖ߂����Ƃ��A���͂ł��Ă��Ȃ��B���悻�ł́A��͂�_���Ȃ̂��B
| �c��Ȏ��s�ƈꈬ��̐����ɍl�@�������Đ������A���G�ɗ��ݍ������낢����قǂ��Ȃ���A�Ȃ����킹�������E�l���������Ă���ƁA����炢���ς��̌����҂̂悤�ȕ���ɂȂ邪�A�c��Ȃق��������o������A���ꂱ�����肪�Ȃ��B�w�q�O�}�����E���s��S�x�̂悤�Ȗ{���o���オ���Ă��܂��B�����������̐l������������������Z���̂Ŏd�����Ȃ����A�@�𑊖_�ɂ��Ă���Ƃ������́A���s�ɖ������������Ċ낤���𑝂����C�z��������B�A���X�J�̃e���g�Ŗڊo�߁A�ؘR������f���e���g�̉����Ɂu�����A�����������Ă邼�v�Ɗ����������Ďv�����悤�ɁA�ŋ߁A���̊���s�ӂɗN���B�Q�ڂ������Ŋ@�̊�����āA���u���܂������C���B����������撣�낤�ȁv�ȂǂƁA�C���������قǖ͔͓I�Ȍ��t�Řb���������肷��B�����A�����Ƃ��ǂ��A�F�����S���Ă����悤�ȎW�R�Ƃ��������b���v���N�������肷��̂����A���̌o���܂��t���܂ɂ��Ăǂ��U���Ă��o�Ă��Ȃ��B�P������������̓X�b�J���J���ɋ߂��B�����̑�n�����������Ă��ꂽ��Ȃ��A�ȂǂƊ����鍡�����̍��ł���B |
|
|
|
The���s
�@�Q�O�O�X�N�̃V�����@�[�E�B�[�N���O�B�L�����v�ꉡ�̃f���g�R�[���ɕt������́u�Œ�S���v����ɗ�����邱�ƂɂȂ����@�Ǝ������A�R���Ԃ̒����E�p�g���[���ŁA�O�����P�U�p�̈�ԑ傫�ȃI�X���ɂ킩�ɓ�����ω������A�V�������Ղ������ł��Ȃ��Ȃ����B�����������Ƃ͐��b�łƂ��ǂ�����B�f���g�R�[���_�n�ȂǂŎ����E���E���Ƃ����������ŕ�����邾���ŁA���̔_�n����p�������̂��B�T�ΑO��̃I�X�̎�O�}�Ɛ��肵�����̃N�}�A���́A���ɂ��Ȃ�̌x���S�������Ă���̂����m��Ȃ��B����A�u�������̐X�v�̋��E��D���悤�ɍs�������Ԃ�������ȏ��^�̃N�}�́A���ς�炸�s�p�S�ȍs�����Ƃ��Ă����B
�@�����ŁA����ژ_�������サ���B���̃N�}�͊��ɒP�Ƃœ����Ă��铖�Ύq���������A�e���̎��n�P���Ƃ��Ă͂����Ă����������B���̃N�}�Ȃ�A�����ǂ��]��ł�����l�ł�������ǂ�������B�N�}�����Ύq�A�@�����Ύq�B�@�̂ق���2�����قǔN�������A���݂����w�Ԃɂ͂����`�����X���B�܂�A���̃o�b�N�A�b�v�̌��A�e���̊@�Ƀq�O�}�̓�����U�����������ނɂȂ��Ă��炨���ƁA���͍l�����B����܂ł̂悤�ɁA�P�Ƀq�O�}�ƑΛ����ɂݍ����̂ł͂Ȃ��A���ۂɈЊd�⌡�������ăq�O�}�̓������R���g���[�����邱�Ƃ��w�����������̂��B���̌P���ۑ�́A���̎���班����������Ɠ��ŁA���̔N�e���ꂵ���P�Δ��̎�O�}�̂����ǂ��炩�ōs���Z�i���������A�K�v�\���ȏ����������Ă����̂ŁA�����S�ȓ��Ύq�ōs�����Ƃ����͑I�B
�@�ʏ�A���̎�̌P���́A�͔͂ƂȂ銮�����ꂽ�x�A�h�b�O�ɕt�����Ċw����B���A����ȃx�A�h�b�O�͂ǂ��ɂ����Ȃ��B�Ƃ���A���̕��@�͂ЂƂB���ۂ̌���Ńq�O�}�ɓ��āA������x�̃��X�N�����m�Ŋw���邵���Ȃ��B�R�̊댯�͑S�Ă��̂悤�Ɋ@�͊w��ł������A���ہA�{���Ɏ��H�Ő�����`�Őg�ɂ���ɂ͂��ꂵ���Ȃ������B
�@�����A�ߌ�̃p�g���[���B�O���܂ł̍��Ւ����Ō��������̌̂̈ړ����[�g�𒍈Ӑ[���i��ł���ƁA�O���S�O���̃T�T�M���K�T�b�Ɖ������Ă��B�����𒍈ӂ��Č���ƁA�h�����č����e�������̂��������B���߂��I�ǂ��������s���̂ɍœK�Ȉʒu�W�B�N�}�̌������ɂ͈�{�̗ѓ��������Ă��āA������z����ΎR�̎ΖʁB���Ɗ@�̔w��ɃN�}�o�v�ŕ����ꂽ�����Ɓu�������̐X�v���������B���͂��傤�lj��ɐ����A�@�ƃq�O�}�͂��݂��ɑ����k���Ȃ��ʒu�W���������A�X�v���[�͏\���g���邻�敗�B�����A�ЂƂA���̃N�}�͎����z�����Ă������A�ǂ����ς����Ă��傫���B������������A�c�����̃N�}�����m��Ȃ��Ɗ��������A���̂܂܍s�����Ƃɂ����B
�@�@���O���ٕ̈ςɋC�����A��̐�������o���ē����グ�A�l�����Ă��̕����𒍎������B�����������ɂ��邳���i���Ȃ��̂��@�̂����Ƃ���B���ɍl���鎞�Ԃ�^���Ă����B���͂n�j�B�����������������B�����A���r���[�ɖ��������T�T���ז��������B���[�V�����ǂ����邩�c�c���̒��ł̓��[�V�����@�̓�����W����B���́A���x���̊@�̌o����M�p���A�ŏI�I�Ƀ��[�V�����t���[�ɂ��Ċ@�ɂ�点�邱�Ƃɂ����B
�@���̓��[�V����Z�������A����ō��}�𑗂��ĐÂ��ɕ����o�����B�@�͊��ɓːi���[�h�ɓ��肩���Ă������A�܂����肪���҂��c�����Ă��Ȃ��l�q�������B10���قǐi�Ƃ��A���������ς�������A�@���Ⴂ�X�萺���͂��߂��B���͊@�̔w���Ɏ�����A���[�V���̋�����O���Ɠ����ɁA�u�͂��I�͂��I�v�Ƃ������̂悤�Ƀq�O�}�ɂԂ����B�@�͂܂�ȃT�T�ɓ˂����݁A�܂�������ɃN�}�̂ق��֑������B
�@�N�}�͂���ɋC�t���A�R���֓��S�A�����āA�ѓ��֏o���O�ł�����Ɍ����������B����܂ł̃p�^�[���ʂ�B���͂������炾�B�@�����E�ɓ����Č������Ă���̂��������B����ȓ����͋����Ă��Ȃ��A���̌��̖{�\���B�����v�����Ƃ��A�������q�O�}�������ŗ����オ�����B�u�����I�v
�@���́A�~�X��Ƃ����B�ǂ����Ă����������ɋ���H�ƈ�u�v�������A��l�ɃJ���}�c�̊��ɉ�荞�݃X�v���[����Ɏ�����B���̃G���A����p���������͂��̂P�U�p���A�����ɂ����̂��B�����ł́A�e���̗��K��ɂ͂Ȃ�Ȃ��B�u�@�I�b�������I�v�Ǝ��͋��сA�g�̂��ْ��������B�N�}��O�ɂȂ����@�́u�Ăсv�������Ȃ��������Ƃ��Ȃ��B���b�̊Ԃ������Ċ@��������ɑ����Ă���̂�������ꂽ�B���A���̂��Ƃ��q�O�}���ǂ��Ă��Ă���̂������B�@�̓��������������B�u�����ē�����v�ɂȂ��Ă��܂����̂��B�u�b�������I�v���͂�����x�A���̑��݂��N�}�Ɍ֎�����悤�ɉs���@���ĂсA���������猩�₷���J���}�c�̉��ɏo�āA����̃��b�N�������Ăقǂ����B
�@�@�͎��̉��łt�^�[�����A���̂܂܌��������čĂуN�}�����������B�N�}�͐����O���Ŏ������F�������~�߂����A�X�v���[�̎˒��ɓ����Ă��Ȃ������B�������ɏ����������Ă���B�N�}�͂��̏ꏊ�ʼnE�֍��ւƗ��������Ȃ��E���E�����������A���Ɗ@�A�̓����ɓːi������C�z�͂Ȃ������B�u�ז�������Ȃ�v�ƔO�������A�����m���Ă��A�@�͎��̌��ɉ�荞�ނ悤�ɍ��E�̌������s�����B�قƂ�Ǖ��͊������Ȃ������B����Ȃ炢����B�N�}���t�����Ǝ˒��ɓ������̂����}�ɁA�u�����ȁI�v�Ɠ{��A���̓X�v���[�̃g���K�[���������B�I�����W�̖����N�}�̂ق��ɕ��˂���Ă���ԂɁA������x�A���x�͖��炩�Ɋ@�ɓ{�����B�u�����ȁI�I�v
�@�q�O�}�͑S�g�̋ؓ����͂���������悤�ȑԓx���Ƃ������Ǝv���ƁA���̂܂ܐg�̂�h�炵�ē{���̂��Ƃ��K�������ē��S�����B
�@�N�}�ł͂Ȃ����A�@�͎��ْ̋��ɓ�������悤�Ɉ�ĂĂ����B������A���̒i�K�ł́A����̃R�}���h���Ƃ������A���ْ̋��x���Ċ����A�͂��߂ăR�}���h�������Ƃ����ӂ��������B���̈�A�ŗp�����R�}���h���قړ�u�b�������v�u�����ȁv�����A���̓�����F���@�͏�ɋC�����A����ɉ����ē������B
�@�u�@�B�����Łv�ƌĂB���̖T��ŃN�}�̓������������p���x�����Ă����@�́A�����Ƃ���̂悤�ȁA�������Ȃ悤�ȁA�˂��炢�̂悤�Ȋ�����Ď������グ���B���́A�����ڂ��ɂ��A�X�v���[���C�t���Ȃ����x���т��悤���B�J���ɂȂ����X�v���[���z���X�^�[�ɖ߂��Ċ@�Ƀ��[�V����t���A�@�̖ڂ�`�����B�X�v���[�͂����ė��тĂ��Ȃ��l�q�������B�u��[���A��[���v�Ǝ���������Ă�藧���オ��ƁA�����ʂ胊�[�V���ō��}�𑗂��āA����㯓����������߂����B
�@�ؗ��̒�������Ă���ƁA�}�Ɋ@�ɘb�����������Ȃ����B�u�����A�������̈ʒu�W�͋t���낤�H�@�x�A�h�b�O�̂��܂����{���Ȃ�O�Ȃ��v�@������߂��ʌ��̓����Ŋ@�͖������ɕ����Ă����B�u�����A�����Ă邩�H���̂̓X�v���[�̂����������B�c�c�܂��A�������v�@���̂܂ܕ����Ē����ɏo���B
�@���̎����ȗ��A���ɖړI�̓��Ύq�͂��̃G���A�Ɍ���邱�Ƃ͂Ȃ��A�V�����@�[�E�B�[�N���}���A���̌�܂��Ȃ��f���g�R�[��������ꂽ�B���炭�A����Ɩ㒅�̂�����16�p���A�@�̑���ɓ��Ύq��ǂ������Ă��܂����̂��낤�B���s�͎��s���������A����͐����ɂȂ��鎸�s�ł���B�@�͂܂�����W�����B���ꂩ�������������������B���̊Ԃɂ����d�˂������A����肭�炢�́B
�⑫�j
�@���̌�A���N�A�@�͓��l�̗Y�W�J�V�тɂȂ邪�A���߂Ă̎��Ɣ�ז��炩�Ɋԍ�������������Ƃ��悤�ɂȂ�A���Ă���ق����������S���Ă�����悤�ɂȂ����B�����āA�V�J�ƗV��ł���^���Œ��ɂł��u�J���I�v�̈ꐺ�Ŏ��̌��ɖ߂点�邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ����B
|
|
�E������K���w�ׁI
�@������k���Ȍv�Z�̂��Ǝ�O�}�̊���������s���Ă���Ƃ�����ۂ�^�����������A����ł͌����Ă��̂悤�Ȃ��Ƃ͂Ȃ��B�s���̎��Ԃ��炯�ŁA�ǂꂪ�s���łǂꂪ�v�悩�킩��Ȃ��Ȃ邱�Ƃ������B�s���̖��H���K�V�K�V�i��ł䂭�ƁA�Ȃ����v��ʂ�I����Ă��邱�Ƃ�����B
�@2008�N8���̏I���A�n�������ɗp������A������o�����͍���333��ۋC�ɑ����Ă����B�Ƃ��낪�A�����ɓ�����5�q���䂩�Ȃ������ɁA�����I�Ǝv���ē��H�e�ɖڂ��ڂ��ƁA�����ɂ͈ꓪ�̃q�O�}�����H��n�肽�����ɁA�s���߂��鎄�̃N���}�����Ă����B���͎�������̃N�}��ǂ������A�N�}�̓N�}�Ŏ���Ď���ǂ����B���̂悤�ȃq�O�}�Ƃ̃A�C�R���^�N�g�́A�������߂Ă��B
�@���͂������u���[�L��ŁA�N���}��H���Ɏ~�߁A���̓ۋC�ȃq�O�}���ǂ�������肩���߂Ă����B����ƁA�q�O�}�͂����ނ�ɃN���}�̓r�ꂽ������n��A���̂܂ܐ��H���z���Ĥ���̐����Ŏ��n���I�����_�n�ɓ����Ă��܂����B
�@���i�A���O�}�́\�\�\�v�Ƃ܂��܂����₩�ɘb�����̌�����A��o�J�F�I�v�Ƃ������t���o�Ă���̂ͤ���������Ƃ����B
�@����̃o�J�F���I����ȂƂ���ʼn�����Ƃ�I�I�v
�@���́A�ς�ł�����O�}����Z�b�g�����Ɋ����č������~��A�o�J�F�A���Ƃ���O�}�̕����������B
�@���̂܂ܗN�ʐ�֍~��Ďp�����������Ƃ��낾�낤���A���̎�O�}�͂����ɓ���Ƃ��ɔh��ɓd�C��ɐG��Ă���B����ŁA������x�d�C���˔j���ē�����E�C���N���Ă��Ȃ��B�������փE���E���������փE���E���A�v����ɁA�_�n�ɕ����߂��Ă��܂����̂��B
�@���������P�[�X�ł́A�ǂ������̃V�t�g�Ȃ�Ă���Ă����Ȃ��B���h���Ȗ쎟�n���W�܂�o���Ɖ����N���邩�킩��Ȃ����炾�B���́A���̎������Ă���7���̍����ʂ̂����O���܂���������j���A��O�}�̗l�q�����Ă݂��B��O�}�͊ՎU�Ƃ����_�n�̒����E���E�����邾���ŁA����Ɍ������̗т֓˂����ē�����E�C���N���Ă��Ȃ��悤�������B
�50m����A�������c�c�v
�@���͎�O�}�ɋ߂Â��č\���A�����ʂɓ_����Ǝl�\����Y��ė͈�t��O�}�Ɍ����ē������B�Ƃ��낪�A���̔��q���m��Ȃ����A���̈�Ɍ��荌���ʂ͐����悭��сA���܂��ɃR���g���[���܂Œ�܂��āA��O�}�̑����߂��܂Ŕ��Œn�ʂɓ]�������B
������A�}�Y�C�I�v
�@��O�}�́A������ǂ��납���̓��̂̒m��Ȃ����̂ɋ����������A���ɂ��@��˂��o���ăN���N���k�������Ȑ������B
�u���J�[�[�[�[�[���I�I�v
�@���͎����̐����̃G�l���M�[��S����O�}�ɔ��U���Ԃ������ŁA�킯��������Ȃ����������狩�сA��l�Ɏ�O�}�̕��֓{���̔@�������Ă����B
�@���̌`���ɋ�������O�}�͐������֔�ёނ��A���傤�ǂ��̎��A�����ʂ��y���B���ł̂Ƃ���Ŏ�O�}�̕@�𐁂�����Ƃ��낾�������A����ł���O�}�͓d�C����z���ē����悤�Ƃ͂��Ȃ������B
�@���̈ꔭ�ŁA���͖����Ɏv�����\�\�\���̃N�}�͖��������m��Ȃ��c�c
�@����Ȃ��Ƃ�����Ă���ƁA��O�}���ˑR�����ɈЊd�̕\����������B���̐���`�����ƌ���ƁA���̑�����k�������쎟�n�炵��������ق�W�܂��Ă����B�Ȃ���O�}�����ł͂Ȃ��쎟�n���Њd������̂��킩��Ȃ��������A����Ŗ����x���B����ȏ㒷�������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B
�@���͍Ō�̍����ʂ𒍈Ӑ[���y���ĎˎE�\�Ȕ_�n�̋��֎�O�}��U�����A�삯���ҋ@���Ă����n���^�[�ɓ����������B
��ˎE���A��낵�����肢���܂��v
�@���͎�O�}��������n���Ă���50���Ԃ��̃N�}�Ɗւ��A���ǁA��ǂ�������Ɏ��s�����B��Ȃ������B
�@���́A�ꓪ�̖��C�Ȏ�O�}�����Ȃ��A����ƈ����ւ��ɁA�����́u�ǂ������v�̎�_��S��m�����B
�@�������̈�{���Ȃ��J�����ꏊ�ł́u�ǂ������v�\�\�\���̎�_�����������D���x�A�h�b�O���B

�u��O�}�v�Ɓu�o�J�F�v
�@����܂ŏq�ׂ��悤�Ɏ��̑Ώۂ́A�v����ɐl������̋���ߒ��̎�O�}���B�R���́u�ł��F�v�͋����≽���͂��邪�A�o�R�҂�ނ�l�ƍI���܂荇�������ĎR�̒��ł��D���Ȃ悤�ɕ�炵�Ă��������B���͂Ƃɂ������ɂ���O�}���B��O�}�́A�l������ł��Ȃ薳�x���ȍs�����Ƃ邱�Ƃ�����̂ŁA�_�o���g�킴��Ȃ��B�V�������Ղɑ��ẮA��Ȃ菬�Ȃ�ǐՂ���̂����ʂ��B
�@�u����́A��̎�O�}���ȁv�Ɛ��܂�����Ŏn�܂��āA�V�������ނ�ǂ��Ă䂭���Ƃ����邪�A����ɍ��ՂƉ�X�̎��ԍ����k�܂�A�ӂƌ�����ɂ��̎�O�}�����������ꍇ������B��̋}��o�ꂸ�A�����̘e�ɉ����ăE���E���ƕ����Ă���B������A�̂ǂ��Ȍߌ�̏��w���̒ʊw���Ԃɂ��B����܂Łu��O�}�A��O�}�v�Ƒ����������l�q�Ō����Ă������̌�����˔@�u�o�J�F�I�v�Əo��u�Ԃ��B
�@�{�S�́A���̃o�J�F�ɋ삯����Ă����̗����̂ق���������Ŗ�����������������������A���܂��ɓۋC�Ȋ�̕@��Ɋ��݂��Ēǂ����������Ƃ���Ȃ̂����A�������ɂ����܂ł͂��Ȃ��B
�@��O�}�ɑ��ē{���Ă���킯�ł͂Ȃ����A���ɃJ�b�ƌ����̂ڂ�A���̂Ă�����̖т��t���̂�������̂͊m�����B
�u�o�J�F�v�Ƃ͍����Ђǂ��������̂悤�Ɏv���邾�낤���A�v����ɁA���m�Ŗ��C�ŁA�܂�l�̋��낵�����������������m�炸�A���܂�^���������ɂ����ۋC�ɐU�镑���ĕ�炷�A����Ӗ��u��O�}�炵����O�}�v�̂��Ƃ��B������悯���ɐ������Ă�肽���ƏՓ����N���B
|
|
|
�@
�@
�@�]
�@�x�A�J���g���[�Ŏ��]�Ԃ͊댯�B����A������̂��댯�B����͊m���ŁA��X���͂��������Ă���B����̌o���ɂ��Ƃ�����傫���B����3�ƂȂ��ăq�O�}�̒ǂ����������Ȃ��Ă���@�ł��A���������́A���x�q���q���������킩��Ȃ��B���̂����q�O�}�ɂ͂�����đ���������̂ł͂Ƃ��A���܂�ɖ�����ɃN�}�̐��ޖ��ɓːi���Ă����̂ŁA�{�����N�}����яo�Ă���̂ł͂Ƃ��B���]�ԉ]�X�ɂ��Ă��A�����g�������̎U���i�T�C�N�����O�H�j�ʼn��x�ƂȂ��̌����Ă��邩�炾�B
�@�����g�́A�댯�Ȍ��A��Ŏ��]�Ԃ��g���ē���I�ɗѓ��𑖂��Ă���B���鎞�A�n���^�[�̉c�ދ������֍s������A�u���܂��A����Ȃ��Ƃ���Ă���A���̂����N�}�ɋ������v�Ɛe�̂悤�ȋ������̂悤�Ȍ��t����������B�ǂ���猩��ꂽ�炵���B���́A������ăN�X���Ə��A�u�����A���x�������Ă܂���v�ƈꌾ�������B������������l�������܂����݂����Ȑ^��Ō�������A���N�X���ƁB
�@���ہA�����Ȃ̂��B�ѓ��e�̃t�L��H�ׂĂ��邱�Ƃ͕��ʂ����A�ѓ���ɒʂ���ڂ̌`�Ńq�O�}�������ӂ������Ă�����A���[�̂������Ɏ�O�}������������Ă��Ėڂ��`�����ƍ�������B���グ���g�h�}�c�ɍ��X�Ɠo���Ă�����A�T�T�M���瓪�����o���Ă���������Ă�����A�e�̐����܂�ōs�������Ă������Ƃ��B�܂��A���낢��ȃp�^�[��������B
�@�Ƃ��낪�A�悭�����}�j���A���ʂ�ɂ��߂��������Ƃ��ӊO�Ə��Ȃ��B
�@�T���Ƃ����̂̓X�g���X���������邽�߂̉^�����������Ȃ��B�����āA���̗ʂ������B1��̃W���M���O�ŁA�~�ł��Ăł�����10�q�B���q�ɂ����20�q���z���邱�Ƃ��������Ȃ��B
�@������A�@��A��ėѓ������]�ԂŃW���M���O�����Ă���Ƃ��A�ӂƗѓ��e�ɖڂ��������A10m�قǐ�̗ѓ��e��1���̎�O�}��������~�߂ĘȂ�ł����B����20�q�قǂő����Ă��邩��A���錩�邤���ɋ߂Â��āA���������܂ŗ����B���R�A�N�}�Ǝ��͖ڂ����������A���������悩�����̂������悩�����̂��A�@�͂��̑��݂ɋC�t���Ă��Ȃ������B����ŁA���b�L�[�Ƃ���Ɏ��͒m����ł�����ʂ�߂����B�u���[�L���y�_�������̂܂܁B�����āA������ƍs�����Ƃ���ʼn����ɋC�t�����@�ɁuHike!�v�Ɛ��������A�������牽�H��ʊ�ʼn����������B���Ǝ�O�}�̍ł��ڋ߂����Ƃ��ŁA2m�قǂ��������낤�B�@�]�ƈꌾ�Ō����Ă��܂��ȒP�����A�ł��}�Y�C�Ǝv����I���̓u���[�L�Ɏ����邱�Ƃ������B�ق��1�b���炸�̊ԂɁA���낢����ώ@���A��l�ɓ����B���̃P�[�X�ł́A�u�m����v�������킯�����A���炭�A���ꂪ�B��A�㒅���N�����Ȃ����@���������낤�B���̃p�^�[���ł͌o���I�ɁA��������������O�}������̋A���҂��\���Ă��邱�Ƃ��l����ꂽ���A�A��ɂ͐Ռ`�Ȃ������Ă����̂ŁA��₱�������Ƃ����Ȃ��čςB
�@�@��1���z�������āA�������ѓ����D�u�Ƒ����Ă�����A�P�c�����o���ėѓ��e�̃t�L��H�ׂĂ���N�}�ɏo�������B�������������͂܂�50m���炢�������̂ŁA���̓u���[�L�������A�u�@�A�~�܂�I�v�ƃX�}�[�g�ɃR�}���h�������Ă݂��B�Ƃ��낪�A���̍��̊@�́A���傤�Ǒ̊i������l�œ����q���̎����B�u�~�܂�v�ƌ������u�ԂɃu���[�L�ȏ�̗͂ŃO�C�O�C��������͂��߁A�N�}�Ƃ̋������ǂ�ǂ�k�܂����B�u�~�܂�I�I�v�u�~�܂���Č����Ă邾��I�v�Ƒ������������������ŁA�N�}�͂�����Ɍ�������A��͂�ڂ��������B����Ń��[�V���������A�E��Ńu���[�L�����A���̍��́A���̉E�u���[�L���O�ւ̂܂܂������̂ŁA20m���炢�̂Ƃ���łƂ��Ƃ��h��ɓ]��ł��܂����B�n�ʂɔ�������Ȃ���A�ꉞ�A��O�}�ɖڂ��������A����O���Ζʂ�o�肩���A���R�Ƃ����悤�ȕ\��ł�����̑����߂Ă����B���́A�N�}�Ȃǂǂ��ł����������ɂȂ��āA�@����������B���łɁA�u����ȂɌ����o�Ă邾�낤�I���]�Ԃ���ꂽ���B�ǂ����Ă����I�~�܂�ƌ�������~�܂�I�I�v�Ƒ吺�ŋ�s�܂Ō������B���ʁA���Ɗ@�̖㒅�̂����ŁA�N�}�Ƃ̖㒅�͖Y�ꋎ��ꂽ�悤�ɉ���ł����B���̎�����A�u���[�L�����E����ւ��A�E��Ō��u���[�L�𑀍�ł���悤�ɂ����B
�@�������������̎�����E���Ă����ƁA���Ȃ�q�O�}�Ƃ̖㒅����̕��@�͍L���邪�A�ǂ�����ă}�j���A���ɐ��荞�߂��������킩��Ȃ��B�Ջ@���ρB���ꂪ�~�\�Ȃ̂����E�E�E�E��������ʓ_������Ƃ���A�o�������q�O�}�̐S���ɂ����C�����Ă���Ƃ������Ƃ��낤�B���̐S���Ύ����I�E�������˓I�ɓǂ݁A�ł����S�ȕ��@���u�ԓI�ɑI�����Ă���悤�ȋC������B
�@���̌o�����炷��ƁAbluff charge�̑O���Ɂu�l�����ށv�悤�Ȃ����������邱�Ƃ������B����܂ŁA��r�I�����Ă����q�O�}���������u�~�߂āA�u�����l���Ă�̂��ȁH�v�Ǝv�����u�ԂɁA�g��|���ēːi�J�n�A�Ȃ�Ă������Ƃ��ӊO�Ƒ����̂��B�܂�Abluff
charge�Ƃ����̂́A���Ȃ��Ƃ��ꕔ�Ɋւ��Ă͏������˓I�ł͂Ȃ��A�����܂ōl�������̐헪�Ȃ̂ł͂Ȃ����낤���H�@�ubluff charge������Ă�낤�v�ƍl��������Ԃ��Ȃ��A�ʂ�߂�����A���邢�͌��������̂悤�ɖ�������`�ŐU�镑������A���������v�f�����̏퓅��i�Ƃ��đ��݂���悤�Ɏv���B���o�ł����u�����Ղ�l�v�A�q�O�}�Ƃ̊Ԃ̐S���W�ł��̏�Ԃ�����Ă���̂��Ǝv���B
�@�����A����̐S���Ə��u���ɍl���Ă̗Ջ@���ρE�@�]�Ƃ����̂́A��͂�}�j���A�������ɂ����B
|
|
�t���[�Y���X�g�[�N�iFreeze��Stoke�j
�@�t���[�Y�Ƃ����̂́u�~�܂�I�����ȁI�v�Ƃ����悤�ȂƂ��ɖ��ߌ`�ł悭�g���B�X�g�[�N�́A�X�g�[�J�[�Ɠ����ꌹ�Łu�E�ъ��v�Ƃ����Ӗ��ł���B�����q�O�}�ɑ��čs���u�t���[�Y���X�g�[�N�v�Ƃ����̂́A�܂�Ƃ���A���{�Ō����u����܂��]�v�ł���B
�@���́A���̃t���[�Y���X�g�[�N���A�A���X�J�ŕK�v�ɔ����Ċo�������Ƃ��B
�@�������������e�����ɂ����̂͊w������A�k�Ă𗬂�郆�[�R����̂Ƃ���x���������B���̉͂̂قƂ�ŋ��R���������V�A�n�̈ږ��̑��q�Ɂu����͂��₶�̌`�����v�Ɖ������̎U�e�ƃX���b�O�ƂƂ��ɓn���ꂽ�̂��A�u�o�C�J���v�Ƃ����A�����ɂ����V�A�I�Ȗ��̃V���b�g�K���������B�X���b�O�͂������O���Y���[�̌�g�p�A�U�e�͒��ȂǐH�Ɗm�ۂ̂��߂̂��܂����B
�@�ގ��g�͏��������ɏo�v�����^�̃O���Y���[���u�ł�����v�Ɛg�U��t���ŕ\�����A���������炵����ɋ���Ă���悤�������B���Ƒ��_���e�Ȃ��Ƀt���t�����Ă���̂�S�z���āA���₶�̌`����ɂ��܂��݂��Ă��ꂽ�̂��낤�B
�@�ނ̃o�C�J���͍����̏e�ɂ͂Ȃ��Ȃ��Ȃ����i�������Ă��āA���c�e�̔@���P�����ŁA���ۂɓ�����̂�������Ȃ��̂��킩��Ȃ��e���������A���̏e�������Ȃ���u���C�N�A�b�v����̃��[�R������𗷂������o��������B
�@���C�t���̖���Ȃ礒ʏ�400m���O�̃V�J���ꔭ�ő��|�����邱�Ƃ��ł���B�Ƃ��낪�A�����o�C�J���ȍ~�A���X�J�Ȃǂŗp���Ă����̂͌�g�ړI�����C���̉��Ȃ��s���Ȃ�Remington��870�Ƃ����ėp�̃V���b�g�K���ŁA���̎˒��͒����Ă�100m���x�B��g��30m�ȓ��ŗp���邱�Ƃ�z�肵�A7�A�˂��ł���悤�p�[�c��I�сA���R�X�R�[�v�����Ă͂��Ȃ������B
�@������A���̌P������Ȃ��̂��B���Ԃ͂ɂ���Ɗ��m�Ȃ̂����A�{�l�͐^���ɂ���Ă������ƂȂ̂ŏ����Ă݂悤�B
�@�܂��A�������O�{�ɍ����̈قȂ�I��ł��t����B�����̃C���[�W�́A���悻�q�O�}���l����ԂƗ����オ�����Ƃ��̓�����菭���Ⴂ�����B�I�͋ʂł��i�{�[���̒[��ł����ł������B�����āA�V���b�g�K���ɐ����̒e�ۂ����߁A�͂��߂̈ꔭ��20�`30m�̋������痧�˂Œʏ�̎ˌ��p���Ō��B�ڈȍ~�́A�������瑦�|���s���O�i���U�j�����ɉ�荞��A�|�ꍞ�肵�Ȃ���l�X�ȑԐ�����l�X�ȃ^�C�~���O�ŕʁX�̎��̓I�����B7�����ƒe�����������Ȃ��̂ŁA���������͂R�`4���B�����5�b�O��ł��ꂼ��̓I�ɓ��Ă���K���B�������A�C���g�������˂�̂ŁA�I���Ă����Ă���ӎ��͂Ȃ��B�{���ɂ����Ƀq�O�}������C���[�W�ŏe�������邪�A���q�������Ƃ���7����10�b�ȓ��ɕʁX��10�p�قǂ̓I�ɑS�e���Ă邱�Ƃ��ł����B
�@���{�ł̓X���b�O�����10����20�����ƌ����ɂ��Ƃ������o���n���^�[���������A���̏ꍇ�͂��������P�\���Ȃ������̂Ť�Ђǂ��ƈ��100���ȏ�̃X���b�O�����̗��K�ŏ�����肵���B
�@�ǂ����낤�B�������݂����Ŋ��m���낤�H�@�ł��A��g�ŏe����g�����Ă������Ƃ́A�قƂ�ǂ����瑤�̗��z�I�ȑԐ��Ō��Ă邱�Ƃ͂Ȃ��Ǝv���Ă��������������̂��B
�@���̎�̎t���̓n���e�B���O�K�C�h������Ă��āA�A���X�J�ł���Ɍ��鐦�r���������A���̔ނƃV�J�ɏo������ƁA�ނ͎���̎˒��̃V�J���������āA���Ɏd���߂����悤�Ƃ��A���͎��Ń��C�t���ɔw�������V���b�g�K���ɂ���������B�Ƃ��낪�A�߂������Ȏ˒��͍ő�100m�B����ŁA�Ƃɂ����V�J�ɋC�Â��ꂸ�ڋ߂���K�v������A�e�̉��˂̐��x���A�����ɖ쐶�����ɋ߂Â��������낢��ȕ��@�Ő����P�������B
�@�쐶�����ɋ߂Â��ɂ́A����@������B��́A���̓����̍s����ǂݐ��āA�œK�ȏꏊ�ő҂��\������@�B������́A�M�╗���t��ɂƂ��Ă�������ƔE�ъ����@�B����𤂻�̂܂�Ɏg���ƁA���ꂼ��u�҂��̗v�u�ǂ��̗v�ȂǂƂ����B�ǂ�����A�V���b�g�K���ł�낤�Ƃ���ƂȂ��Ȃ���Փx���������A�������s�̃N���}�ɂ�颗����£�ɔ�ׂ�Γr�����Ȃ��ʔ����B
�@�����L�`�K�C���݂��P���̂������Ŏ��͖쐶�����ɋ߂Â�����Ȃ�̋Z�p��g�ɂ������A���݂ł́A������ӂ̃V�J����ɒP�ɐ����ŁA�Ђǂ��Ƃ��́A�����Ǝ��̘[�ɍ����ăV�J��҂��A�ڂ̑O��ʂ�߂���V�J�̘e�����w�ł��ċV�����������邽�߂����ɁA���̂��������̓��Z���s�g���Ă���B
�@�V�J�͖ڂ������������A���S�ɓ����Ȃ����̂ɑ��ĈӊO�Ɠ݊��ŁA���𗧂Ă��������ƃV�J�̈ړ����[�g�����v�Z����A���ɂ����ꂩ�����ĐÂ��Ƀ{�[�b�Ɨ����Ă��邾���ŁA�ق�̐����[�g���̋������܂��������ɋC�Â����������邱�Ƃ����\����B���̎���e�ɂ���I�V�̌܉E�q��ɐZ�����Ă����{�[�b�ƍl���������Ă��Ă��������Ƃ��N����B�{�B�̢�؉����v��≻���v�͕ʂɃ{�[�b�Ƃ��Ă���킯�ł͂Ȃ����낤���A���̏ꍇ�͂��̃{�[�b�Ƃ����̂����\�~�\�����m��Ȃ��B
�@�t�ɂ����炩��߂Â��ꍇ�́A�����������A���p�𗘗p���Ȃ��特�𗧂Ă��ɂ��傤�ǔL�̕��̂ŋɂ߂Ă������Ƃ�������ŋ߂Â��A����Ȃ�̋����܂ŃV�J�ɋC�Â��ꂸ�߂Â����Ƃ��ł���B
�@�q�O�}�̎��͂̓V�J���͂邩�Ɉ����A���̍�Ƃ͂���ɗe�Ղ����m��Ȃ��B�߂Â��̂͗e�Ղł��A�C�Â��ꂽ�Ƃ��̑Ή��͗e�Ղł͂Ȃ����B
�@�Ⴆ�A���E�̊J�����L���q���n��150m�̋����ɖq����H��ł���q�O�}���������ꍇ�ȂǂɁA�t���[�Y���X�g�[�N�̏o�ԂƂȂ�B����́A��O�}����Ɍ��������Ƃł͂Ȃ��B
�@�q�O�}�Ƃ����̂́A���ɑ��{��H�ׂ�Ƃ��ɂ́A���䖲���ł͐H�ׂȂ��B���̎��Ԍ������ĐH�ׂ������グ�A��������O���b�Ɗm�F���Ă܂��������A�܂����̎��ԂŊ���グ�A�Ƃ�����Ȃ̂��B��قlj����Ɍx���S������Ȃ���A����𗥋V�ɂ���Ă����B������A�q�O�}���u���E��E�܁E���E��E���A�]�I�v�Ƃ������킯�ł͂Ȃ����A�^�C�~���O�����v����āA�q�O�}���q����H�ׂĂ���Ƃ��ɂ�������E�ъ��A����グ��u�ԂɊ��S�ɐÎ~����A�q�O�}�ɋC�Â��ꂸ���Ȃ�̋����܂ŋ߂Â����Ƃ��ł���B
�@���ۂ́A�q�O�}�����R�Ɨ����Ă��鎄�ɋC�Â����Ƃ��ɂ��܂�ؔ�����悤�ȋ����܂ŋ߂Â��Ɗ댯�Ȃ��߁A�t���[�Y���X�g�[�N�Ńq�O�}�ɐڋ߂ł�����E�������m���߂悤�Ǝv�������Ƃ́A���ɂ��Ȃ��B�������������A������������A�ނ�Ƃ̕��Ńq�O�}�̘e������������邭�炢�ɂ܂ŋ߂Â���A�����m��Ȃ��B
�@�P�Ȃ�X�g�[�L���O�ŁA�Ⴆ�Α�̃t�L��H�ו����q�O�}�ɔ��������荞��ő҂��\���A�������蕨�A�ɉB��Ċώ@����ꍇ��40m�ȉ��܂ŋ߂Â����Ƃ����邪�A�q���n�Ȃǂŋ߂Â��������Ńq�O�}�Ɏ����C�Â�����Ƃ��́A���낢��ȍD���������ׂđ����Ă��A���̏ꍇ�͂�������80���O��܂ł��B���������q�O�}���n�m���Ă���l���A���������e��Ŗ��d�Ȑl�Ȃ�A����ɋ������k�߂邱�Ƃ��ł���̂��낤���B
�@80m�Ƃ����͍̂������������邾�낤���A����ɂ̓q�O�}�̋��������J���N���ɂȂ��Ă���B�q�O�}�̋������\�\�\�Ⴆ�q�O�}���ؔ�����q�g�Ƃ̋����́A���E�̊J�����ꏊ�Œ����A�M��ؗ��̂���ꏊ�ł͒Z���B����͌o�����猩�������̖@���ŁA�Ⴆ�A�c���h���̃f���v�X�^�[�n�C�E�F�C�����ł͒����A�T�T�M��������k�C���ł͊T���ĒZ���B
�@��q�̂悤�ɁA�k�C���̃q�O�}�ɓ����I�ȁu���ސ헪�v�Ƃ����̂�����B�T�T�̖��������k�C���ł́A�q�O�}�����̐헪�����I�Ɏg���̂����A�t�ɍl����ƁA���̕������q�O�}�ɂƂ��Ă͐헪�̑I�������������ƂɂȂ�A�L���Ƃ������Ƃ��ł���B���Ȃ��Ƃ��q�O�}�́A���E�̗����Ȃ��ꏊ�ł́A�q�g�ɑ��Ď������L���Ɗ����Ă���B������A���Ȃ�̎��ߋ����܂Őؔ����Ăǂ��������邱�Ƃ����Ȃ��̂��B
�@�t�Ƀq�g�́A���E�̗����Ȃ��ꏊ�ł́\�\�\�Ⴆ�Ζ�ԂƂ��A�q�O�}�ɑ��Ď������s�����Ɖ��ƂȂ������Ă��锤���B�s�����Ǝv�����炱���A�q�O�}���q�g���ْ��x�������A������Ƃ��������Őؔ�����s���𔗂��Ă��܂��̂��B
�@���������āA����q�O�}�ɑ��āA���Ɏ����X�ѓ��ŕ��ʂɂ��Ƃ�ł��鋗����40m���Ƃ���A���̓����q�O�}�ƊJ�����q���n�̂ǐ^�œ����悤�ɂ��Ƃ���s�����Ƃ���A���̋�����2�`3�{���x�ɐL�тĂ��܂��B�����q�O�}��������ɓːi���Ă����Ƃ��A���Ƃ��Ďg������{�Ȃ��Ƃ����̂��A������L���������B
�@���ہA�R��Ŏ����܂��܂��S�n�悭�q�O�}�Ƃ��Ƃ���s���鋗���́A�����}�[�W�����Ƃ��Ă�������40m���炢���낤�B���̋����́A�O�����Č��߂Ă���킯�ł͂Ȃ��A���̎��X�̏ɂ���Ď��R�ɕς��B�����A50m��蒷���Ƣ�����Ȃ��B���������l�߂悤���ȁv�Ƃ����C�ɂȂ邵�A30m�ł͂��N�}�X�v���[�̃g���K�[�Ɏw�����������Ȃ�B��������10m�̍������A���ꂪ���\�A�S���I�ɂ͉_�D�̍��Ȃ̂��B�������A��̃q�O�}�������낷�ʒu�ł͂��������Z���A��������グ��悤�ȏꍇ�͒����B
�@����D�ꂽ�N�}�����́A�N�}�������z�̋�����30m���Ƙb���Ă��ꂽ�B���́A���̋������������ŁA�ނ�A�]�̂܂Ȃ����Ō����B���̋����ŁA�ނ͗�ÂɃq�O�}���ώ@���A�Â܂肩�������C�����Ő����̋������Ȃ��e�����Ă�Ƃ������Ƃ��B���炭�A�ނɂƂ��Ă���30m�Ƃ����������}�[�W�����܂߂��������낤�B���ہA���Ĕނ̓q�O�}�̈ړ����[�g�𐔏\���[�g���ǂݑ��Ȃ��A�҂��\�����ˍ��̂ق�̐����[�g������M����p���������q�O�}�̉������ÂɌ��������Ďd���߂����Ƃ�����B�s���ɂȂ����q�O�}���ނ̎ˍ��ɓ|�ꍞ�Ƃ������礂��Ȃ肫��ǂ��������Ǝv���B
�@��{�I�ɁA���݂��ɕs���̂�����u�o�b�^�������v�Ńq�O�}�Ƃ́u���Ƃ�v�u�R���g���[���v���s���Ƃ��́A�������ǂ������Ă��邩�ł͂Ȃ��A�q�O�}���������ǂ������Ă��邩���܂���ɍl����B�q�O�}�����L���Ńq�O�}�̐S���Ƃ��ė]�T����������ɌX���Ă���ł́A�q�O�}�ɂ͑����̐헪���c����Ă��āA�ʏ�̃o�b�^�������Ȃ�ނ���댯�x�͒Ⴂ�B�q�O�}�̙�l�̍U���J�n�Ȃǂ̊댯�x�������̂́A�q�O�}�̑I�����������Ă���Ƃ����B���̏ꍇ�A�܂��͂ł��邾�������q�O�}���ɑI������^���A�܂�A�q�O�}���ɑI�����ς˂�`�őΉ�����̂��ł����S�ȕ��@���B
�@�ł́A��ϐ���A�T���ăq�O�}�ɗL���ɂȂ��Ă���k�C���̒n�`�E�A�����A�q�g�ɂƂ��ėL�����s�����H�Ƃ����ƁA�q�O�}�̎���������x�������������Ή��ł���R�؍̂��ނ�l�ɂƂ��Ă͗L���A�q�O�}�����Ƃ��Ƃ���n���^�[�ɂƂ��Ă͕s���A�Ƃ��������̌��ʂɂȂ�B�������A�N���}�œ����u���u���Ɨ����Ă��邾���̃n���^�[�͘_�O���B�q�O�}�Ƃ̖㒅����������q�g�ɂ͗L���A�㒅���N���������q�g�ɂ͕s���Ƃ������ƂɂȂ邪�A�q�O�}���ؔ����Ȃ��Ƃ������A�q�g�ɂ��q�O�}�ɂ��L���Ƃ����Ƃ���͈Ӗ��[�ȕ��������m��Ȃ��B
�@�q�O�}�ɑ���t���[�Y���X�g�[�N�́A�V�J����̑҂������ƈ���Đ����ł���Ă���̂ł͂Ȃ��B���낢��ړI�����邩�炾�B
�@��́A��苗���ł��̃q�O�}�����ɋC�������Ƃ��A�ǂ̂悤�Ȕ������������������o���e�X�g�B����ͤ��q�́u�ǂ������v�̃e�X�g�v�f�Ɠ����ŁA���̃q�O�}�̃q�g�ɑ���o�������ʂ邽�߂��B��������t���[�Y���X�g�[�N�Ɏ�������A�ŏI�I�Ƀq�O�}���P�c�������ē�����܂Ŏ��͈���������Ȃ��̂ŁA���ʓI�ɢ�쏜�v�f������v�f������������ƂɂȂ�B
�@��߂́A����q�O�}�̎��͌����B
�@��{�I�ɁA���������ĔE�ъ��̂́A�q�O�}������������Ă��Ȃ��Ƃ��������B�q�O�}������グ�Ă���������������Ă���Ƃ��́A���͊��S�ɐÎ~���Ă���B
�@����ł́A�q����150m�قǂ���t���[�Y���X�g�[�N�Ńq�O�}�ɏ��X�ɋ߂Â��A85���̋����ŁA�q�O�}�����S�ɂ�����������ėl�q�������������Ƃ��ɁA�q���n�̐^�ɗ������Â߂̃A�[�X�J���[�̈ߕ��𒅂������܂������F���ł��Ȃ������P�[�X������B���̂��Ƃ���A���̓q�O�}�̎��͂��u0.1�ȉ��v�ƁA���悻���肷�邱�Ƃ��ł����B
�@���̌�A��������������t�ŘA�ʂ����Ƃ���A�q�O�}�͂��̃V���b�^�[���ɋC�����Ă������������Ɍx�������B�d���Ȃ��̂Ŏ��͑傫���r��U���āu�ق��A�ق��[���I�v�Ɛ����������B���̃I�X�́A�悤�₭�����Ƀq�g�̎��������Ă��邱�ƂɋC�����A���炭��������Î����m�F�������ƁA���������ɂ����Ƃނ������M�܂ŕ����Ă䂭�ƁA�Ђ傢�ƒ���ŃT�T�M�ɓ��肻�̂܂܉����������B
�\�\�\���i���B
�@���̃q�O�}�͐���200�s�O��̐^�����ȃI�X���������A���͂�������قǂ̘V��ł͂Ȃ��A�ꉞ���ϓI�ȃq�O�}�̎��͂������Ă���ƁA���͊T�ˍl�����B
�@�q�O�}�̎��͂��q�g�ɔ�ׂĂ��Ȃ舫���͉̂ߋ��̌o�����牽�ƂȂ��킩���Ă������A���ꂪ�ǂꂭ�炢�����A�q�O�}�̌��镗�i���ǂ�Ȃӂ����͂Ȃ��Ȃ��z���ł��Ȃ������B����ŁA�t���[�Y���X�g�[�N��p���ăe�X�g�����Ƃ�������܂�������B
�@�O�߂̖ړI�́A�����g�̌P���Ȃ̂Ńq�O�}���ɂ��܂�W�Ȃ����A���̋������Ɗ�̋ؓ���ዅ�̔����ȓ����͔���Ȃ��̂ŁA���悻�q�O�}�̃{�f�B�[�����Q�[�W�ł��̃N�}�̎��̍s�����u���ɗ\������P�����ł���B������A������80m����Ă��Ă��A���Ȃ�_�o���W����������Ƃ裂ƂȂ�̂����ʂ��B
�@����́A�����ߋ��ɉ��x���~�X��Ƃ��Ă�₱�������ƂɂȂ����o�������邩�炾�B
�@������p�g���[���ł́A���������Â��Ȃ�O�ɃN���}�ɖ߂�悤�S�����Ă��邪�A�����o�������艽���ɔM�������肵�ċA����}���Ƃ�������B�����āA�T�T���܂�ȃg�h�}�c�тȂǂ��V���[�g�J�b�g���ĕ����ċA��r���ɁA���̗т̒��Ŏ�O�}�Əo���킷���Ƃ����x���������B���m�Ŗ��C�ōD��S�����Ȏ�O�}����̒����ɏo�Ă���̂�����A����������̑��݂��A�s�[�������Ƃ���Ť�����������Ƃ͉��X�ɂ��ċN���肤��B���Ԃ�A�����ɏo��܂��܂����邢�����Ȃ̂����A�J����̃g�h�}�c�т̒��Ƃ����̂́A�v���̂ق��Â��̂��B���̏ł́A����40m�̋����ɂ����Ƃ��Ă���q�O�}�ł��A�قƂ�ǃV���G�b�g�Ƃ��Ă��������Ȃ��B�Ȃ�ƂȂ�������������Ă��邾�낤�Ƃ͔����Ă��A�ڂ��������F�ł����\��ǂ߂Ȃ��B�܂�ʼne�G�̃N�}�̍s����ǂނ悤�ȏ�Ԃ���������̂��B�V���G�b�g�̓����Ɖ��A�����Ă��̃N�}�����m�Ŗ��C�Ȏ�O�}�ł���Ƃ����������A���̎��ޗ������A���̓s�x�A���Ƃ��떂�����ăN���}�܂Ŗ߂����B
�@�������q�O�}�́u�_������O�}�v�����m��Ȃ����A�u�_�����ꏊ�v�u�_�����V�`���G�[�V�����v����Ƃ��ɊO��Ă���̂ŁA����͂����܂Ń~�X�e�C�N���B���䂭�g�h�}�c�тŎ�O�}�̃K�`���R����ȂǁA�������܂肵�����Ȃ��B
�@���˂Ă�肱�́u�e�G�̃q�O�}�v�Ή��̌P���������������̂����A���邢�ꏊ�ŋ����Ă��܂��ƁA�ǂ����Ă����̐_�o�̓q�O�}�̕\��Ǝ�ɏW�����Ă��܂��A�Ȃ��Ȃ��֊s�����Ȃ��B����Ŏv�������̂��A��̂悤�ȃt���[�Y���X�g�[�N�̏ł́A�����S�ȌP���@�������B
�@���̌P�����n�߂Ă���A�Ȃ����u�e�G�O�}�v�ɏo���킵���������Ȃ����A���Ԃ�A�����͌P���������Ă���Ƃ͎v���B�����A��̕s���ӂłȂ��Ƃ��A����̔ӂ̃q�O�}�Ȃ�A���̗֊s�ʼn��Ƃ��u���Ƃ�v���s����\�\�\�����m��Ȃ��B
�@�Ȃ��A���̎�̃e�X�g�ɂ�100m�ł̌덷���P���O��̃����W�t�@�C���_�[(�f�W�^�������v�j��p���ċ����𑪂��Ă���B���R�A�f�W���p����A���̃q�O�}�̑̍��E���������炢�͂͂����o����B
�NjL�F��̖q���n�ŋɂ߂ėǍD�Ȕ������q�g�ɑ��Ď������q�O�}�́A���傤�ǂ��̃e�X�g�����T�Ԍ�A���̔����߂��̎R�����猩����Ζʂɂ���Ƃ�������R�ʂ肩�������V�J�쏜�̃n���^�[�ɖڌ�����A��͂�ώ@�����f���Ȃ������C�t���ŎˎE���ꂽ�B190�s�̃I�X�B�ߏ�Ȃ��B���ȁc�c
�⑫�j�q�g��|����Ȃ��N�}
�@�����̓����ł́A���ɎႢ�̂��l�����邢�͏Z��n�E�s�X�n�܂ŏo�Ă���P�[�X�������Ȃ��Ă���B�n���^�[����݂ň�ʓI�ɂ悭������_�́A������N�}�������������āA�N�}���R�Ńq�g�ɒǂ������܂킳���o�������Ȃ��Ȃ����Ƃ������B����́A�������Ǝv���B�N�}�����̂悤�ɁA����̃q�O�}��ǂ��ĎR���������҂́A�c�O�Ȃ��ƂɌ���ł͂قƂ�ǂ��Ȃ��B�����������A�N���}�Ŝp�j�����R�������N�}�ɔ��C���邾���̘b�B�O���O�ӁA�������q�g�����������_���ĒW�X�ƒǂ��Ă���Ȃ�Ă����o�������N�}�́A���Ȃ��Ƃ����̒n��ɂ͑��݂��Ȃ��B�N�}�������q�O�}���X�R�[�v�ɓ���ăg���K�[�������ĎˎE���邻�̏u�Ԃ܂łƓ�����Ƃ��A���̂����Ȃ��Ă����N�}�ւ̃X�g�[�J�[�s�ׂƂ������Ƃɂ��Ȃ�B�������A�e��͎�����,�A�q�O�}�Ƃ̋����͂͂邩�ɒZ�����B
�@�悭�������l�����āA�u�t�O�}�쏜�v�ŃN�}���l��Ȃ��Ȃ������炾�A�Ȃ�Ă����Ƃ��炵���������A�ʂɃN�}�������悤�����낤���A�q�g���\���x�����Ă���A�����ȒP�Ƀq�g�̊�������ꏊ�Ƀt���t���߂Â�����͂��Ȃ��B���́A�t�O�}�쏜�̔p�~�ŁA�q�g�ɒǂ���N�}���������Ƃ������Ƃ��B
�@������́A�����́A�N�}�����s�݂̒n��ł͓��ɁA�L�Q�쏜�ŏe������㩂Ɉˑ�����X�������|�I�ɑ��������Ƃ��B��㩂̃����b�g�͖�ԏo�v�^�̃N�}���ߊl�ł���Ƃ����_�ƁA���̍�Ƃ̓�Փx���Ⴍ�A�q�O�}�ւ̒m���������t�قł��s���ӂȃN�}�A���ɎႢ�̂Ȃ�A���w���̉ċx�݂̎��R�����ł��ł�����x�̂��̂��B������G�T�ł��т���̂ŁA������������炵���Ƃ���ɒu���A�N�}�̂ق��������Ă���B�����A���R����Ă����N�}�̂������Ɍo�����s���ӂȌ̂�ߊl���邱�Ƃ͂ł��Ă��A�_��������̌̂�ߊl���邱�Ƃ́A���Ȃ��Ƃ����w���ɂ͂قƂ�ǂł��Ȃ��Ƃ͎v���B
�@��㩂Ƃ����̂́A�قƂ�ǃq�g��l���ւ̌x���S���N�}�ɐA�����邱�Ƃ��ł����A�u㩂������ӂ�����C�v�Ɛ����c�����N�}�����͑�����悤�ɂȂ��Ă��܂��B���������N�}�ɂƂ��ẮA㩂͉��̏�Q�ɂ��Ȃ炸�A���R�Ɣ�㩂̉���ʂ�߂��āA�ړI�̃f���g�R�[���_�n�Ɍ��������肷��B
�@�Ƃ��낪�n���^�[��s���E�Z���́A�N�}���l���Ɖ����d�v�ȍ�Ƃ����Ă���悤�ȍ��o�Ɋׂ�A�Ђ�����㩂ŃA�g�����_���ȃN�}�̕ߊl�ɑ������肷��B�u���N�͂���10���Ƃ������I�v�ƗE�܂����������A���̑�������Q�ɊW�̂Ȃ��N�}�ŁA�P�ɔ�㩂̒��Ɏd���G�T�Ɉ������ĕ߂܂����Ⴂ�̂��B���̂�����̗������������܂ܕߊl�������Ȃ�ƂȂ������Ȃ邪�A���̉e�ŁA�u㩂������ӂ���q�g���l�����댯�ł͂Ȃ��v���������N�}���ǂ�ǂ��Ă���悤�ȋC������B
�@�w�n�������q�O�}�ی�Ǘ��v��x�ɂ����āA�w�t���̐l�ވ琬�ߊl�x�Ƃ������g�݂�����B�����ŕ��サ����肪�A�e��̐��\���B�q�O�}�̎��͂ɂ�銴�m�\�͂Əe��̐��\�����܂�ɈႢ�����āA�e�ő_���Ă邱�Ƃɂ��C�����Ȃ������ɎˎE�����Ⴊ�������ł���ƁA�f�[�^����͓ǂ߂�B�Ⴆ�A�ł̎ˎE������400m���O�Ƃ����Ⴊ�Ƃ��ǂ������邪�A�q�O�}��100m��ɐÎ~�����q�g���������邱�Ƃ��ł��Ȃ����x���̎��͂��������Ă��Ȃ��B�ϐ����400m�Ȃ�A�������畁�ʂɋ߂Â��A�قƂ�NjC�����ꂸ�߂Â���B������ɂ܂������C�����Ȃ��N�}�́A���炭�x�e�����胆�������ƕ�������A�Ƃɂ����I�Ƃ��Ă̓C�[�W�[�ȏ�Ԃ��Ǝv���B�����Ă�����́A�قƂ�ǔ�������\�����Ȃ����߁A����S�Ō����Ƃ��ł��邾�낤�B�܂�A�N�}�ɂ��Ă݂�A�ˑR�ǂ�������e�e�����ł��āA�����N�������������킩��Ȃ������ɁA���̏�ɓ|��Ď��ʂ��ƂɂȂ�B��q�����悤�ɁA�ÓI�ˌ���400m�Ƃ����̂́A�������Ȃ������Ȃɓ�����Ƃł͂Ȃ��B
�@�������A�Ⴊ�Z���Ė����������Ă��܂��A����Ȏˌ��͕s�\������A�l�ވ琬�ƌ����Ă��A�債�Ė��ɗ��Z�p����킯�ł͂Ȃ��B�n���^�[�ɂƂ��čł��L���Ȏ����E�����ŁA�����\���C�t���ł��̂悤�Ȏˌ��������炵���Ƃ���ŁA���H�ł͂قƂ�ǖ��ɗ����Ȃ��Ƃ������Ƃ��B
�@���̐l�ވ琬�̕��@�_�̂ЂƂɁA�V���b�g�K�����g�p����Ƃ������Ƃ�����B�Ƃ͂����A���ǂ��̃V���b�g�K���̓X���b�O��100m��̊l���Ȃ�܂��O�����Ƃ͂Ȃ��قǏo�����ǂ��̂ŁA�N�}�ɂ͏\���Ȑ��\�������Ă���B���̃V���b�g�K���ŁA50m���O�̋����Ŏd���߂�悤�ɂ���A�n���^�[�ɂ�����Ȃ�̎��͂��g�ɂ��A�Ȃ����A�q�g�ɒǂ���o�������N�}�������邾�낤�B
�@��㩂����C�t�����֗��ȓ���ł͂��邪�A����䂦�ɁA�q�O�}�̋Z�p�ōł��d�v�Ȃ��낢���މ������Ă����B���̑މ��ƂƂ��Ɋ���̖�肪�����o�Ă�����Ǝv���B�q�g���Ȃ߂��N�}�����邱�ƁB�����āA�ǂ����Ă��l��Ȃ���Ȃ�Ȃ��댯�O�}���s���|�C���g�Ŋm�������₩�Ɋl��Ȃ��Ȃ邱�ƁB�ǂ�����A�l�g��Q�̊댯���̓_�ŏd��Ȗ��Ǝv����B
�@�ې��z�ł́A�k�C���̎w�j�E�w�������ĎR�֓���u�쏜�v�Ƃ������ڂŃN�}���ˎE����l�Ԃ����܂��ɉ��l������B�����Ƃ��ɂ͒���3����A�Â���������R�ɓ����ăN���}�ŗѓ���p�j���A���������N�}�Ɏ蓖���莟�攭�C���Ă��邪�A���̂������Ŏ蕉���O�}���l�m�ꂸ�����A���܂Ɏ蕉���ɂ������Ƃ����R�o�����肷��B���̃X�^���X�Ŏ����V���b�g�K�������ĂΔN�ԂɍŒ�10���̓q�O�}���ˎE�ł��邾�낤���A�������A����͂�����������ł͂Ȃ��B�ނ�͌��������N�}�̂����x���S�̖R������O�}�������E���B���̕��@�ł́A�قƂ�ǐ�ɂȂ���Ȃ��B���́A�Њd���Ēǂ������B���ʁA�N�}�����̓n���^�[�����ꂸ�A���ƃx�A�h�b�O���ނ��닰��Ă���悤�ȋC�z��������B�l������N�}����������R�c�́A�����E�����Ƃł͂Ȃ��A�������ċ����邱�Ƃ��B
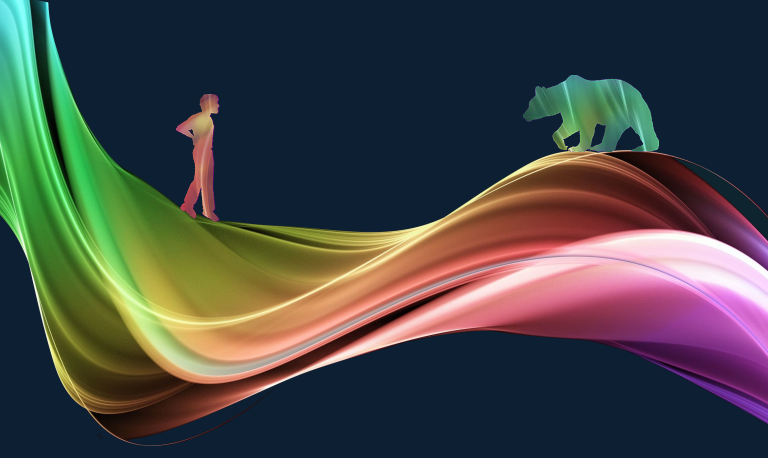
|
|
�ڂ₫�F�{���̂Ƃ��넟�����O�D�P�x�̉\��
�@����̃q�O�}�Ǘ��Z���^�[�Ń��N�`���[���I���A�G�R�E�c�[���Y���̃~�j�o���͕���������u�X���v���߂��A�Q�[�g���J���đ����ւ������������B�~�j�o���ɂ͏�q�U���ƃq�O�}���������K�C�h�Q���B�G�R�K�C�h�����Ȃ��璲�����[�g��i�ށB�K�C�h�̓��e�́A�q�O�}�̍��Ղ����Ȃ���̃q�O�}���N�`���[�ɉ����A���S�m�ۂ��ł���Ɣ��f���ꂽ�ꏊ�ł́A�u����ف[���I�ق��ف[���A�ق��I�v�ƎR�̕����������H�Ŋw�ԁB
�@�~�j�o���̑��A�����p�i�G�R�c�A�[�q2���܂ŏ�ԉ\�j�����ƃV�J����p�s�b�N�A�b�v�����p�ӂ���Ă��邪�A�����̈ʒu��GPS�f�[�^�������Ő����Z���^�[�ɑ����A����̃q�O�}�Ǘ��Z���^�[�̐E���ɂ���Ēn�}��Ŕc������Ă���B
�@�~�j�o���̂䂭��́A���݈ꓪ�̎�O�}�̊���������Ŏ���Ƃ���ɍ��Ղ��c��B���̍��Ղ���q�ɐ������Ȃ���i�ނƁA������ΖʂɎ�O�}���B�����@�Ɏ��L���Z���^�[�ɘA���B
�i�����j�Ⴑ����ꍆ�ԁB�r����E�n�̔w�̉�1200m�BR1�A�t�L�H�A���x���P�B�Ԃ̓Q�[�g�ɂđҋ@�肢�܂���@
�@���̖����Ō��F���ꂽ�q�O�}�́u�ꏊ�v�u�R�[�h�l�[���v�u�s���v�u�ٔ��x�v�Ȃǂ��Z���^�[�ɑ�����B�f�W�^���J�����ŎB��ꂽ�ʐ^�́A�̃f�[�^�Ƃ��ăZ���^�[�ɃX�g�b�N�����B
�u�����͍K�^���B�������Ƀt�L��H�ׂ�Ⴂ�q�O�}�������܂��ˁv
�u�����H�@�ǂ��H�v
�u�ق�A�������̞��̖̂ӂ��Ɓv
�u�����I�����I�v
�u���v�B�������肵�Ȃ�����A�Â��ɒ��߂Ă��������v
�������]�X
�@�ޕ������̏o���������m��Ȃ����A���ꂪ���̕`���k���̃N�}�Ɨ��K�q�̂ЂƂ̌`���B�@
�@���ݎ������g��ł���u�ǂ������v�u��O�}�̐l�Ԋ�������v�́A���낢��Ȍ�������Ĕ��Ύd���Ȃ��ߓx�ɂ���Ă����Ƃ��B����́A�ЂƂ܂����m�Ȏ�O�}���ό��q�����䂳�����肵�Ȃ��悤�ɂ���ړI���炾���A���̌��݂̒Z���I�ڕW�Ƃ͈قȂ�C���[�W�����̒��ɂ͂���B
�@�l���ߕӂɃL�c�l��^�k�L��E�T�M��V�J��q���l�Y�~�����邾�낤�B���ނł́A�傫��������I�I���V�A�I�W�����V�A�N�}�^�J�A�t�N���E�A�J���X�A�N�}�Q���A�J�P�X�]�X�Ƃ��čŌ�ɃR�K���B�����́A���ɐl����G�T��^�����Ȃ��Ă��A�l���ߗׂ̋_�n��ѓ���т����\���ʂɕ����A���̒n��̋�����������Ɏ~�܂��ĉ�X�q�g�������낵���肵�Ă���B���R�ł��l�Ɍ��������āu�o�v���������I�v�����āu�F��W�I�v�u�쏜����I�v�ƂȂ�̂́A���悻�q�O�}�������B
�@���̒��b�s���͂��߁A���̉ߕq�Ő_�o���Ȃ܂ł̑Ή��̑����Ɍ�F�E���낪���邱�Ƃ͏q�ׂĂ����B
�@����łȂ��ЂƂ̎����́u�Ƃ�����ƃq�O�}�͔��Ɋ댯�ł���v���邢�́u�l�̍s�ׂɂ���Ċ댯�ȑ��݂ɕς��v�Ƃ������������A�u�Ƃ�����Ɓv�u�l�̍s�ׂɂ���āv�Ƃ�����������������A�q�O�}���ߗׂ̎R�ɐ������邱�Ǝ��̂̊댯���͋ɂ߂ď������ł���B�����Ă���������ƁA�ǂ��܂ł����Ă��l�K�e�B�u�ȁu�Q�b�v����u���Y�v�u�����v�u��]�v�u��v�ւ�180�x���̑��݉��l��]�����邱�Ƃ����\���B
�@
�@����A���̏W���̎�҂������C���Ɏ��̂��Ƃ֗��Č������B
�u��䂳��I�l�A���̂܂������A�̕��ŁA���܂�Ă͂��߂ăN�}��������ł���I�v
�u�ق��I�߂��ł����H�v
�u50m���炢�I�@�������傫���āA��������Q���ȏ゠�肻���ȑ傫�ȃN�}�ł����I�N�}���āA��������Ȃ��I�v�@
�@�Ȃ�قǁA���̋C���͂Ȃ�ƂȂ�������B����A�������悭����B
�@�|�\�E�ւł��s�����甄����q�ɂȂ�悤�ȓڂ̌����A�N�}�̂��Ƃł���Ȃӂ��ɖ��C�ɓ������Ƃ̕������ɂ͂�����ƕs�v�c���������A��������͂Ƃ������A���S�̌����͔��ɂ�낵���B
�u����Ⴀ�悩�����I�K�^�ł߂ł������Ƃ��B�Y��Ȃ��悤�ɍ��Ӗ��������炢�����I�v
�u�Y�ꂽ���Ă��Y��܂����A����́I�v
�@���������āA��҂̖ڂ͎��ł͂Ȃ��ǂ��������̔ޕ�������ڂɂȂ����B���������Ƃł͂Ȃ��A�����g���g���ƕ����̉����h��Ă������������B�́A�����̗F�l�ɂ��̊���������Ƃ�����B�����ċ��炭���̗F�l�����́A���̊�ɓ����������Ă����̂��낤�B
�@�N�}�Ɋ�Ԏ�҂���Ԏ����������A�ЂƂ������������������u�����A�̂ق��Łv�Ƃ����������B�c�O�����_��������������Ȃ����A�Ƃɂ������X�Ɉ���������A���ꂪ�Ȃ�ƂȂ��V���N�������B
�@���́A�ނ̋A��ۂɂ������������B
�u�ł��Ȃ��B���̕ӂɂ������ȃq�O�}����R������v
�@��҂́A���������悤�ȕ�����Ȃ��悤�ȕςȊ�����Ă������A���������邾�낤�B
�@���ہA���̒����Ŕނ̎؉Ƃ���500m�ȓ��ɖ��N�������̃q�O�}�̍��Ղ���������邵�A���͂��͈̔͂ō��N���A�����ƑΖʂ��Ă���B�ł�����Ȃ�A�u�����A�̂ق��v�Ȃ���Ȃ��A�ނ̎���̗��R�̃N�}�ɍ����Ă��炢���������A�Ƃ����̂����̐����ȂƂ���ł���B���ɂ��̃q�O�}���A�����ĂP�D�T�������Ȃ������ȃN�}�������Ƃ��Ă��A�����A�̃N�}�̉��{���S�����������͂����B
�@���݂ɁA�N�}�Ɋւ��̂ɓڂ͕K�v�Ȃ��B���̂������Ȃ��B���������Ƃ܂��v��ʂƂ���Ńq�O�}�E����ɂ�܂�邪�A�A�����E�h������o�[�g�E���b�h�t�H�[�h�炵����͕�����ł��Ȃ��B���������`���[���Y�E�u�����\�����X�^���[�����g���{���^���A�R�i�L�W�W�C���͓��̎O�����T�j���B�ŋߖk���̃N�}�̗��ɂȂ����j�́A�N�}���N�}�Ɏ��Ă��镗�̂����B���̒j���O���N�}�������Ƃ����A���͏]���ɂ����M���Ă��܂��B�ނ����A�F���i�N�}��ǂ����Ď˒����ɂƂǂ߂錢�j����Ă�H�c�̗t���A�u�����͊炪�O�D�q�Y�݂������낤�B�������ɂȂ�v�ƌ����Ă����B���R�Y�O����_�����������B�N�}�������҂́A������������F���̑f���������˂Ȃ�Ȃ��̂����m��Ȃ��B
�@�u�����\�����͓��̎O���ɂ����ЂƂ��ʂ���̂́A��قǂ̂����g���g���̉����ނ�̊�ɂ��邱�Ƃ��B�����Ď��ɁA���̂���炪���������ƍ����ŔR��������B
�@���āB
�@��҂ɍ��������Ƃ͂��ׂĎ��̖{�S���������A���̂��Ƃ�Ŏ��̐S�͗J�T�ɂȂ����B
�@�[�����ߑ������Ďv�����B��̃A�����B
�������Ⴄ��Ȃ�
�@�����̒��ƈꕔ�n���^�[�͂������ς�����E�����Ƃ��A���͎��ł������ς�����ǂ���������������s���B�������A�n���^�[�̓V�J�쏜�̎��ɋ��R��������O�}��q�O�}�������E������������A���N�E����N�}�̐��ȂǁA�˔��I�ȉ������Ȃ����㩂���g���Ă���������10���~�܂肾�낤�B���̐��͂ǂꂾ���I���ɂ���Ă��ς��Ȃ��B�����āA���݂̂悤�ɐl�ו���H�ׂ܂����Č��C�����ς��̃��X�F���炯�Ȃ�A���̃��X�����͋ɂ߂ď����Ɏe�F�Y�������邾�낤����A���炭�A���ʐl�����ӂŃq�O�}�̐��������邱�Ƃ͂����Ă����邱�Ƃ͂Ȃ��B�������A���͂���10���ł����Ă����Ŗ����ʂȕߎE�͑j�~�ɂ�����B
�@�����̖��͔ނ炪�E���N�}�̎�ނ��B�ނ炪���ՂɌ����E���Ă���q�O�}�́A��́u���m�Ŗ��C�ōD��S�����Ȏ�O�}�v�̂����A���ɓۋC�Ōx���S�̂Ȃ��̂��B���̃o�J�ŊԔ����ʼn��̊Q���Ȃ���O�}���������̎R�̎ΖʂœۋC�Ƀt�L��V���N��H�ב�����Ƃ��A���邢�͋߂Â����V�J�쏜�̃n���^�[�������m���߂悤�Ɨ����オ���ċ����ÁX�Ō��Ă���Ƃ��A�e�͂Ȃ������̒e�ۂ��������܂��B�܂�A�x���S�������A���ςŐl�ڂɕt�����Ƃ��Ȃ��_�n�֍~��A㩂��������悤�ȃq�O�}���������̐l�����ӂɐ����c���Ă䂭���ƂɂȂ�B
�@���͎��ŁA���̐��N�ѓ���R��_�n���ӂŁA���C�ȃo�J�F�Ƀq�g�ւ̌x���S�Ɖ�������헪��A���t���Ă����B��O�}�ɂ���Ă͓O��̏�ɓO��I�ɁA���ǂ��̋��t�Ȃ�\�͋��t�Ǝw���������@�ł�����������B�Ƃ��ǂ��̔��̃_���[�W���S�z�ɂȂ��Ė���Ȃ��Ȃ����B
�@���ΖʂŁA�S�����Ɖ��ɂȂ��Ă����ł�������Ȃ���j���j�����߂Ă���ꂽ�قǂ̎�O�}���A���ʁA�������łȂ����̒N�����ڋ߂��Ă���������悤�ɂȂ��Ă��܂����B�o�J�F�������͗����ɖڊo�߂��B���ꂪ�ړI�������̂�����A��������͑听�����B�������B
�������Ⴄ��Ȃ�
�@���ꂪ�{���ł���B
�@���̒n���K���ό��q�́A��{�I�ɓs��⒬�ɂȂ����R�����߂Ă���Ă���B�R�ɕ��i��������A�����k���̗��ꂾ������A�������ŋC���܂܂Ȃ���C��������A���̂������肾������A�Ђ����萶����L�m�R��������A�����ڂɓ������G�]���X��������A�l�Y�~�Ƒ債�ĕς��Ȃ��i�L�E�T�M��������A�Ђ�Ђ��Ԓ���������������A�ǂ����̓��̉����̂悤�ɔ�ԃI�I���V��������A�Ԃ�Ȋ�ňӊO�Ɛ}�����_�o�̃G�]�V�J��������A�Ќ������肻���łȂ������ȃq�O�}�������脟�����܂��A���낢�낾�B
�@������Ⴆ�A�G�]�V�J�̌Q�ꂪ�����猩���邾���ŎԂ����䂩�~�܂��Č����l���o��B�L�c�l���L�����v���z�e���߂���������A���ɒa�����v���[���g����n���悤�Ȃ��肳�܂ʼn��l���̂��q�����َq��^����B�����āA���̌��i��A��̒N�����J�����ŎB���Ă����x�ɂȂ����肷��B�吨�ŋ�����グ�Ċ��Q���Ă���Ǝv���A�G�]�V�J�̎��[�̏�Ɍʂ�`���I�W�����V���B�}�E���R���ɂ͗��h�Ȗ쒹�p�G�T�䂪����A�����ŃG�T�����ޏ��������͕�˂̃q���C���悤�Ȋ��тƈ�������B
�@�L�c�l�ɃG�T�����̂͂��������l���Ȃ��Ⴂ���A�܂��A�����ł͑f�ʂ肷��B�Ƃɂ������ɂ��A������K���ό��q�́A�n�����炷��Ƃ�ɑ���Ȃ����ʂȐ������̂≹�⍁�肪�����Ɋ������A��������߂Ă�܂Ȃ��̂��B�Ƃ�ɑ���Ȃ����炢���ʂɂ����������̂����邩��A�ό��q�͂킴�킴���̂悤�ȕ�翂ȎR�ԕ��ւ���ė���̂ł���B
�@������B�q�O�}�Ȃǂ��ق�̃`�����Ƃł����悤���̂Ȃ�A�قƂ�Ǒ��|����̂ł͂Ȃ����Ƃ����炪�S�z�ɂȂ邭�炢�g�̂�k�킹�������A��їE�ށB�����炪����`�����X���^�����u�k�C���܂ŗ����b�オ�������I�v�u�����Ă��邤���Ƀq�O�}��������Ƃ͎v��Ȃ������I�v�u����ł�����������ł������v�ȂǂƐl���̑��M�̂悤�Ɋ�������B
�@����A�҂Ă�B�悭�悭�l���Ă݂���A���̒n���ł����N�}���������Ƃ̂Ȃ��l���炯���B������������{���ɑ��M�Ȃ̂����m��Ȃ��B
�@�����l�����ƁA�܂��܂����̗��ߑ��͐[���Ȃ�B
�@�����g���͂��߂ăq�O�}�ɑΖʂ����Ƃ��̂��Ƃ��v�������Ă݂�B
�@���̃q�O�}���̌��͑�w�ɓ����Ă��炭�������A�k�C���ł̂��ƁA�u�b�V���̖鎊�ߋ����������������A���낵���Ƃ��������Ƃ��A�ł�Ƃ��撣��Ƃ��A����Ȓ��Ȃ��̂ł͂Ȃ������B�N��ƐÎ���y��ƁA���̂̒m��Ȃ�����ւ̔��B�����̈�؍��������Ɏ���ۂݍ��݁A�����ł������������N�������A���ɒ��ʂ������A���̍�����������u�Ԏ��́u��������́H�I�v�ƙ�l�Ɏv�������ŁA�g�̂̋@�\�𗎂Ƃ��Ĕ]�������t����]�����������̏𐳊m�ɗ�������̂ɓ�b�قǂ͎��Ԃ�v�����B�����āA���͐_�ƈ����A���ƋS���������|�I�ȉ����ɑł��̂߂��ꂽ�C���ɂȂ����B������A�K�^�Ƃ��s�^�Ƃ��v��Ȃ������B
�@�������k�C���̃q�O�}�̑��݂́A�f���⊈����l�̘b�Œm���Ă����B�������A���̓������ӂƌ������������ɑ��݂��錻�����A��˂̎��͉�ɐM���邱�Ƃ��ł��Ȃ������B���n�Ȃ�o���ƒt�قȂ�m���ł��̏�����̊Ԃɂ������R���߂����A�Y���Y���n�ʂ�ŗѓ��܂ŏo�āA����Ƃ����n����ɋA�҂����悤�ȋC���ɂȂ����B
�@���̏ꍇ�́A�A�j���`�b�N�ʼn����ȋ������сE���|�Ƃ͂Ȃ�Ȃ��������A����̂���ɉ��̕��ւ��킶��Ɛ��ݍ���Œ���������݈ӎ��Ƃ��ăq�O�}�͎��ɐ��݂����B���̏o�����ŁA���̎R��͂ւ̈ӎ����ς�����B�q�g�ւ̈ӎ��������ς�����B�����Đl�������̎����Ԃ�O�D1�x�قǕ�����ς����B�O�D�P�x�͂��̏�ł͔����Ŗڑ��덷�����m��Ȃ����A���̔������Q�O�N�o�����Ƃ������قȂ�ꏊ�֎����Ă���B
�@���́A�Ⴉ�肵���A�n���ۏo���Ŗ������̂悤�ɗ��������Ă��ꂽ�����̏����k�Ɠ����قǁA�N��ƐÎ���y��Ɣ��������Ď��̑O�Ɍ��ꂽ�q�O�}��l���̍��ɉ��Ɏ����Ă���B���̕�́A�W���W���ƉA�T�ɈÂ����������̂ł͂Ȃ��A�ނ��됰��n���Ė����钩�̋�̂悤�Ȃ������������������Ă���B
�@�u�l�ɂ͓��ނ���B���������l�Ƃ��Ȃ������l�v����ȃt���[�Y���ǂ����ŕ��������Ƃ����邪�A����ɕ���Č����u�l�ɂ͓��ނ���B�q�O�}�ɋ������l�Ƌ���Ȃ��l�v�Ƃ��Ȃ�B
�@�܂�A�ǂ�����l�̐l�����O�D�P�x�قǕς����邪�A���̔����ȂO�D�P�x�ŁA���̐l�̐l���͖L���ł��ł₩�Ńf�B�e�[���ƃR���g���X�g��@�ׂɎ��������̂ƂȂ�B�܂�A�������Ĕ߂����āA�������ėD�����A�������낢�l���ƂȂ�B
�@�u�N��A��u������I�v�Ɠf�����̂��搶�̑����w���ɂ��������A�u�N��A��u������O�ɑ�������Ȃ����I�v�ƌ����������炢�ł���B
�@�u�|�p�͔������I�v�ƖT�ᖳ�l�Ɍ����������l������ȁB�����A���͂��̃t���[�Y�Ƒ��Y����̃L�����N�^�[�����������Ɏv���Ă������A��l�ɂȂ��Ă���Ƃ��ǂ����̃t���[�Y���]�����ӂƐ^��ʼn���B���̐^�炪���\�炢�B�����Ď������}�̂悤�ɁA�O�Y�O�Y�u�X�u�X�Ƃ����Ԃ��ĔR�Ă�����Ȃ����Ɍ����đ��Y����͉���B������u���q�O�}�������A������������l�����̂��̂����̔��������m��Ȃ��B
�@�����Ƒ�̂ɂ́u���̂̂����v�Ȃǂƍ��������Ƃ₩�Ɍ������l������B
�@���̂ǂ�����A�̂���Ƃ���炢���������Ȃ��l�̐l���̑�n�ɁA�[���J�����肻���ɂ͓{���̔@�����w�Ȑ�������A�Ǎ��Ȃ�R�x���Ȃ���A�J���~�����蕗����������A�ق̂ڂ̂ƒg���������蓀�ĕt������A�����₯�����̂悤�ɗ�������A����łƂ��ǂ��̎肪�オ���Ă������ʂ��^�����ɏĂ��s��������A�V�J����������N�}���Q�����A�����m��ʒ����P���P���A�s�[���s�[���Ƃ��������Ă݂��脟�������������쐶�̐X�̂悤�ȑ�n�ɕϖe������u�O�D�P�x�̉\���v�Ȃ̂��B���̐X�̐l���́A�L���ɂČ��i�A��тɖ������ӂ�߈��A�����ɂĐ؎��B�܂�A�Ђ�����߂Č����u�������낢�v�̂ł���B
�@�u�O�D�P�x�̉\���v�́A����ɐG�ꂽ�l�ɂƂ��Ắu�����̉\���v�ł�����B
�@������A�q�O�}�ɑ����āu��������ł������v�ȂǂƂ͌֒��ł������Ă̓_�����B�s�e�Ȍ`�Ō����A�����邽�߂ɑ����̂��B�����邽�߂Ɋ�����̂��B
�@�q�O�}�ƍ����`�����X�����Ƃ��Ǝ����������̐l�����B�n���^�[�͔ނ�̊�т��]��u�O�D�P�x�̉\���v���ɒD���Ă���B���͎��Ŕނ炩�炻����������Ă���B
�������ǂ��������A�Ⴄ��Ȃ�
�@�F��̎E�C�͂Ƃ������A���̊�������ɑ��ẮA���́u�O�D�P�x�̉\���v����ۉ�������Z������B�N�ł�����y�Ƀq�O�}����������͍��Ȃ����A���炭�A���E�ōł����R�Ȍ`�̃q�O�}�����̏�A�ώ@�̏�A���������ł���B���̉\�����k�C���̖k���ɂ͂���B
�@�����悭�����u�q�O�}�����n�I���ӁI������ҁI�v�̊Ŕ́A�K��������k�ł͂Ȃ��B�G�ł��Ȃ��B�q�g�ƃq�O�}�̃R���g���[�������x�����B���ł���A�\���M�ߐ������Ŕ��B
�@�u�������ς�����E���v���u�������ς��������������{���v���Ȃ����āA�����ƈ��S�����Œ���ɃR���g���[�����Ȃ���u�����Ƃ��Ă����v�u�����炩�ɒ��߂Ă��v�ɃV�t�g���鎞��͂����A���邾�낤��������

|
|
�������h�H�\�\�\�q�g�ƃN�}�̃M�u�E�A���h�E�e�C�N
�@���́A�ꓪ�ꓪ�̎�O�}�ɑ��Ċ�����������݂Ă����B�������A���ꂪ�ł������I��@���Ǝv���Ȃ��Ȃ��Ă���B�����ƃV�X�e�}�`�b�N�ɁA�q�O�}�ꓪ�ꓪ�ł͂Ȃ��q�O�}�̎Љ�S�̂��R���g���[�������@�������I���ƍl����悤�ɂȂ����B�͊w�͊w�Ɨ͊w���̂悤�Ȃ��Ƃ������̂́A�����������R������B�u�ǂ������̃X�y�V�����X�g�v(�I�X���b)�Ƃ����������̋���ң(��O�})���q�O�}�̒��ɂ���킯������A������I�݂ɗ��p���āA�ł��邾���q�g���J�͂��������Ƀq�O�}�̂��Ƃ̓q�O�}���m�ł�����x����Ă��炤�B���ꂪ�I���@�\����悤�Ƀq�g�̓A�V�X�g����B�����������z�ɕω����Ă����B�n���^�[���{�����e�B�A���q�O�}�ی�Ǘ����������҂��k�C���̗\�Z���A�ǂ���X��قǏ���ɂ���Εʂɂ���Ȃ�₱�������Ƃ��l���Ȃ��Ă��ςނ̂����m��Ȃ����B����A�]���̕��@���ʗp���Ȃ����Ƃ����͊m�����B
�@���́A���X�F�E��O�}���l���ߗׂɑ����������̗͊w�Ƃ��āA���X�F�̈Ӑ}�����邩���m��Ȃ��B���̐��́A2006�N���A���X�J��KatmaiNationalPark�̏����Ƃ��Ċ���郉���t����[�A������̓`�������A�M�ߐ�������Ǝ��͎v���B�܂�A��q�����悤�ɃI�X���b�̐��_�I���n�Ƃ����̂͢�x���S��Ɓu�Ǘ����v�Ȃ킯�����A���̂��ߑ����ăI�X���b�̓q�g��l��������ĕ�炷�B���ʁA�l�����痣�ꂽ�G���A����v������Ƃ���X���������A���̂��Ƃ�m���Ă��郁�X�F�̓q�g�̊�����ɐڋ߂��ĕ�炷���Ƃɂ��A�I�X���b����g������Ă���A�Ƃ������̂��B���X�F�̓I�X���b���������邽�߂Ɂu�q�g�𗘗p���Ă���v�ƕ\�����邱�Ƃ��ł���B
�@�������ꂪ�������Ƃ���A�u�q�g���q�O�}�𗘗p���ăq�O�}���R���g���[������v�Ƃ�����@���A�ނ��뎩�R�Ȕ��z���Ǝv���Ă���B�l����Ɩ����ȋC�����ɂȂ�B���X�̓q�g�𗘗p���䂪�g�Ǝe�F�����A�q�g�̓��X�F�𗘗p����������e�F�����炵�Ă��炢����̂Ȃ���O�}�𑗂�o���\�\�\��͂�A�������B
|

|
�����j�R�̖L��̗��N�A���b�I�X�̕ߊl����������H
�@�����x���̃V�X�e���ɂ���āA�H�����L�x�ɂ����ď\���h�{��~������N�̓~�A���X�F�͏����ɒ����E�D�P�E�o�Y�������Ȃ����Ƃ��ł���̂ŁA�Y�q���������邱�Ƃ͗e�Ղɑz���ł���B�����ȖL��̗��N�A���̃x�r�[���b�V�����N����A���̔N�A�e�q�A��̃��X�������A����ɗ��N�ɂ����đ����̎�O�}���e���ꂷ�邱�Ƃ��l������B���ꂪ�L��ɂ�����A���̌�̃��X�F�Ɋւ��o�܂��B
�@�Ƃ��낪�A�I�X���b�ɂ��L��̉e�������N�Ɍ����\��������B
�@�A���X�J�Ȃǂ̉��C�ł̓T�[�����𒆐S�Ƃ������Ɍ����I�ȐH�������s���ɂ��邽�߁A�H�����߂̃}�[�W�����\������B����ŁA�~����������̃q�O�}�ł����p�̔牺���b�������Ă����肷�邪�A���̎�̃N�}�͓~���������ォ�烊�n�r���̐ېH�����ނ����ɂ���K�v�͂Ȃ��B�Ђƌ����̊ԁA����������ŕ�炷�q�O�}������Ƃ����B�k�C���ɂ�����H�����߂̎����͊T�˂W���ȍ~���낤�B����܂ł̎����i���ɂS���`�U���j�́A�~���J���̃��n�r���v�f�������B�Ƃ��낪�A�O�N�������ȖL��ŐH�����߂̃}�[�W�����Ƃ����q�O�}�́A��N�ɔ�אېH�ɐ�O����K�v���Ȃ��B
�@�����ŗ���ł���̂���������B�k�C���̏ꍇ�A�K������������܂łɏ\���ȃ��n�r�����ł��邩�ǂ������^�킵�����A�ʏ�́A�~���J���̃��n�r���𑁂��I�����I�X���b���ɐB�ɂ͗L���ɂȂ�B�ꌾ�Ō����ΐH�~�Ɛ��~�̃o�����X�Ƃ������ƂɂȂ邪�A�ېH�ɗ]�T������A�\���h�{���������Ă���I�X�F�́A��N������ӗ~�������Ɏ����A�H�ׂ��胁�X��T������Č����B�����悤�Ƃ���B������̃I�X�ɍs�����������Ȍ̂͂悭���邱�Ƃ��B
�@�ϐ���̎R�Ȃ炢���m�炸�A�����̐l������Ńq�O�}���e�E�ł���p�^�[���͌����A�T�ˎO�B��́A�x���S�̔�����O�}�B����Ɏ����ŁA���͎�O�}�ɔ�ׂ�Ώ��Ȃ����낤���A������Ŗ{���̌x���S���\�������ł����ɂ������ȍs���ƂȂ�I�X���b�A�����āA�Ō�ɂ��Ȏe�F��A��s�������䂳��Ă����O�}���B����ɉ����āA����������ɉa�t������s���̃G�X�J���[�g���N�����x���S���������ُ�O�}������B��O�}�ȊO�͌x���S�̌��@�܂��͊����A��O�}�͎Ⴂ�قNJ����A���̓�����ꂼ��ɊɂȂ錴���������Ă���B
�@�����ł̖��̓I�X���b�����A�L��̗��N�A��N�����ȐH�~�����~�ɂ���ւ��A�e�n�Œʏ�ł͍l�����Ȃ����x���ȍs���p�^�[���ƂȂ邱�Ƃ��l������B���ʁA�l���̍l�����Ȃ��ꏊ�ɏo�v������A�ѓ��e�Ŗ��h���ɖڌ����ꂽ��A���邢�͂����̂��Ƃ���ߊl�ΏۂƂȂ�A�ʏ�ł͂��蓾�Ȃ��e�Ղ��ŕߊl�����\��������B
�@�܂��A���̌�������A��Q�̉��Q���������яオ��B�܂�A�q�O�}�̌o�ϔ�Q�i���̂قƂ�ǂ͐H���̔�Q�ʼn��X�ɂ��ĉa�t���ɂ�����j�������ɔ������Ă���G���A�ł́A�R�̎��̖L���ɂ�����炸�q�O�}�̐H�����߂��\���ɂł��邱�ƂɂȂ�A���X�̎Y�q���E�ɐB���������A�܂��A������̃I�X�̍s���p�^�����ʏ�ƈقȂ���̂ƂȂ�B
|
|
�e���ƃq�O�}
�@����܂ł̋L�q�ŏe��̔��B�E���y�ƃq�O�}�̓����ω��Ƃ������Ƃɂ��ĐG�ꂽ�B����͂���Ŏ����Ť���ɗ������₷�����Ƃł����邪�A��������ŕʂ̌��ۂ��N���Ă���B
�@�Q�O�O�V�N�S���B���y���Ńq�O�}�̃t�H�[����������[���܂Ŏ��͂�����s�݂ɂ����B������A�����������Ďw�����Ă���㯏m�̎��́A���̓��A�d���Ȃ��P�ƂŃV�J�쏜�Ɏ���A�[���̔��鎞�ԑтɃg�h�}�c�̗тňꓪ�̑傫�ȃ��X���d���߂��B�ˌ������͂P�O�O���O��B�V�J�͑��|�������߂��̋�����ѓ��܂ʼn^�Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ����A���̎����Ȃ�Ⴊ�\���c���Ă���̂ŁA�ʏ�A�\���ɏ悹���̏�����������ăN���}�܂ʼn^�����A���̂܂܃\�����ƃN���}�ɏ悹��B
�@�Ƃ��낪�A���̌���́A�V�J�̓|�ꂽ�ꏊ�܂ł̒n�`���N���ɕx�݁A���܂��ɐ��N�O�̕��|���d�Ȃ�悤�ɗ��G�ɓ|��Ă����B�d���߂��V�J���̂��傫�����Ƃ�����A�����̕��@���ȒP�Ɏg���Ȃ����Ƃɔޏ��͋C�������B
�@��ޏ���Ƃ�������ɂ͏������B�e�̖Ƌ������A���߂Ă̗����I��������̐V�l�������B�Ƃ͂����A�r�͂����B�u���[�j���O�̃{���g�A�N�V�����E�V���b�g�K���ŁA�P�T�O����̓����Ȃ��V�J�Ȃ�A�܂��d���ߑ��Ȃ����Ƃ͂Ȃ����x���܂Œb���Ă������B����́A�قƂ��12�Q�[�W�E�V���b�g�K���̐��x�̌��E���Ǝv���B
�@�ޏ��͎d���Ȃ����ꍏ�ƈÂ��𑝂��g�h�}�c�т̒��ŃV�J�̉�̂��n�߂����A��������肾�����r���͂������ƃi�C�t���Ҋ߂ɓ��ꂽ�Ƃ��A�ٕςɋC�������B
�u�p�L�b�c�c�v
�@���̊��������́A���قlj����Ȃ��g�h�}�c�т̒����狿�������A����~�߂ĐU��������ޏ��͓��h�����B����40�`50m�B�����ɂ́A��̏�ɃV���G�b�g�ƂȂ����ꓪ�Ƀq�O�}�������Ă����̂��B
�@���́A�V�J�����ɍۂ��Ă��m���ɂ͏�ɃJ�E���^�[�A�\�[���g�����������āA�܂�A�˔��I�ȃq�O�}�Ƃ̑����ł͕s�p�ӂɔ��C���邱�Ƃ��֑��Ƃ��A�Ƃɂ�������̃q�O�}���ώ@�E���f���A�������ȃN�}�łȂ�����e�Ȃ��őΛ����u���Ƃ�v���s���悤�w�����Ă����B�����g�̃q�O�}�Ƃ̋ߋ��������̌o������͂������A���牽���Ƃ������e���̎���͂��̕��@���x�����邾�낤�B
�@�ޏ��͓��]���������ӎ��Őh�����ăq�O�}�̗l�q���ώ@���A��̔��f�������B�C��ɗ�Â���ۂ������A�������ޏk���Ăǂ����Ă����𗧂Ă��Ȃ������B�����Ńi�C�t����Ɏ������܂܁A���肩������̏�Ń\�����o�^�o�^�Ƃ����ĉ��𗧂ĂĂ����U���ɃK���K���ƈ����A�q�O�}���������`�Ő��ł��̂܂ܕ��ʂɃN���}�܂ŕ����Ė߂����B���̃q�O�}�����ɓ��s���A���N���x�����ߋ����̃q�O�}���ώ@���Ă����o��������t�����悤���B
�@
�@�������ȃt�H�[��������A��ƁA�ޏ��������ɂȂ��[���ȕ\��ő҂��Ă����B
�u�V�J�͊l�ꂽ�̂��H�v
�u�l�ꂽ���ǁc�c������ƁA�����ւ�Ȃ��ƂɂȂ��Ă��܂��v
�@�Ȃ�ƂȂ��C���ȗ\�����������A���͖ق��Ĉ�ʂ莖����A�ꌾ�����������B
�u�g���K�[���������f�͂����ƐT�d�Ɂv
�@�������A��������Ȉꌾ�����킸�Ƃ��A�ޏ����g�������̉ߎ����\�����Ȃ��Ă����Ǝv���B������A���ł̂悤�Ɉꌾ�A�t���������B�u�N�}�̂ق��́A�܂��܂����i�v�@�ǂ������͗_�߉���炵���B
�@���́A���̃G���A�̒n�`��q�O�}�̊����Ȃǂ������̉\�����l�������A�������Ԃɂ͂ǂ��ɂ��ł��Ȃ��̂ŁAWEB�œ������̋C���z�u�����m�F���A�V���O�������g�����Ɋ܂�ł������Ɖ������Ƃ��ė������̍�Ƃɔ������B����͂��̎����̃V�J�쏜�̃��b�J�ŁA�ނ�l�Ȃǂ��߂�������B����ԈႦ��Əm���̎c�����V�J�ɕt�����q�O�}�����̋쏜�n���^�[�ȂǂƎ��̂��N�����\�����������B������A��̓r���̎��[�̏�Ԃ��m�F���A�\�Ȍ��肵�����������Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B���ɉ���s�\�ȏł��A�܂��ʂ̈��S�m�ۂ��l���˂Ȃ�Ȃ��B
�@�����A�n���^�[���������O�Ɍ���ɒ������������́A�O���m���̒�߂������ʒu�ɃN���}��u���A���������ăg�h�}�c�т�`�������A��͂�V�J���[�܂ł͉����N���╗�|�ŃV�J�̎��[���ǂ��ɉ�������Ă��邩���m�F�ł��Ȃ������B���ɁA�O��̕���q�O�}�̐ڋߌo�H����肵�A�������ɑ��Ղ��m�F���Ă݂��B���̎����̐�ʂ͒���̋C�����ŕω��ɕx�݁A�c���ꂽ���Ղ��玞���܂ł����悻���肷�邱�Ƃ��ł���B���́A������������^�S�ËS�̃N�}�ł͂Ȃ����Ƌ^���������ɂ��������A�m���̌����Ƃ��肭������ƃq�O�}�̑��Ղ��c���Ă���A���̋^���͂��̎��_�Ŋ��S�ɐ��ꂽ�B�O����15�`16�p�̃I�X�̎�O�}�B�N���5�ΑO��Ɛ���B
�@�V���ȏ��������Ď��͂���ɐ����������\�����i�������A���āA��������̍�Ƃ͑�ς��B���E�̈����g�h�}�c�т̒��Ť�����������炻���ɕt�����q�O�}�𒍈ӂ��Ȃ���V�J�̎��[�̏��m�F���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�A�C�k�̋����ɂ��u�q�O�}�������ł����������V�J���[�ɂ͐�Ɏ���o���Ă͂����Ȃ��v�Ƃ����̂��m������B����̓q�O�}���������ĂĂ��邪�A���̃P�[�X�ł͂��֑̋���j�炴��Ȃ��Ǝv��ꂽ�B
�@���́A�ޏ�����Ɏ��̌��50m�ɑҋ@�����A�������ꂽ��O�}����Z�b�g�����Ɋ����A���Ӑ[�����Ԃ������ăg�h�}�c�̗т݂��߉�̌���̕��։�荞��ŕ������B�������͎̂�������A�ޏ��̎ˌ��̐��x�͎�����Ԃ悭�m���Ă����B50m�Ȃ�3�p���Ⴆ�邱�Ƃ͂Ȃ��B���̐��x���o���鐸�_�I�Z�p�Ɋւ��Ă͎�s�����c�������A���낢��ȏ�����V���ɏ悹�Ď��Ȃ�ɔ��f�����B���̃P�[�X�ł�������悤�Ȃ�A�N�}�����Ȃǂ�߂����������B
�@�V�J���[�ɋ߂Â��Ă킩�������Ƃ́A���ʂ��������A�J���X��C���܂Ȃ��O���c�����܂܂̏�Ԃł��������ƁB���͎��ӂ������ƃ`�F�b�N���A�u�ف[���I�ق��I�I�v�ƎR�ɂ����܂����Ă���ޏ����ĂсA���r���[�Ƀo���o���ɂ��ꂽ�V�J�𑬂₩�Ƀ\���ɏ悹�ėѓ��܂ň����������B
�@���ꂾ���ޗ��������A�O���[���̏o�����̉\��������ɍi���B���̏o�����ɂ͊���̋��R�Ɗ���̕K�R������ł���B�܂�B���̃G���A�́A���̎����̃V�J�쏜���b�J�ł���B�V�J�̌��͂��������ɗ���A������ꂸ�ߗׂɓ]�������܂܂̃V�J���[�����݂������낤�B���R�Ȃ���A���ӂ̃q�O�}�A���Ɍx���S�̔����Ⴂ�̂͂��̃G���A�Ɋ���Ċ�������悤�ɂȂ�B���ɤ���̎����̒��O�A�Œ�O���̃q�O�}�����̋����G���A�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��A���̒�������������Ă����B
�@���͏e�����B���ʂɍl����A�e���ɂ���ăq�O�}�͂��̕������牓��������֓�����ƍl���邾�낤�B�������A���̃G���A�ł́A�q�O�}�͏e���ɔ������ē����A�ނ���e���̕����Ɉړ�����B���̈ꓪ���A�m���̑���������O�}�Ƃ������ƂɂȂ�B���������āA���̎�O�}�̓V�J�̓�����ǂ��Ă����ɗ����̂ł͂Ȃ��B�e���̕����Ƀt�@�W�[�ɕ����Ă��������������̂��B
�@����ɐ�������ƁA��O�}�Ƃ��ẮA�܂����[���̈Â��g�h�}�c�т̒��Ƀq�g������ȂǁA���Ĉ�x���o���������Ƃ��Ȃ��A�v������炸�����Ă������낤�B���炭�A���Ȃ薳�x���ȏ�ԂŁA�Ƃɂ����e�������ɕ����Ă����B��̌���Ǝ�O�}���ł��ڋ߂��������́A�ޏ��̐����ʂ�40m�قǂ��������A�����܂ŗ��Ă���O�}�̓q�g�̑��݂ɋC�Â��Ȃ������B����قǖفX�Ɣޏ����V�J�̉�̂����Ă����؋����B���̎�O�}���q�g�̑��݂ɋC�������̂́A�ޏ����Ӑ}�I�ɏo�����\���̉��ɂ���Ă������B��O�}�͔ޏ��ȏ�ɂт�����V�������낤�B�����āA���̕s�C���ȃq�g�������ʼn������Ă��������m�F�����A��ڎU�ɓ�������A���̕s���ȏꏊ�ɂ͖߂�Ȃ������B�������́A�K�R�I�Ɏ�O�}����ޏ������ցB��O�}�͊T�ˌ��������œ������ɈႢ�Ȃ��B���̕������͑O��ɒ��ׂ��C���z�u�Ƃ��T�ˍ��v����B�����āA���̎�O�}�́A����e���ɋ߂Â��Ƃ��Ă��A����܂ł̂悤�ɖ��x���ɂ͋߂Â��Ȃ����낤�B
�\�\�\���̂ł��鐄���͂���ȂƂ��낾�������A���̗[���̎��Ⴉ��͊���̔��ȓ_�ƒ��ӓ_�������т�����B�ޏ��̓N�}�����u�]�����A�������Č���ł��낢���蔲���A���ȂƎ��s���J��Ԃ��Ȃ��珙�X�ɂ����N�}�����ɂȂ��Ă䂭�������͂Ȃ��B
�@���āA���̎���͔��Ɏ����ɕx��ł���Ǝv�����A���ł��d�v�Ȃ̂́A�q�O�}���w�K�ɂ���ď펯�Ƃ͐����ɂ܂ŕω�������Ƃ������ƂƁA���ɏt��ɂ̓V�J�̎ˎE�쏜������̃G���A�Ƀq�O�}��������Ƃ��������B�s���́A�V�J�ƃn���^�[���W�܂�ꏊ�������͔c�����A�����ȃG���A�ł͒��ӊ��N���s�����ق��������悤�Ɋ�����B�܂��t�ɁA�A�x�ȍ~�A�����n�܂�܂ŃV�J�쏜�́A���̃G���A������������ׂ����낤�B
�@�Q�N�O�̂V�����������A�Ƒ��ł��̎R��K��Ă����Ⴂ�v�w�ƂЂ��Ȃ��Ƃ���m�荇���āA������萻�̂��ٓ����͌��ł����������B���������ꍇ�A���͌��\���h���ɉ����Ȃ����ɂ�������ɉ^�肷��̂ŁA�������������Ȃ��b���₷���B���̎��A�����̔��q�ɃV�J�쏜�̘b�ɂȂ����̂����A�ǂ����Ă��n���^�[�̂��Ȃ��Ƃ���Ŏq����V�������Ƃ����B�����Ă݂�Γ��R�̂��Ƃ��B�u�ǂ��֍s�������ł����H�v�Ɩ��ꂽ�̂ŁA���́A������ƍl�������ƁA�u���̒����o�邵���Ȃ��ł��ˁv�Ə�����k�߂��ē������B�X�����炢�͏�k�ł͂Ȃ��̂����A�Ƃɂ������́A�V�J�����Ȃ��n���^�[�����C���ɂ����ꏊ�ƂƂ��ɁA��˂ɋ���Ȃ����߂̃N���}�̒��ߕ���s���̎d����`�����đ���o�����B
�@���݂̂悤�ɎR�S����쏜�G���A�Ƃ���̂ł͂Ȃ��A���Ɋې��z�̂悤�ɃA�E�g�h�A���W���[��n��i����n��ł́A���߂Ċό��q�E�ނ�l�E�R�؍̂肪�R�ɑ������鎞���ɂ́A���̓������������Ď����ɉ������]�[�j���O���{���ׂ��ł͂Ȃ����낤���B�쏜�ɍۂ���e�e�ƃV�J���[���A���̑��Ɋ�������l�����ƁA������x������ׂ��̂悤�Ɋ�����B��N�A�V�J�쏜�̂��߂ɒP�Ƃŏe���ς�ŃN���}�Ŝp�j���Ă���n���^�[���A���R�R�̎ΖʂɃq�O�}���������C���A�����Ɋό��q���ʂ肩�����Ċ댯�ȏ�ԂɊׂ������Ƃ�����B�]���ʂ�̃G���A�ɉ����A�u�����͏e��̔��C�͂���܂����v�Ƃ������S�G���A��ݒ肵�A������ό��q�ނɒm�点��ׂ��Ǝv���B�O�q�̕v�w�̂悤�ȏꍇ�͂����֍s���Ƃ����悤�ɁB����Ƃ��ẮA�R���ƂȂ��l���ƂȂ��A���b�ی��������S��ɋ쏜�n���^�[���p�j���V�J�쏜���s���Ă��鎖�����A�����̗��K�҂͒m��Ȃ��B
|
|
�N�}�ƃV�J�Ǝ�
�@���̏����͔������ЂƂ������琅��������Ă��邪�A���̔����ɂ̓g�h�}�c�̗т������āA�����ɃG�]�V�J�����N�~�ɂȂ�Ƃ�����Ƃ����x�e���Ƃ��Ďg���B㯏m�ł͂����Ŋl��V�J���ꓪ�ƌ��߂Ă���B�N�������o�����킯�ł��Ȃ��A�Ȃ�ƂȂ��A���̊Ԃɂ��������܂��Ă���B�m���������Ȃ��Ă����̒N�����������m��Ȃ����A����ł��������܂��Ă���B
�@�Ⴊ�R�������A���͉ĂɏW�߂��ώG�ȃf�[�^�̐����⎷�M���͂Ƃ̊i���ŁA���炵����ʃf�X�N���[�N�̖����𑗂邱�Ƃ������B�m�����̊J�����Ђǂ��o�b�N�y�C���ɔY�܂���Ă������A�c�����s�ɖ�O���삯����Ă��Ă����M�E�f�[�^�����Ƃ�����Ƃ�����ƁA���ǁA�s���N�ňޏk�����悤�Ȑg�̂ɂȂ��Ă��܂��̂��낤�B���͔w����L���Ȃ���A���߂������ɏ����̑����炻�̔���������B�����ĉ^���悯��A�V�J�̉e���g�h�}�c�тɏo���肷��̂��������肷��B
�@���̃V�J���A�t��ɗ�̒��q�Łu�L�����A�L�����I�v�ƒZ�������Ď��X�Ɍx�������o���Ė����Ƃ�����B�����ɂ��鎄�́A���̑����悤�ł�����Ƃ����ߗׂٕ̈ς������邱�Ƃ��ł���̂��B�V�J������قǃL�����L�������̂́A�q�g���N�}�ɑ��Ă������B�L�c�l��^�k�L�͂ނ���q���ɐ������V�J����͉�������A�����I�W�����V��N�}�^�J�́A�V�J�ɂ͂قƂ�Ǒ���ɂ���Ȃ��B
�@���������������́A�V�J�̑������炵�炭���Ԃ�u���ď������o�āA�X�m�[�V���[�Ő��ł��̔������ʂɕ����Ă䂭�B����ƁA�ق��200�����s���Ȃ��t��̒��܂�����ʂɃq�O�}�̑��Ղ̗�������c���Ă����肷��B�����ɂ́A�^����㯓��ɂ͒��������G�߂̕ς��ڂȂǂʼn������̃q�O�}���ړ�����B���ȃ��[�g����{�قǂ���B���ӂ̒n�`���炵�Ă��A���邩��Ƀq�O�}���ʂ肻���ȏꏊ�Ȃ̂��B�{���́A���̏ꏊ����͊ݒi�u�������Ɍ����Ď��̏����Ɍ��������[�g���������A���������Ɋ��荞�ݏ��������Ăċ��������̂ŁA���̃��[�g�͏�����������ėѓ���n��A�k�����n���đΊ݂̎Ζʂɑ����Ă���B
�@�ꓪ�͂��Ƃ��Ə����̏ꏊ���D����Ƃ��Ă����A���̒n��ł͎�����Z�̃x�e�����O�}�B�O������20�p������̂ŁA���Ղ���������s���p�^�[�������ʂ��₷���B���N�O�A��N�A���ł��̒J�ɓ~�������\�������Ƃ����邪�A���̌�A���̃N�}�������ߗׂɌ���邱�Ƃ͔��ɏ��Ȃ��Ȃ����B
�@�����ꓪ�́A���N��{���̑犈���͈͂��L�����̏������ӂɂƂ��ǂ��p���������O�}�B�O�N�Ԃقǂ��Ȃ蒣��t���Ē������A���낢����Ƃ���s�����N�}�����A�����Ԉ���Ă��Ȃ�����N�U�ɂȂ�I�X���B�����͕��n������Ə����т����������Ȃ�����B�ЂƂ��햳�C�ōD��S�̉�̂悤�Ȏ�O�}���������A���Ƃ�������邱�Ƃ��Ȃ������܂Ő������тĂ���悤���B���R�̔����������ʼn��x���Њd���ǂ��������ɂ�������炸�A���̂����̏������s�����Ɋ܂�ʼn������ɕ����܂��B�������낻���O�}�ƌĂԂɂ͗��h������I�X�F���B
�@����ȊO�́A��r�I�A�g�����_���ɁA�P�ɋ��R�����̕ӂ��ʂ肩����A������Ƌ����������ď������ʂ߂���͂��邪�A�C�܂���Ȏ�O�}�������A���s���̑O���������邩���s�[�^�[�łȂ�����ǂ̃N�}�����܂�ꐶ�����̎��ʂ����悤�Ǝ��݂����Ƃ��Ȃ��B
�@2008�N4���ɓ����ĊԂ��Ȃ������ɁA���̃p�^�[���Ō��ꂽ�͎̂�O�}�̕����B���̔N�͏��ϐ�ŃT�T�������オ��̂��������E���������߁A��������200���ȓ��͈̔͂������̃g���b�N��ǂ������A���̏����ɂ͉������قǂ܂������ڒ����Ă��炸�A���胊�Y���ő����^�сA���̂܂ܖk�̎Ζʂ�o���Ă����B���̂悤�Ȃ��Ƃ��N����ƁA�����̃V�J�͎p�������B�����āA�q�O�}���ǂ����ֈړ����Ă��܂��ƁA�Ăуg�h�}�c�̔����ɖ߂��Ă���B
�@��O�}�̕��́A���Ɏ��̐�������������A���炭����ɐ�������i��2�T�Ԃقnj�A�ނ����܂��������R�̔����t�߂ŏ����̔w��Ō����̂Ɠ������Ղ����͊m�F���A�����čK�^�Ɍb�܂��A�o�J�F���猩���ɐ��������ꓪ�̋��т̃I�X�F��ڌ��ł��邾�낤�B
|
|
��l�̐搶�������X�J���N�ƃI�I�J�~(StripedSkunk��GrayWolf�j
�������u�e���g���[���֎�����ɂ̓E���t�ɂȂ�A�P����X�J���N�ɂȂ�I�v������
�쐶�̋���
�@�k�Ăɂ͐���ރX�J���N���������邪�A���ɓ���݂̂���X�J���N�́A�k�̓J�i�_�܂ōł����ʂɂ݂���StripedSkunk�i�ȃX�J���N�H�j�B�����P�Ɂu�X�J���N�v�ƕ\�����Ă���̂ł������炸�B
�@�X�J���N�̕���t�Ƃ����͔̂��ɋ��͂��B�J�E���^�[�A�\�[���g�iCA�j�̒������l�A�T���̋����ł��̉t�̕�������ƁA�܂����|����قǂ����B�����X�J���N�̕����ɂ���A�k�o�̋ɂ߂ē݂��q�g�ł����P�q���ꂽ�ꏊ���番��t�˂����X�J���N�̑��݂�m�邱�Ƃ��ł���قǂ��B���ꂾ�����͂ȕ���t�Ȃ̂ŁA���X�A���C�O�}���x�̑傫���̃X�J���N�ɏo���킵������ȃO���Y���[���v�킸�T�b�Ɣ�ёނ��ē�������Bbluff
charge�Ȃǂ�����]�n���A���̃X�J���N�ɑ��Ă͂Ȃ��B�������������A�X�J���N���h�����Ȃ��悤�����ƌ����邵���O���Y���[�ɂ͏p�͂Ȃ��̂��B��X�̃J�E���^�[�A�\�[���g�����̕���t�قNj��͂��ǂ����͔��������A�q�O�}�����ނ��錴���E�R���Z�v�g�͓������B���ޕ����ł���Ȃ���A���ׂẴX�J���N����p���邱�ƂŁA���q�O�}�́u�����v�ɂȂ肤��B
�@�X�J���N��CA�ɂ́A���̑��ɂ����낢�다�ʓ_������B�˒�������4�`5���O��B���˂��ڂ�����Ƃ��炭�ڂ������Ȃ��قNj���B�h���L���q�O�}�����n�ł͓Ɠ��B�X�J���N�̕���t�̎听���̓u�`�������J�v�^���iC4H9SH�j�Ƃ��������炵���B
�@�܂��A�X�J���N�ɂ͑���ɑ���Ɠ��̌x���p��������B�t���������Ĕ��𗠕Ԃ�����t�˂������t��(���B�j�����X�Ƒ���Ɍ�����s�����B�����g�́A��O�}�ɑ��ăT�C�h���C���_�[�ƌĂ�ł���x���s���������Ȃ��Ă���B���˂̑O�ɁA�V���J�V���J��CA�{�g�����U���ɐU�铮�삾���A���̂悤�ɑ���ɕ�����₷�������I�ȓ���ł܂��x�����A���̌x�������Đڋ߂��鑊���CA�Ȃ蕪��t�Ȃ�˂���B��x���̍U�������q�O�}�́A��x�ڂ���͂��̌x���s�ׂŏ\�����ʓI�ɉ������邱�Ƃ��ł���\��������킯���B
�@���́A��������́u�L���̃t�F���X�v�Ƃ��������̓A���X�J�̃e�B���o�[�E���t�iGrayWolf�j�ɋ���������@���B�E���t�Ƃ����̂̓O���[�v�ł��̐����L���̃e���g���[�������A���̍L��ȃe���g���[���Ǘ����邤���Ŕނ�͉��i�n�E�����O�j�̑��ɏL���i�}�[�L���O�j��p����B
�@���ăf�i���̓�Ńe���g���E���t�̌Q��ɉ������Ɉ͂܂ꂽ���Ƃ�����B�ْ����Ȃ�����������s�����A���ꂱ��z�������ǖ����Ă��܂��킯�����A����������̎U��ɏo������ƁA�Ɠ��̏L��������ꂽ�Ղ�����m�F�ł����B���̃e���g���P������܂ł͂Ȃ��������e���g���[���֎����悤�Ƃ����A�Ǝ��͏���ɃI�I�J�~�̂����t�����߂��Ă���B
�@�J�i�_�̃��[�R���e���g���[�Ƃ��炷���̍����t�߂Ńu���b�N�x�A�ɑ厖�ȓ炪���ꂽ�Ƃ��A����������ɏ��ւ�O���[�X��h���ĕ������̂̓E���t�ɕ�����������B�O���[�X�Ƃ����̂̓A���X�J�̌���ł͎�ɏe��Ɏg����B�V���b�g�K���ɂ��냉�C�t���ɂ���\�ʂ��O���[�X�A�I�C�������ƒʏ�e��͂����Ƃ����ԂɎK�т�̂ŁA�n���^�[��͂�������イ�O���[�X�A�b�v�A�I�C���A�b�v���e��Ɏ{���킯�����A�ꌾ�Ō����ƁA�e��̏L���͓S�̏L���ł͂Ȃ��O���[�X�A�I�C���̏L���Ȃ̂��B�܂�A���́A���̏��ւƃV���b�g�K�����֘A�t���ău���b�N�x�A�Ɏ������������킯���B�������A�K���I�C�������ʂ����̂̓I�C���ƂƏe�킪��r�I�����֘A�t����ꂽ�k�Ă̐X�����炾�B�������{�ł���Ă����炭���ʂ͔������肩�A�t���ʂ̏ꍇ�����邾�낤�B
�@�����̏L���́A�q�O�}�̍s���ɍ�p����u�֘A�t�������v�ɂ�����B
�@�u�e���g���[���֎�����ɂ̓E���t�ɂȂ�A�P����X�J���N�ɂȂ�v��������قɕ������邩���m��Ȃ����A���R�Ɋw�ԁA���R�̐ۗ��E�������������Ƃ������̃X�^���X�́A�ȒP�Ɍ����Ƃ����������Ƃ��B�u���R�̍������v�Ƃ������Ƃ����������A���̍ł��M���ł��鍇�����̒��Łu�I�I�J�~�ƃq�O�}�͒��N�������Ă���v�Ƒ����邱�Ƃ��ł��A�q�g�ƃq�O�}���������Ă䂭���߂Ƀq�g���I�I�J�~�̎�@���������̂́A���͋ɂ߂ė��ɓK�������@�Ƃ������Ƃɂ��Ȃ�B�I�I�J�~���q�O�}���X�J���N���Ȋw�������Ă͂��Ȃ����A���ɉȊw�I�ō����I�ȕ��@�ŋ������ʂ����A���N���ɐ��������Ă��Ă��铮���ƌ�����B
�@�I�I�J�~�̓e���g���[�Ǘ��c�[���Ƃ��āu�n�E�����O�v�Ɓu�}�[�L���O�v��p���Ă��鄟�������̈Ӗ��͔��ɏd�v���Ǝv����B�u�n�E�����O�v�͉��Œ��o�ɑi���A�u�}�[�L���O�v�͏L���Śk�o�ɑi������@�ł��邪�A���̂悤�ɕ����̕��@�Ō֎��������Ȃ��_�́A��X�q�g���w�ԂƂ��낪�傫���B��X�q�g���q�O�}�ɉ������֘A�t���Ċw�K������Ƃ��A�����̕��@�Ŋ֘A�t��������̂����z�I�ł���Ǝ������Ă���B
�@�ŋ߁A�l�ԊE�ł́u�q�O�}�̕ی�Ǘ��v�Ƃ������������Ȃ����B�I�I�J�~�ɑ��̖쐶������I�I�J�~��ی�����悤�Ƃ����ӎ��͂������Ȃ����A�����̃c�[����p���Ď���̃e���g���[�̌֎������邱�Ƃɂ���āA���ʓI�ɂ��݂������݂��̕ی�Ǘ������Ă���Ƃ������������ł���킯���B��������̌����u���R�̍������v�ł���B�l�Ԃ̃e���g���[�́A�T�ˎ��̋K�肵���l���܂łł���B���������āA��X�͐l���̊Ǘ��Ɋ���̊m���ȃc�[���E�}��������Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B
�@�l�Ԃ̏ꍇ�I�I�J�~�̂悤�Ƀ}�[�L���O�Ƃ����킯�ɂ͂����Ȃ��̂ŁA����ɑ��鉽�炩�̌��ʓI�ȕ����Ȃ茻�ہE�s�ׂȂ��p����Ƃ������ƂɂȂ�B�Ȃ����A���̕������X�J���N���ʂ������ăq�O�}�Ɋ���S�������������Ό������ƂȂ����낤�B�J�v�T�C�V���͂��̈�Γ�_�����L�͂Ȍ��̂ЂƂł���B
�q�g�̍s���u�ی�Ǘ��v
�@�쐶�����́u�ی�Ǘ��v�Ƃ����Ă��܂��Ɣ��ɍd�������ŁA���������Ȋ�������l�����ɂ͂��邾�낤�B�m���ɂ���Ӗ������Ȃ킯�����A���̘����ɂ͂���Ȃ�̎��̗͂��t��������B�����E�Ȋw�ɂ��l�ނ̎��͂����A�܂�Ƃ���u�l�ނ͒n����ŗ͂������������v�킯���B
�@�Ƃ��낪�A���̎��͂́u�^�̍������v���炷��ƁA���Ȃ蒆�r���[�Ȃ��̂ƌ��킴��Ȃ��B�u�^�̍������v�Ƃ́A�����Ă��܂��u�F���̍������v�ƁA����P����n���́u���R�̍������v�̂��ƁB�l�ނ́A���炭�O���ȓ��ɒn���̐����w����łɒǂ����ގ��͂�L���Ă��邪�A�{���ɍ����I�ȕ��@�Ő������т���͂܂ł͎������Ă��Ȃ����������̓q�g�̎����͂��������߂��Ă���B
�@����܂ł́u�������邱�Ƃ��l�ނ�ɉh�����邱�Ƃ��v�Ǝv���Ă����B�쐶�������X�т��͐���C�m���A�Ȋw�Z�p�Ő���������������������ΐl�ނ̖����͖��邢�ƁA����Ȃӂ��Ɏv���Ă����Ƃ��낪����B���̕��������l�ނ̎��B��̐헪�ł���Ƃ܂Ŕ��R�Ǝv���Ă����B���̌��ʂ��A�n�����x���̊���l�Ԃ̐��_�ɂ���ƂȂ��Đ����o�Ă���̂ł͂Ȃ����B��ɂ����x���G�ꂽ�A�G�R�V�X�e������A���g���A�����Ď��E�Ȃǂ́A�{���ɑ���ɓn�鏔��肪���ꂾ�B�����������͂��������̂��l�ނł���A������s���Ă��Ă��܂����̂��l�ނł���B���̎��o�������Ŕ��Ȃ����߂��u�ی�Ǘ��v�Ƃ�����������ԂŘ����Ȍ��t�ŕ\������Ă���Ɖ��߂��Ă����Ǝv���B
�@�ł́A�����u�ی�Ǘ��v�Ƃ͉��Ȃ̂��Ƃ����ƁA���́A��q�́u�I�I�J�~�̃e���g���[�Ǘ��v�ɒʂ���Ƃ��낪���ɑ�Ȃ킯���B�I�I�J�~�ƃI�I�J�~�A�I�I�J�~�ƃq�O�}�A�I�I�J�~�Ƃ�����쐶�����A�����Ƃ����I�I�J�~�ƃ^�C�K�̐X�A�I�I�J�~�Ɖ̈́����������͂��悻�u���Ɉ���I�ɑ��݂��Ă䂭�E�������т�v�悤���ꂼ��̐����헪�A�Ђ��Ă̓G�R�V�X�e���Ƃ����@�\�n���o���オ���Ă���B�I�I�J�~�͎����̐헪�Ő�����}��e���g���[�̊Ǘ������Ȃ��猋�ʓI�ɂ����鎩�R����ی삵�Ă����A�܂�l�ԗ��ɂ����u�ی�Ǘ��v���s���Ă����Ƃ��\���ł���B�v����ɁA���ɂ̕ی�Ǘ��Ƃ����͎̂��R�E�̋����̂��ƂȂ̂��B
�@���ݍs���Ă���q�O�}�̕ی�Ǘ��Ƃ����̂́A����̐l�ނ̓ˏo�����G�S�����Ȃ薞��������u�����v�u�����v�̕��@�̂��Ƃł���B�ǂꂭ�炢�l�ނ̃G�S�A�~���A�~�]���ˏo���Ă��邩�Ƃ����A�I�I�J�~�ƃX�J���N�ƃq�O�}�ƃT�[�����ƃA���ƃg�h�}�c�̗~���i�H�j�����킹�������͂邩�ɖc��ȃG�S�A���~��L���Ă���ƌ����邾�낤�B�l�Ԉ�l��l�͑債�����͂Ȃǎ������킹�Ă��Ȃ��B���͂������Ă���͉̂Ȋw�����E�Ȋw�Z�p�Ƃ����l�ނ̞B���ȋ��L���ł����Ȃ��B����ɂ��ւ�炸�A�l�Ԉ�l��l�́A�������g���قƂ�ǒ��ڊ֗^����^���������Ƃ̂Ȃ����̋��L���Ɉˑ����A�~���E�~�]��������ɁA�X�g�b�v���X�ɉ��X�c��܂��Ă����킯���B�P�������͂��Ă����A��������������l�Ԃ͈�ʂŎ����Ă���Ɨ������Đi�ނ����Ȃ��B
�@���́A�q�g�̎��ł��\�͂������i���I�Ɏ����͂̂���X�L���́A���X�ɕ����ԃq�g�̗~����������Ȋw�Z�p�ł͂Ȃ��ė~�����R���g���[�����鐸�_�I�Z�p���ƁA�l�ނ̗L����Z�p�i�K��������������ɂ����������Ă���ƁA���͎v���Ă���B���l�����H�������Ă���̂��A�����Ă��܂�����������ނ̂��Ƃ��B���Ȃǂ́A���炭�ʏ�̃q�g�Ɣ�ׂĂ��~���E��]���ˏo���Ă���ƌ����邩���m��Ȃ����A���Ȃ̂͗~���̗ʁE���ł͂Ȃ��������Ǝv���B
�@�u�q�O�}�̖��̓q�g�̖�肾��v���������錤���҂̙ꂢ�����̌��t�B�ނ�̋�Y��[��������B����ԂŘ����Ȃ̂́A�u�ی�Ǘ��v�Ƌ�Y���\�����q�O�}�⎩�R�Ƃ̋����E�����Ɍ������ނ�ł͂Ȃ��A�ނ�Ɂu�ی�Ǘ��v�Ƃ����\���������o�����Ă��鑼�̃q�g�S�̂��Ǝ��ɂ͎v����B�����̂����A�u�q�O�}�ی�Ǘ��v��v���u�q�O�}�����v��v�ƃX�^���X�Ƌ��ɖ���ς��鎞������̂��A���͊�]����B
100���~�E100�������̓d�C��̍s���́H
�@2011�N�A�S����100���~�Ƃ�������ȏ��������쐶�����̖h���Ȃǂ̂��߂ɔ_���Șg�ō~�낳�ꂽ�B����܂œd�C��̐ݒu���a���ċ쏜��ӓ|�������ꕔ�̔_�Ƃ��u�^�_�ł����Ȃ�v�Ƃ���Ɏ�������Ĕ�Q��i���A�u�N�}�ƃV�J�̖h���̂��߁v�Ƃ������ڂŏ������̐\�������A�����̔_�Ƃ͐��S���̎��ނ���ɓ��ꂽ�B���́u����Ől���̊댯�����������������v�Ɩ����Ɋ��҂��Ă������A�����d�C�����Ă݂ăK�b�J�������B�Ƃ������A���ɗ����B�N�}�p�̓d�C��̓����e���߂�ǂ������Ƃ������R�Ŗ�������A�V�J�݂̂Ɍ����d�C��̐ݒu���@�ɂȂ��Ă������炾�B����ŁA�܂����N���l�����Ńq�g�ƃN�}�̃o�b�^�����������x���N���邱�Ƃ��K���ƂȂ����B�u���ꂶ�Ⴀ�������x�����̃T�M����Ȃ��̂��H�v�Ǝv�������A����������Ă���ɂ��Ȃ��A�N�}�̓��������ƒǂ�������Ƃɒǂ���8�����}�����B���낻��N�}�������_�n�̃f���g�R�[���̗l�q���ɍ~��鎞�����B�V�J�p�ł���������Ƃɂ��������e�������Ă����A�ꕔ�̃N�}�͕s���ӂɓd�C��ɐG��Ċ���������悤�ɂȂ邾�낤�B�\�z�ʂ�̃^�C�~���O�ʼn������̃N�}���~��Ă��āA�L�����v��܂����ړ����[�g�ɑI�B���͂��̃��[�g���x�A�h�b�O�ƂƂ��ɉ����Ԃ��ăL�����v�ꂩ�牓�����d�C��̃����e�i���X��҂������A�҂ĂǕ�点�ǂ���͂��ꂸ�A�Ƃ��Ƃ�9���ɓ������B���̎��_�ł̑O�����͂��悻10��ށB�Œ�ł����̐��̃N�}���~��Ă��āA��������Ă��邱�ƂɂȂ�B���炭�A�����e������Ȃ��V�J�p�̓d�C��̉����@��Ԃ��ăf���g�R�[�����ɐN�����Ă���̂��قƂ�ǂ��낤�B�����L�ѕ���̓d�C��ł́A�قƂ�Ǘp�͑����Ȃ��B�P�Ȃ�Ў�ȃq���ł����Ȃ��B�V���������A�����ǂ��ɂ��Ȃ�Ȃ������B���N�A�����̃N�}���d�C�̌@��Ԃ����w�K���Ă��܂������Ƃ��E�E�E�E
�@���ꂪ�A���łŎ�ɓ��ꂽ�d�C��łȂ���A�������匾���Ƃ���܂ł̂��Ƃł͂Ȃ��̂��낤�B�������A���̏ꍇ�A�\���ʂ�ɃN�}�����h����̐ݒu���@���̗p����`�����_�Ƃɂ͂���B�����āA���ނ͌��ł����m��Ȃ����A�����e�i���X���炢�͔_�Ǝ��g���������肨���Ȃ��`��������B������Ȕ_���Ȃ����āA����������O��œd�C����������Ă���̂��낤�B����ł�l�グ���悤�Ƌc�_���Ă��邳�Ȃ��A����Ȃ��Ƃ͒N���l���Ă��킩�邱�Ƃ��B���ꂪ���s����Ȃ������B�����Ă��̌�����e�F����s���B�����Ă��̎Љ�B���W����C�����ɂȂ����B
�@���́A���̎�̔_�Ƃ̔�Q�h�~�̂��߂ɓ����̂̓o�J�炵���Ȃ����B�����܂ʼnߕی�ɐŋ����g���ĉ��ł�����Ă�����āA�Ō�̃����e�i���X�������܂��������C�̂Ȃ��_�ƂȂǁA����ɂ�������B����œ��R�̔@���N�}�����������āA�u��Q���I��Q���I�v�Ƃ�߂��ȁB���̒��ɂ́A�N�}���V�J���h���Ŏ����̔_�Ƃ��������萬�������悤�ƈꐶ�����w�͂��Ă���_�Ƃ����Ă���B���́A���̐l�����̗͂ɂȂ�ׂ����ƁA�����Ɋ������B
�@���炭�A���̔_���Ȃ�100���̂����ŁA�N�}���͓D��������B�d�C�����Ȃ��N�}���킴�킴���ʓI�ɂ���A�������ɃN�}�p�̓d�C������Ƃ��Ă��A�����Ȃ��̂��@��Ԃ��ĐN�����鎖�Ⴊ���o���邾�낤�B����Œz���グ�Ă����u�d�C��̃q�O�}�ɑ���h����100���v�͖����ꂩ�`���ƂȂ邾�낤�B����͔_���Ȃ̖��m�ƑӖ��������N�����l�Зv�f���������Ƃ��炾�B
�@�@�@�@ �@�@�@ �@�@�@
| �@���̓d�C��͍��N�͂��߂Ē���ꂽ���̂����A3�i��ł͂Ȃ��B�E�ʐ^�ł͐h�����Č����邪�A���ނ�̒��ɍʼn��i�̈�{�����ɗ��݂����悤�ɉB��Ă���B���R�A�R�d�͒������A�قƂ�ǒP�Ȃ�q���Ɖ����Ă���B����120�p�̍ŏ�i�ɂ܂ő����G��Ă���̂����������A�قƂ�ǁA����A�܂��������C�̂Ȃ��؋����B�����āA���̔_�n�̂܂��ɂ͈ȑO�ʂ�N�}���������A�ό��q��Z���Ƃ̃o�b�^��������ڌ��������Ă���B100���~�S������Ȃ����낤���A�_���Ȃ͂���Ȃ��̂̂��߂ɃJ�l����܂��]�T������̂��H�@�����ď���ő��Ř_�c�̖{�l��́A���̌�����m���Ă���̂��H |
�\�\�\�Ƃ����̂����݂̂Ȃ炸����̖{�������A���Ăǂ��������̂��E�E�E�E���ꂪ���ɂ͂킩��Ȃ��B
�@�_���Ȃ����ł͂Ȃ��A�_�����܂�����̖��m�m�Ǝv�킸�\������N�Z���ǂ�������B�쐶������ł��̓����̂��Ƃ�m��Ȃ��f�l���C������K�ł��ꂱ�����Ă����ʂ͒m��Ă��邵�A�q�O�}�̏ꍇ�͈����ɂȂ��邱�Ƃ��قƂ�ǂ��B�����Ă��̈����Ƃ́A�l�����ł̐l�g��Q�̊댯��������܂ށB�l���̈��S�������������̂��B���ꂪ�A�c�O�Ȃ���A���݂̖k�C�����֖��ɐi��ł���o�H���B���̗���́A�ǂ�����ĕς����炢���̂��낤�E�E�E�E�E�H
�@���W�Ƃ����C���ŏ�������q�����璭�߂āA����Ɉ��W�Ƃ��Ă����Ƃ���A����Ƃ��납�炱�̖��Ɋւ��Ĉӌ������߂��A�ʏ�ʂ��R�Ǝ��M����@����̂ŁA��������ڂ��Ă������Ǝv���B���܂ɂ́A���������̂������E�E�E�E�E
�u100���~�E�P�O0���v�̏������d�C��̓^��
�@���݁A�d�C��̗L�����͓��{�e�n�E����̖쐶�����ɑ��ė�����A���łɓd�C����ɂ����쐶������Ƃ����͍̂l�����Ȃ��Ƃ���ɂ���B�������A���̓d�C�u�S����v�ƌĂ��悤�ɁA�P���ȕ�����i�l�b�g�t�F���X�Ȃǁj�ɔ�ׁA�쐶�����ɑ��邩�Ȃ荂�x�ȐS���I�E����I�v�f�������Ă���_�͋ɂ߂ďd�v���B���̂��Ƃ́A�e��̓����ɑ��āA���ꂼ��̓����̓����ɑ������ݒu���@������A������Ⴆ��ƌ��ʂ��������肩�A�w�K�\�͂̍��������ɑ��Ă͌����ȃ}�C�i�X���ʂ�����邱�Ƃ��Ӗ�����B
�@���̕M���i���q�O�}���낤�B�q�O�}�̒m�\�̓C�k�Ɨ쒷�ނ̊ԂƂ���A�w�K�\�͂����ɍ����B��x�w�K�������ւ̏�K���E�p�����������A����ɁA�q�O�}�̐����N��20�N�`30�N�Ƃ����̂��A�q�O�}�ɉ����w�K�����邩���d�v�ȃt�@�N�^�[�ɂ��Ă���B
�@�q�O�}�̏ꍇ�A�}�C�i�X���ʂ͔_�Ɠ��̌o�ϔ�Q�����̍���ɉ����A���X�ɂ��Đl���y�ю��ӂł̐l�g��Q�̊댯���̑���Ɩ��������܂ށB
�@�d�C���̕K�{�����́A���̓����ɑ��čœK�Ȑݒu���@�ŁA�m���ɓd�C�����������悤�ɐS���I�ɖ쐶�������R���g���[�����邱�Ƃł���B���Ƀq�O�}�Ɋւ��ẮA�͂��߂đ��������d�C��ŋ���ȓd����^���A���S�ɓd�C�����������悤�ɐS���I�Ɏ����Ă������Ƃ��d�v�ƂȂ�B���ꂪ����Ɏ����ł����ꍇ�A���̃q�O�}�͓d�C����щz���悤�Ƃ��A�ːi���ē˔j���悤�Ƃ��A�����@��Ԃ����Ƃ����v���]�n�͂Ȃ��A�ꍇ�ɂ���ẮA�s�����j�܂�Ă��d�C��̐����[�g���ȓ��ɋߊ��Ȃ��B�d�C��͖h���t�F���X�����u����c�[���v�Ƃ��Ă̐F�������Z���A�����ɏœ_��u���Ȃ��d�C��̈��ՂȐݒu�́A�ނ��땾�Q�������炷�\���������B
�@�q�O�}�́A�����ځi�ЂÂ߂̓����j�ƈقȂ�l�ԓ��l�̗����ŕ������ߒʓd�����͂邩�ɍ����A���A�k�o�̓����ł��邽�߁A�͂��߂đ����������ȏ�ǂɑ��Ēʏ�@�Ŋm���߂ɂ����B���ʁA�����d�����@����f���ɗ���邱�ƂɂȂ�B���������A�g�̓����E�s���������q�O�}�ɑ��Ă̔��ɍ����d�C��̖h�����������炵�Ă���B�n�������ɂ�����q�O�}�p�d�C��̖h������100���i�k�C���E�T�[�W�~�����L�E�~�j�B���̑��̒n��ł����肩��q�O�}�ɓK�����ݒu���@�Ń����e�i���X�������Ȃ����ꍇ�A���l�̖h����������Ă���B
�@����܂łɓd�C��㗝�X�A�_�ƁA�s���A�����҂Ȃǂ����Ƃ߂Ă����q�O�}�ɏ\�����ʂ̂���d�C��i�q�O�}�p�d�C��j�̃X�^���_�[�h�́A�d�C�C���[�����i����20�40�60�p�̂�����u1�d3�i�v�̓d�C��ŁA�ŏ�i��10�p�グ�Ă��\���ɋ@�\���邱�Ƃ��ŋ߂킩���Ă��Ă���i�ې��z�u�������̐X�v����Ȃǁj�B
�@�ݒu���@�̕K�{�����͍ʼn��i�ɂ���A���ꂪ�n�ʂ���20�p�ȏ㗣���ƁA�̌@��Ԃ����N����A�Ȃ������̊w�K�́u�d�C�@��Ԃ��ē���v�Ƃ������̂̂��߁A���̌̂́A�ǂ��̂ǂ�ȓd�C��ɂ���Ċw�K�������ɂ�炸�A�ʂ̏ꏊ�ł��A�d�C��ɑ�������Ɓu�@��Ԃ��v�������Ȃ��Ă��邱�Ƃ��قƂ�ǂ��낤�B����́A����̃q�O�}�Ɋւ��鐫���ł͂Ȃ��A�q�O�}�S�̂Ɍ����X�����B
�@�^�p�i�K�̕K�{�����́A�����e�i���X���B�d�C��̃����e�i���X�Ƃ́A�u�R�d��h���d�����ێ�����v�Ƃ������ƂɏW��ł��邪�A��̓I�ɂ́A�̑����蓙�ɂȂ�B�Œ�ł��d����5000V��K�v�Ƃ��A���ɂ�鏬�}�̗������̑��̎��Ԃɂ��j�]���Ȃ��悤�A���펞��7000�`9000V�̓d�����ێ�����̂��]�܂����B
�@����A�����ŕ��y������u�V�J�p�d�C��v�̊�{�`�͒n�ʂ���30�`40�p�Ԋu��3�`5�{�̃��C���[��^�C�v�̂��̂ŁA����Ɋւ��ẮA�����e�i���X���\���ɂ����Ȃ��Ă��Ă��q�O�}�ɑ��Ă͏\���ɂ͋@�\���Ȃ��B�x���ꑁ����q�O�}�ɂ��u�@��Ԃ��v���N���A����������Ȃ��q�O�}�̐����N�X�����X�������ǂ�̂����ʂ��낤�B�����e�i���X���s�\���ȃV�J�p�d�C�A���̓q�O�}�ɑ��čł����ʓI�Ɂu�@��Ԃ��v���w�K�����鈫������c�[���ƂȂ�B
�@�ʼn��i���n�ʂ���30�`40�p���ꂽ��ł́A�����̃q�O�}�͎��R�ɓ��������Ă����낤�Ƃ���B��w���ɂ����ēd�C���C���[���G��ēd�C������邪�A����ł͏\���Ȋ����܂Ŏ����Ă����Ȃ��B�����e�s�\���Ȃ�Ȃ����炾�B���̃N�}�͌y���d�C�̎h����������ēd�C����z���悤�Ƃ��A�ނ�ɂƂ��čł����ӂȁu�@��Ԃ��v�Ƃ������@�őΉ����Ă��邱�Ƃ������B�q�O�}���u���Ƃ����Ă��̍���z���悤�v�Ɗ�Ă��i�K�ŁA���͓d�C��̖h���͎��s���Ă���B
�@�܂��A�q�O�}���N�����Ă���_�n�́u�V�J�p�d�C��v�̃����e�i���X���A�_�Ƃ��ł��邩�H�Ƃ��������I�Ȗ��������ł��Ȃ��B�q�O�}�̑����̓f���g�R�[���Ȃ�ΐN�������܂ܒ��ɋ���������A�_�n�e�̖��ɐg����߂��肵�ē������߂����B�f���g�R�[�����̒����Ŕ_�n�̒�����q�O�}����яo�ė�����A�e�̃T�T������Q�Ăē�������́A�N�Ԃɉ��x���͌o������B�܂�A�V�J�p�d�C������E�̈����f���g�R�[�����ɐݒu��������Ƃ��āA�N�}�p�p�����`�ɂ��邱�Ƃ��K�v�ƂȂ�B�_�u���h���̊�{�`�́A20�40�70�100�130�p�́u1�d5�i�v��B����5�i�̃V�J�p�d�C��̕ύX�Ȃ�A�o��I�Ȓlj��͈�ؕK�v�Ȃ��B
�@�n�������ł́u�h����100���v�Ɋւ��āA�֒��E��ׂ͂Ȃ��Ǝv����B���������ہA�k�C���̑����̒n��ł́A�n���ƈقȂ�u�V�J�ƃN�}�̃_�u���h���v���v������Ă���n�悪�����B���ɗ��_�̎����ł���f���g�R�[���͏]�����N�}�ƃq�g�̊Ԃɍ����a瀂������炵�Ă������A�o�C�I�G�^�m�[���R���̉��i�㏸�̉e�����A�_���Ȃ̎��Ɛ��Y�x���̐�����㉟�������ē����e�n�Ŕ�Q�������������Ȃ���A��t�ʐς𑝂₵�Ă���ɂ���B
�@�k�C���ł́A�d�C��̌������^�p�̂����炷�P��I�����A����ɂ̓q�O�}�Ɋւ��Ă̐����ɂ��Ă̕��y�E�[�ւ��\���Ȃ���Ă��Ȃ��������߁A�e�n�Ōo�ϔ�Q�z�������������ȃV�J�̖h���ɕΏd���A�q�O�}�̖h�����Ȃ�������ɂ����X�������܂��Ă���B
�@�V�J�p�d�C��̐ݒu�������ꍇ�̃q�O�}�ɑ��鈫�e���́A��q�u�@��Ԃ��v�̖����ɂ���B��x�q�O�}�ɂ�����w�K������ƁA20�`30�N�ɂ킽�肻�̃N�}���@��Ԃ��������Ȃ��Ă��邱�Ƃɉ����A��n�`���ɂ�邻�̍s���p�^���̊g��A���邢�́A�@��Ԃ�����ɑ��������q�O�}�̐V���Ȃ�@��Ԃ��w�K�Ȃǂ���`���A������̃G���A�̃q�O�}�̕����ƌĂׂ�悤�Ȗ����̎d���������\��������B�u�q�O�}�̕����v�Ȃǂƌ����Δ����߂����A���ۂɔ_�앨��Q�Ɋւ��Ẵq�O�}�̚n�D���E�����͒n�搫�������A�Ⴆ�Γ���ł͈�A���y�ł͏�������Q�ɑ����A����ł͂��̂ǂ�����R�ۂɍ�t�����Ă���q�O�}�̔�Q�ɑ���Ȃ��B�܂��A���y�Ńq�O�}�ɂ܂�����������������Ȃ��r�[�g�́A�Η��ł͔�Q���[�������Ă���B�܂�A�H���Ɋւ��Ăł����A�q�O�}�ɂ͋����w�K���ʁE��������p���Ă��邱�ƂɂȂ�A����͈��̕����I�Ȓn�搫�ƕ\���ł���B
�@2011�N�A�_���Șg�Łu100���E100���v�Ƃ�������쐶�������p�̏��������S���ɍ~�낳�ꂽ�B����́A����ɂ����ĉp�f�ƕ]���ł��鏕�������Ǝv�����A2012�N9���܂łɎ��ۂ̐ݒu�Ɖ^�p���m�F���A�c�O�Ȃ���A���̏����z�����傾�������䂦�ɁA�q�O�}�̌o�ϔ�Q�E�l�g��Q�ϓ_�ł́A�����ď������Ȃ������������Ă���Ƃ��]���ł���B
�@���̒����G���A�i���y���j�ł��������̓d�C���̏������ɂ���Đݒu���ꂽ���A���_�͓����B��́A�\���i�K�Łu�N�}�ƃV�J�̖h���̂��߁v�Ƃ��Đ\������Ă���ɂ�������炸�A�����e�i���X�̉������肪�ʓ|�Ƃ������R�ŁA�ݒu�i�K�ŃN�}�h�������̂ɂ���Ă���_�B��_�ڂ́A���̃V�J�p�d�C����A�قƂ�ǃ����e�i���X����������A�d���������肫���ĒP�Ȃ�q���ɋ߂��Ȃ��Ă���_�B
�@���ʁA�q�O�}�̍~�_�n�͑O�N2011�N�ƕω��Ȃ��A�قƂ�ǂ̃q�O�}���������d�C��̃f���g�R�[�����ɐN�����A�o�ϔ�Q�͂Ƃ������A���̔_�n���ӂł̊ό��q�E�Z���ƍ~�_�n�q�O�}�Ƃ̃o�b�^��������ڌ����N���Ă���B���̎����́A�������̓d�C��ݒu�ɂ���ăq�O�}�̑��Ɂu�ɕω��Ȃ��v���������̂ł͂Ȃ��A�����̃q�O�}�����ʓI�Ɂu�@��Ԃ��v���w�K���Ă��邱�Ƃ������A���̒n��ɂ�����d�C��ɂ��q�O�}�̖h����������Ă���ƕ]��������Ȃ��B
 |
 |
�ʐ^���F2012�N9��5���B�e�B�������̍s���B30�p�Ԋu�̃V�J�p�d�C���A3�i�ł͂Ȃ��B���ނ�̒��ɍʼn��i��{�����ɗ��܂��悤�ɑ��݂��Ă���B���R�Ȃ���R�d���N���ēd����������A�قƂ�Ǔd�C��Ƃ��ċ@�\���Ă��Ȃ��B���̐L�ѕ����������A�����e��ӂ��Ă���Ƃ������́A�͂��߂�����C���Ȃ��悤�ɂ���������B��������́A���̔_�n�̍�ŁA8���ȍ~��1�����ŁA�e�F���܂�10���O��̃N�}���u�@��Ԃ��v�u�����蔲���v���w�K�����ƍl������B
�ʐ^�E�F���N9��6���B�e�B�d�C�̌@��Ԃ��B���̎ʐ^�͔_�n����o�邽�߂̌@��Ԃ������A�V�J�p�d�C��ł́A���̂悤�ȏK�����x���ꑁ����N���n�߁A�V�J�p�d�C��̕��y�ɂ���āA�ꍇ�ɂ���Ă͋}���ɐ��𑝂₵�Ă����B��^�̃I�X���b������������Ȃ����ꍇ�A�V�J�̌Q�ꂪ���̏ꏊ�𗘗p���đ����Ŕ_�n�ɐN������P�[�X��������B |
�@�_���Ȃ��A���������O��E�z��ŏ��������~�낵���킯�ł͌����ĂȂ��낤�B�܂��A�������\���i�K�̖ړI�Ɋւ��ė��s���`���Â���̂́A�ނ�������̓��{�̍������ӂ܂���A���R���Ƃ��v����B�����Ă܂��A���߂Č��łő������d�C��̃����e�i���X���炢�͔_�Ǝ��g�̋`���Ƃ��Ė��m�Ɉʒu�Â��A�����͂̂���`�Ŏw�����Ă����˂A���̂܂܁u�@��Ԃ��v�O�}�̐��͑������A�o�ϔ�Q�̉����ǂ��납�A�l���̊댯���̍��~�܂��j�~���邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ɋׂ�͕̂K���Ɨ\�������B
�@�d�C��̖��́A��㩂Ȃǂ̕ߊl��ɂ��֘A����B���Ɍ��݂̖k�C���̈ӎ��ł́A�h������͈��Ղȃq�O�}�ߊl�Ɍ��т��������낤�B�Ƃ��낪�A�w�K�\�͂̍����q�O�}�ɂ͔�㩂ɂ�����Ȃ��Ȃ鐫��������A�܂��A���łȃq�O�}�̕ߊl�����̎��ӂɂ�����q�O�}�̎Љ�\����ς��A�Ǐ��I�ȁu���̑����v�Ɓu��Ԃ�v�������炷���������サ�Ă��Ă���B�ߊl�ɂ���Ĕ�Q�������A�Ȃ����y���Ȏ�O�}�ւ̓���ւ�肪�N���邽�߁A�l�g��Q�̊댯���𑝂��A�s�X�n�o�v���͂��߂Ƃ��邱��܂łɌ����Ȃ������N�}�̍s�����ɂ킩�ɐl������ɑ������邱�ƂɂȂ���B��㩓�����A�����e�n�ł��̂悤�Ȍ��ۂ��N���Ă���Ǝv���邪�A��������������Γd�C��̃q�O�}�ɑ���h�����\�͍����̂ŁA���������ׂĂ̖������̎����ɂȂ��Ă��邱�Ƃ͊m�����B�F��̍���E���E���������~�߂̂߂ǂ������Ȃ�����A���}�ۑ�Ǝv����B
�@�����I�̔_�ƂƂ��āA�q�O�}���܂߂����ɃC���p�N�g��^�����A�_�Ɣ�Q�E�a瀂��������A�Ȃ����l���̈��S���ɔz�������_�Ƃ��߂������ׂ������A���ꂪ���݂͋Z�p�I�ɏ\���\�Ȓi�K�ɂ���Ǝv���B�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2012/09/07�@�q�O�}�̉����^㯏m�i�Ђ��܂��キ�j�E�m����\�@��� ���
2011�D�y�N�}�����̕��͂ƈӌ�
�@���̕��͂�2011�N�H�ȍ~�A�����ɂ���Ă����Ȃ�ꂽ�u�q�O�}�ߊl�Z�p���C�v�ɂ����ču�t�������ۂɗ��K�҂ɔz�z���Ă���������̂ŁA��r�I�}���ŏ��������߃��t�ȕ������邱�Ƃ𗹏����Ă��������A�ǂ�ł�����������K���ł���B
�����F�u2011�N�x�O���̎s�X�n�o�v�ƏH�̎D�y�ߍx�N�}�����ɂ��āv�i2011�`2012�N�q�O�}�ߊl�Z�p���C�z�z�j
�@��N�H�ɓ����Ă��烁�f�B�A����킵�Ă����D�y�ߍx�̃q�O�}�����ɂ��ẮA�F����̂ق����ڂ��������m��Ȃ��B�₢���킹�Ƃ����قǑ�U���łȂ��Ƃ��A���̌��ɂ��Đ��������߂���@������Ă��邪�A�D�y�݂̂Ȃ炸�A2011�N�͏㔼�����瓹���Ŏs�X�n�o�v���N�����B�����g�A�e���n�ŖȖ��Ȓ����������Ȃ����킯�ł͂Ȃ��A�܂������Ă������܂�ɖR�������_���d�˂���Ȃ��B���ɌX�̎���Ɋւ��Ă͂����肵�����Ƃ͌����Ȃ����A2004�N����8�N�Ԍp�����Ă����k���R��i�k���R�n�j�̃q�O�}�������ʂ���A���̍l�@�������Ȃ�Ȃ��Ă͂����Ȃ��Ǝv���B
�@�q�O�}�̏ꍇ�͒n�搫���傫���A���̓y�n�̐A���E�n�`�Ȃǂɉ����A�����ɕ�炷�q�g�̃q�O�}�ւ̈ӎ���Ή��ɂ���Ă����傫���ς���Ă���B�Z���Z�[�V���i���ɂȂ����D�y�̎����ǂ݉����Ȃ���A���łɕs���Ɏv�����ƂȂ��A����̒n�搫�ɉ����ēK�ȑ���Ƃ��Ă����邱�Ƃ��肤�B
��h���O���s��ࣂ̐M�����́H
�@�܂��A�D�y�Ƃ����k�C���œˏo������s�s�x�O�ւ̃q�O�}�̑��o�v�œ��������ɍ̗p����Ă��颃h���O���̕s����v�����A�m���ɁA�{�B�̃c�L�m���O�}�A����E�n�������̃q�O�}�Ɋւ��ẮA��u�i�̎��v�Ƃ����̂��q�O�}�̓����ω��������炷���������ɂȂ肤��B�Ƃ��낪�A�����颃h���O����i�~�Y�i���E�R�i�����j�́A����R��ł������������ɕs��ƂȂ邱�Ƃ��قƂ�ǂȂ��B����G���A�ŕs��Ȃ班���W����ς���ƖL�삾������A��ΖʂƖk�ΖʁA���邢�͎Γx�ɂ���Ă��o���c�L��������B�܂�A��قǕ��R�ň��̓��ƁE�C���E���Ȃǂ�����̂���Ƃ����n�`�ȊO�Ţ�h���O���̖L���v���]�X����ꍇ�ɂ́A�T���v�����O�|�C���g�i�w�W�ƂȂ���̒n�_�j�ɏ\���ȃ��@���G�[�V�������������Ē��ׂ�K�v������B
�@���Ȃ݂ɁA2011�N�A�k���E�W��300m�`600m�G���A�ł́A�R�P�����ȊO��������s��E����X���͊m�F�ł��Ȃ��B����͎��̒����݂̂Ȃ炸�A�n���^�[�A�����̐��Ƃ̋��ʂ����������B
�@�܂��A�q�O�}�̐H�������i���̍̎�E���́j�������Ȃ��Ă������ʂ���́A�k���R��̃q�O�}����̎��Ɉˑ����Ă���X���͏������A�h���O���̖L���ɂ�����炸�A�̎��Ƃ��Ă͂ނ���H�̎�H�̓}�^�^�r�E�R�N���E���}�u�h�E�ɕ�B�����Ă܂��A���̎�H�̂����ǂꂩ���s��E����ł����Ă��A�q�O�}�͂ق��̐H���ŕ���ď\���Ȣ�H�����ߣ�������Ȃ��Ă���ƍl������B
�@�D�y�s���ӂɂ͓K�p�ł��Ȃ����낤���A�����钆�R�Ԓn��ȂǂŖh�����x��q�O�}�ɂ��_�앨��Q���P��I�ɐ����Ă���G���A�ł́A8�����{�`������i�f���g�R�[���Ȃ�ʏ�9���A�x���_�n�ł�10�����{�j�܂ŁA�q�O�}�̑�������H�����ߣ�������̔_�앨�ň�背�x���܂łł��邽�߁A�R�̖̎��̖L���́A����ɉe�����ɂ����B
�@�����̗��R�ŁA���́A�q�O�}�̏o�v�Ƣ�h���O������������ʊW�Ō��т���̂́A��댯���Ǝv���B
�@�������A�������h���O���̕s��݂̂��w�W�Ƃ��ăq�O�}�̑�ʏo�v��\�z�����킯�ł͂Ȃ����낤���A��q�͒��ӂ�v����B
�⑫�j�q�O�}�̐H���̗ʓI���́A�q�g�̐H�����������l�A�p�����E�c�������܂߂čl���Ȃ��Ă͐������l�@���ł��Ȃ��B�܂�A���ԓI�ȃq�O�}�̊����e�͂Ǝ��ۂ̃q�O�}�̐������A�����Ė̎����Ȃ�R�N���E�}�^�^�r�E���}�u�h�E�E�R�i���E�~�Y�i���E�I�j�O���~�Ȃǂ̎��̐��ƁA�ŏI�I�ɂ��̖L���B������S���l�����킹�Ă��낢�낪���f�ł���悤�Ɏv���B
���{�I�Ȍ����́H
�@���ɎD�y�Ȃǂ̃N�}�����ƃh���O���̖L���̑��ւ������Ƃ���A�ǂ������v������q�̏o�v�������I�ɗU���������H�@��������肾���A����͎D�y���݂̂Ȃ炸�A�����e�n�̒��R�Ԓn��ȂǂɈꑫ���������Ă��錻�ۂł͂Ȃ����Ɛ��@�ł���B�܂�A�����G�ꂽ���O�}�̋Ǐ��I����������A�D�y�����̎R��ł͐��N�O�̓˔��I�ȑ�ʕߊl�]�X�ł͂Ȃ��A90�N�܂ł̏t�O�}�쏜���ȗ��A��Ŋ뜜�̏�Ԃ��珙�X�ɉ����Ă����ƍl�����A����90�N���ɐ����c��A�Đ��̊j�ƂȂ����̌Q�����悩�玟��Ɏ��ӕ��֊g�U���Ă��Ă��낻��D�y���ӂ܂ŐZ��������Ƃ������_�́A���t�ł͂��邪���藧�B�����A����ɗv�������Ԃ��t�O�}�쏜�p�~����20�N�Ƃ����̂́A����������������悤�Ɋ�����B�����ȂƂ���́A�D�y�����R�k�E�������ʂɎ���R��̃q�O�}�̔N��ʍs�����z�u�ȂǂׂĂ݂Ȃ��Ƃ͂����肵�����Ƃ͌����Ȃ��B
�@���Ɏ�O�}�������֗^���Ă���Ƃ���Ƃ��āA�ߔN�̗F��̏��������čl����ƁA����Ɂu�V����x�A�[�Y���v���d�Ȃ��Ă���\��������B�q�O�}�̐������x���Ⴂ�G���A�ŁA�I�X���b�������Ă��邱�Ƃ͂����Ă��}�ɑ�����Ƃ����������Ȃ���A���ۂ��N���Ȃ��B������̂͂܂���O�}�B�����Đ��N�ォ�烁�X�F�B�T�˂����������������A�D�y�ߍx�̎R���ǂ̒i�K�ɂ���̂��́A�������Ă݂Ȃ��Ƃ킩��Ȃ��B�V����x�A�[�Y�͒m���Ȃǂ̊ό��n�Ɍ���₷���q�g�ɑ��Ė��x���E���S�ȃq�O�}�̑��̂����A90�N�̏t�O�}�쏜�p�~���邢�͂��̌���������F��̍���E���E�������炷��ƁA��O�}�̐V���㉻�͑�Ȃ菬�Ȃ�e�n�ŋN���Ă��邱�ƂƐ��@�ł���B����́A���R�̓��ɃI�X���b�̑�^���ȂǂƐ����������B�����ł͋ߔN500�s�z���̃q�O�}���ߊl����Ă��邪�A�V�J�̐������g��E�����ɉ����A������u�N�}�����v�̌������֗^���Ă���Ǝ���B�N�}��ǂ��ĎR��������d���߂��@���قƂ�ǂȂ��Ȃ�A�����ѓ����N���}�Ŝp�j���颗����£�ɕω������̂����R�Ƃ��đ傫�������m��Ȃ��B90�N��3��������O�}�́A�����c���Ă���Ƃ�����N24�B�����c��\���͐̂�肠��B
�@���R�ŁA�l�m�ꂸ��������^�������̂Ɠ����ɁA�ߔN�̎�O�}�͐l�����ӂɕ�炵�Ă��A�̂ɔ�ׂ�q�g����̃X�g���X���������ɐ����Ă�����B�ό��q������K���m���قǂłȂ��ɂ���A�X���Ƃ��ĐV���㉻�A�܂�q�g��l���ւ̌x���S�̌����͋N���ē�����O�Ƃ�������B�ߊl�̂����A�����Ƃ��q�O�}���X�g���X�������x���S��A���t������̂́A�V���b�g�K���ɂ�颒ǂ��̗v�B���ŁA�����������ˌ��ɂȂ肪���ȃ��C�t���ɂ��B�쏜�ő��p����Ă��锠㩂ɂ��ߊl�́A��߂܂�̂͂������Ȃ��߂܂邪�A������Ȃ��͉̂��X�߂܂�Ȃ��v�Ƃ��������������A���ہA�q�O�}�ɂƂ��Ă͢㩂������ӂ���Α��v�v�ƁA�q�g��l�����r�߂Ă������Ă���X��������������B�������ɁA�s�s�����ӂœ��l�̃q�O�}�������Ă���A���̂������ɢ���m�Ŗ��C�ōD��S�����ȁv��O�}�́A�D�K�Ȉړ����[�g�������݂���Εs�p�ӂɃt���t���Ǝs�X�n�E�Z��n�ɍ~��Ă��܂��̂��A�ނ��뎩�R�Ȃ��Ƃ����m��Ȃ��B
�⑫�j�x���S�̊ȃN�}�O��
�@��O�}�ƐV����x�A�[�Y�́A�O�҂����m�Ŗ��o���Ȃ��߂ɖ��x���ł���̂ɑ��āA��҂̓q�g�𢖳�Q�ł��飂Ɗw�K�������Ė��x���ɂȂ����N�}���B��l�̌��������Ȃ��Ȃ�������A��D��S��Ƃ������_�Ō���ƈႢ�������o�Ă���ꍇ������B�����A�q�g�Ƃ̊Ԃɐ�������Q�́A�قƂ�Ǎ����Ȃ��B�����I�ɂ́A�P�Ȃ��O�}�̖��x���̂ق����A��������i�ǂ������Ȃǁj�ɂ���čs�����P�͗e�Ղ����낤�B�������x���S���������q�O�}�ɁA�a�t������s�������������Ȃ�����ُ�O�}���댯�O�}������邪�A����Ɋւ��ẮA�댯�x���ˏo���Ă���B�����āA��������ȂǂƂ������U�@�ő��邱�Ƃ̂ł��郌�x���ł͂Ȃ��B
���̎��W�ƊJ��
�@�D�y�ߍx�̗�ł́A���N�A���ӂ̃q�O�}�̓������\���c���ł��Ă��Ȃ������Ǝv���邪�A�ߋ����N�ԂɋN�����o�v�Ɋւ��Ă��A���Փ��̒�����������Ȃ�ꂸ�A�c�����\���ɂł��Ă��Ȃ������̂ł͂Ȃ����B���邢�͔c�����Ă����Ƃ��Ă����J�����͂��߂Ƃ�������������Ƃ�Ă������B���̓_���^�₾�B
�@�������ɁA���Ӄq�O�}�̐����E������c�����Ă����Ƃ��āA�܂��A��O�}�̏K����m���Ă���A����̂悤�ȏo�v�͓��R�\���ł��邵�A�\�����Ă���A���̎�̎�O�}�̏o�v�͖��R�Ɏ~�߂邱�Ƃ��\���ł������낤�B�Z���ւ̌[�ցE�n��̃��X�N�}�l�W�����g�����������i��ł����ɈႢ�Ȃ��B�܂�A���N�̏o�v�͔h��ɖڌ����̂ŃZ���Z�[�V���i���ɂȂ������A���ۂ́A���Ȃ��Ƃ��������N�ԁA���l�̏o�v�����ʉ��ŋN���Ă����\��������ƁA�R�������ł��ǂ߂�B
�@���m�Ŗ��C�ōD��S�����Ȏ�O�}���炷��Ύ��������A���ɐ��������ɑ������Ȃ��Ă��A�����̔��q�ř��ߓI�ɗ��֍~��Ă��邱�Ƃ͏\���l�����A�����~�肽��ʼnƒ�؉��E�R���|�X�g�E�S�~�X�e�[�V�����E�|�C�̂ẴS�~�Ȃǂɏo�����A�����H�ׂĐl�ו����w�K���Ă��܂��ƁA��Ȃ菬�Ȃ��K���������\��������B���X�Ȕg��o�v�^�̃N�}�Ȃ�A�����������炻�������o�܂����ǂ��Ă��邩���m��Ȃ��B
�D�y�Ƃ�����
�@�����w���̍����A�D�y�s�̐l����150���ɒB�����s�����ǂ��̂Ǝ��������o�������邪�A�D�y�͍����ɏW������������200���s�s�ɔ��낤�Ƃ����������B���̐������͌���̓��{�ɂ����Ă͂��Ȃ�̂��́B���̖k�̒��̓����̓q�O�}�̐����n�Ɣw�����킹�ɂ���A�������瑱���q�O�}�����n�������I�ɂ��Ȃ�L�����Ƃ��B����ȑ�s�s�ׂ̗Ƀq�O�}�����ʂɐ�������悤�ȏꏊ�͐��E�I�Ɍ��Ă����݂��Ȃ����A����͂���Ӗ��k�C���̐l�����E�Ɍւ�鎖�����Ǝv���B�i���m�ɂ����A�܂������Ă͌ւ�Ȃ����A�������̐����R��̃N�}�Ɛ܂荇����t����������ב��v�������ł���A�����Ƃ��ɎD�y�͐��E�̊���i�s�s�ƂȂ邾�낤�j
�@���āA�D�y�����ɂ͖k������R�[�A��q�R�A�Ռk�A����R�ƎD�y�s���̂Ȃ��ݐ[���X�L�[�ꂪ�U�݂��A���̎��ӂ̎R��K���l�������B�������A�Ⴆ�Ύ��R���N���}�ŏ���ăn�C�����h�܂ōs���A�������炳��ɏ����o���Ē��ォ�琼���߂��l�́A�����������Č������R�x�̋C�z�������邾�낤�B����́A�Ռk����ł������ł���B����s�����������ɓo�낤���A�R������Đl�m�ꂸ��R�k�_���܂œ��B���邱�Ƃ��ł���B��R�k�ƒ��������ԓ���1���i��R�k���C�N���C���j�́A�X�L�[�ƍg�t�̃V�[�Y���ɂ͂���������ʗʂ����邪�A�ċx�݂ł���Ԃ͊ՎU�Ƃ��A���̖�Ԍ�ʗʂł̓q�O�}�̉��f�ɂ܂������x��ƂȂ�Ȃ��B���̓������T�N�b�Ɠn��A��R�k�_�����j���œn�낤���C�����b�g���։I�悤���A�������z����ĂюR�ɓ��蒆�R������̔������z���ċ��ɂ̑o�t�_��������܂ŁA�N�}�Ȃ�X�g���X�Ȃ��s�����낤�B����قǍL���R���݂̐����D�y�̐����ɗ����Ă���킯���B���̎R��œo�R���������Ƃ�������͂킩��Ǝv���B���̕���������w�������́A������������q�O�}�̐��������ɒ[�ɏ��Ȃ��R�����������m��Ȃ����A���̃|�e���V�����͖k���Ɉ������Ƃ�Ȃ��B�\�������̃q�O�}��{���Ă�����R�Ȃ̂��B
�@�܂��A��R�k���ӂ͂������A�������ӂł����Ȃ�O����q�O�}�̏o�v����k�������炠�����B�쑤�͎x┌ɂȂ����Ă���B���͖k������̏o�v�̂����A��������~�R�܂Œ��������Ȃ�10�q�Ȃ��B���̃G���A�̎R���������Ƃ��Ă��A�q�O�}�̑��Ȃ����œ��j���Ă��܂��������B
�@�܂�A����A�D�y����s�s������q�O�}�͖��W�ȉ������݂��Ƃ������o���́A���͍��o���B
�@�ʏ�A���R�Ԓn��Ńq�O�}�ƃq�g�̖㒅�E�a瀂��邢�̓q�O�}�̏o�v���������̂́A�ߑa���E����ȂǗl�X�ȗ��R�ɂ���ď]���l���������Ă��������E�G�l���M�[�������A�����̂���Ȃ��т���������_�n�Ȃǂ������āA�R�⎩�R�������Ă���C���[�W���B�ꍇ�ɂ���ẮA�l�����f�Љ�����ꍇ������B�Ƃ��낪�A�����q�O�}�o�v�ł��A���W�r��̓s�s���x�O�ł́A�t�ɏZ��n�Ȃǂ��g��X���ɂ���A�܂���ΖL���ȁ��~�^�E���v�Ȃǂ�ɂ����������i�߂���X���������B���L���Ȃ͓̂s��l�ɂƂ��ĐS�̕�̂悤�Ȃ��̂����A���̖L���ȗ��쐫�����Ƃ̋������k�߂Ă��錻�����ۂ߂Ȃ��B���Ƀq�O�}�̏ꍇ�A�X�g���X�Ȃ��ړ��ł���i����сj���A�l�m�ꂸ�s�X�n�E�Z��n�̎��ߋ����܂Ŏ�O�}���Ă��܂��i���o�b�h�R���h�[�^������L�j�B����̏o�v�O�}��20�̐��b�������肷��ƁA�܂��قȂ������������シ�邪�A�o�v�p�^����������ł́A�\������5�Ζ����̎�O�}���낤�B�Ƃ���ƁA�o�b�h�R���h�[�����ƂȂ������Ă�����s���~�܂�ɂȂ�A�ӂƑO����������X���L�����Ă����A�Ƃ����o�܂ŏo�v�Ɏ������̂ł͂Ȃ����낤���B���H�̉�L�Ƃ������Ƃ��B�c�ɂ��낤���s��낤���A���R�Ԓn��ł��낤���D�y�ł��낤���A�q�O�}���\�����S���Ĉړ��ł���R���h�[�����݂���A��O�}�͂��~��Ă����������Ȃ��B�����āA���x���Ȏs�����ł́A���X�ɂ��Ă��̃R���h�[�ƂȂ��Ă����M��т̒����q�O�}�͐l�m�ꂸ�ړ�����̂ŁA��ˑR�N�}���o���v�Ƒ����ɂȂ�B�����̏ꍇ�A����͓ˑR�ł͂Ȃ��B�\��������A���ӂ̖ڂ��������������������肵�Ă���A�قƂ�Lj����������Ă�����̂��B
�o�v�h�~�̎�@�́H
�@�܂��������A��̑S�̎��ӂ̎R�ʼn����N���Ă���̂���m�邱�ƁB�l�X�ȕ��@�Ńq�O�}�̒��������A�ǂ̂悤�ȃq�O�}���ǂꂭ�炢�ǂ������ӂ��ɂǂ��Ŋ������Ă��邩�A������ł��邾���������m�邱�ƁB���̒m�蓾����������A�q�O�}�ɑ��Ă��낢��ȃX�g���X�������ėݐς����A�ړ����[�g��ς�����A�����I�ɎՒf������́A�����ɉa�t���A��������K�����Ă���q�O�}�ɑ��Ă���背�x���ʼn\���B���ړI�ŋC���ŕ�������Ă����O�}�Ȃ�A�Ȃ�����B�������A���ׂẴq�O�}�R���g���[���́A�q�O�}��m�邱�ƁA��m�邱�ƁA�Ƃɂ����m�炸�ɂ͍����I�ɂ����Ȃ����A���m�̂܂܂����Ȃ����ꍇ�A���X�ɂ��āA�t�Ɉ����ނ��ƂɂȂ����Ă��܂��B
�@�����q�O�}�̖�肪���m���邢�͗\���ł����Ƃ��A�Q�Ăđ���u����̂́A�ً}���������Ă���P�[�X�������A�����߂��Ȃ��B�ł�����葫���g���Ē������������B�Ƃɂ����m�肤�邱�Ƃ��\�Ȍ���m��B�����W��o���B���̌̂̑O�����E�傫���E�ړ����[�g�͂��Ƃ�萫�ʁE�ړ����ԑсE���i�E�ȁE�H���E�̒��ȂǂȂǁA�\�Ȍ���B��ɂ͓d�C��E�o�b�t�@�X�y�[�X�̐ݒu����ߊl�܂ŃJ�[�h�����邪�A�ǂ̃J�[�h���ǂ̃|�C���g�łǂ�����Đ邩�A����f�������ăs���|�C���g�ł����Ȃ��̂��ŗǂ��Ǝv���B
�@�q�O�}�̐l���E�s�X�n�o�v�ɂ͑傫�������A��͏�q�́u��O�}�^�v�B�q�g��l���ɑ���o�����܂��A���낢����w�K���Ă���Œ��̃N�}���B����ɑ��ẮA�a�t��������Ȃ���A�������������ނ��Ƃł��悻�������Ƃ��ł���B
�@������́A�G�T���݂̃N�}�ŁA�l�����̐H�����w�K���A���̃G�T����߂����č~��Ă���^�C�v�B����́u�a�t���^�v�ƌĂ�ł������낤�B���̐H�����l�ו��i���S�~�A�R���|�X�g�A�엿�A�y�b�g�E�ƒ{�̃G�T�A�_�앨�Ȃǁj�̏ꍇ�A��r�I��K��������₷���B���̃N�}�ɑ��ẮA�S�~�ނȂ�ΓP���A�_�앨�E�R���|�X�g�ȂǕK�v�Ȃ��̂Ȃ�h��������ȊO�ɁA�������Ă������@���Ȃ����낤�B���ɏo�v���Ă���̂�1���ߊl���Ă��A�x���ꑁ����܂����l�̌̂������B�i��㩂ɂ��Ă͕ʏq�j
�@�q�O�}�̕ߊl���f�́A���̌̂̒P���Ȗ�萫�ł͂Ȃ��A�ُ퐫�ɒ��ڂ���Ƃ������ʂ��o����B
A�D�~��Ȃ����߂̐헪
���o�v���[�g�������i�ԐړI�ȃN�}���ւ̊֗^�j
�@�܂��o�v�̃c�[���ƂȂ�o�b�h�R���h�[���Ւf���邱�ƁB�Ւf�ɂ́A�I���Ƀo�b�t�@�X�y�[�X��z�u���A�q�O�}�̓d�C����i�K�v�Ȃ��i�\���E2�ӏ��Ɂj�ݒu����B�ړ����[�g�i�o�b�h�R���h�[�j�����ʓI�ɎՒf����A�܂��y���Ȏ�O�}�̏o�v�͏����邪�A�C�ۏ����Ȃǂɂ���āA�ɂ킩�Ƀq�O�}�̓������ς��ꍇ������B�Ⴆ�Ζk���̍��N�i2011�j�ł���A�䕗����̉��ђ�C���������邱�Ƃɂ��͐�̑呝���������A�n��Ȃ��N�}�������͐�ɉ����ĉE�������������A���������ω����N����ƁA�ʏ�̈ړ����[�g����ʂ̃��[�g�֕ύX����N�}���o�Ă���B���̃G���A�ł́A�q�O�}�̓����ω������m�ł����i�K�ŁA�}篁A�v���̃o�b�t�@�X�y�[�X��60m�قNJg�債�A�Ȃ����N���}�ɔ��܂荞��Őڋ߂����q�O�}�̒ǂ������������Ȃ��ė������B�܂�A�ʏ�Ȃ�\���@�\����d�C�����������ݒu���Ă��A�c�O�Ȃ���100�����v�Ƃ������Ƃ͌����Ȃ��B���Ƃ����āA������i�l�b�g�t�F���X�j���K�͂ɒ����ăg���b�v���C���[�i�⏕�I�d�C��j�Ō@��Ԃ��Ƃ悶�o���h�������̎����͂Ȃ��Ȃ������Ȃ����낤�B
�@�d�C����ӁE�ړ����[�g�R���̗v���ɂ̓f�W�^���Z���T�[�J��������ݒu���A����I�Ɋm�F����ƁA�P��I�ȃN�}�̊����m�F�ɂȂ�A�܂�������Ƃ����ω��E�O�����������ɂ����Ȃ�B
�@�v���Ƃ������t��p�������A���̗v�������o�����߂ɂ��A�o���l�Ɩڂ��K�v���B
�⑫�j�������[�g���2�ӏ��Ƃ����̂́A�͂��߂ēd�C��ɏo�����q�O�}�̂����ꕔ�́A�G�ꂽ�Ռ��Ƀr�b�N�������̓d�C���˔j���Ă��܂��ꍇ�����邩�炾�B�����r�b�N���ːi��ȂǂƒP�������ɌĂԂ��A�ŏ��̓d�C��ʼn��Ƀr�b�N���ːi���N�������N�}�́A�\������ɓd�C����w�K������S��������Ă���̂ŁA��ڂ̓d�C��͌����ē˔j���悤�Ƃ͎v��Ȃ��B�d�C��̓d�����̂��A���̌̂ɔ��R�Ɛl���ւ̌x���S���C�荞�ނ̂ŁA�\���Ƃ��Ă͂��͓̌̂�x�Ƃ��̎��ӂɂ͋߂Â��Ȃ��B���̌��������邽�߁A��ڂ̓d�C��͂ނ���w�K�p�B��ڂ̓d�C�q�O�}���~�߂邽�߂̓d�C�B�Ȃ̂ŁA���R�A��ڂ̓��[�g��ɒZ�������āA�I�₷���悤�ɐݒu����B���̌̂��ʂ郋�[�g�����Ɋ��S�ɌŒ艻����p���Ă���|�C���g�Ȃ�A��̒�����5m�ł��\�����낤�B��ڂ͋t�ɉI�ĐN���ł��Ȃ������E�`��ɂ��Ă����̂�����B�Ȃ��A�q�O�}�͓d�C��̍����d�����U�����鎥������m���Ă���\�������邽�߁i�m�F�s�\���j�A�d���̗������d�C�邢�̓t�F�C�N�̓d�C��́A������̉ӏ��ɂ��p����ׂ��ł͂Ȃ��B
����O�}�̊�������i���ړI�ȃN�}���ւ̊֗^�j
�@��O�}�ւ̌p���I�Ȋ�������B����͋Z�p�I�ɍs�����ł��邱�Ƃł͂Ȃ��̂ŁA�����N�}������q�O�}�̐��Ƃ�����A���̐l�ނ����p����B��q�A�N�}�����̗����͌����I�ɍ��㍢��Ȃ��߁A��O�}���ǂ��E�����Ƃ����Ɏ������܂��A�ǂ����������A�܂�ǂ������w�K���ǂ̂悤�ɂ����ċߗׂ̎R�ɐ��������ɁA�ӎ����v��K�v�Ƃ���B�ϋɓI��@�́A�x�A�X�v���[�A�����ʁA�x�A�h�b�O�A�N�}�����ɂ��Њd�e�Ȃǂ����A��{�I�ɁA�������܂Ƃ����������ʂ̃q�g�̊������q�g�ւ̋��Ђ��q�O�}�ɗސ�������B
�@�q�g�ւ̊����A�l���ւ̊����́A�Ƃɂ������킹�Z�ŁA�q�O�}�̐S���ɗݐς����Œ艻������̂��R�c���B
���Z���E���K�҂ւ̃q�O�}����i�q�g���ւ̊֗^�j
�@�s��̏Z���ł��R���ɕ�炵�Ă���A�q�O�}���ӎ������낢�뒍�ӂ�����炵���K�v�B���̃X�L���Ɋւ��āA�Z���E���w���Ȃǂ�ΏۂƂ����u�q�O�}�𐳂����m�邽�߂̋���v�����ꂼ�ꂨ���Ȃ��Ă����B��q����q�O�}�c����j�ɁA�ЌP���E�n�k���P�����l�A�q�O�}�o�v�P�������܂ɂ����Ȃ��Ă��������낤�B
B�D�~�肽�Ƃ��̂��߂̐헪
���q�O�}�c��
�@�h������{���Ă��o�v�̉\��������킯������A���̎��Ԃ�z�肵�A���ӊ��N�E�������萧���E�p�g���[���E�ǂ������Ȃǂ̂ق��ً}���Ԃɂ�����n���^�[�̔��C�Ɋւ��Ă܂Ŏ�茈�߂�Z���i������j�E�s���E�x�@�E���h�E�n���^�[����Ȃ鋦�c��I�ȑg�D������Ă������Ƃ��d�v�B���c��Ƃ��Ĉӎu��������A���c��Ƃ��đ�ɓ����B�Ⴆ�A�ً}���ɂ͎s�X�n�ł��e����g�p�ł��镶�������A�N�̌����ł��ꂪ�^�p���ꂤ�邩���߂Ă����B�g�D�I�ɓ����Ė��ʂȂ����₩�ɑΉ����邽�߂ɂ́A�����҂m�ɂ��Ă������ƂƁA���̌����҂��s�݂̎��̃i���o�[�Q�A�i���o�[�R���炢�܂ŕK�v�B���̑g�D�ɂ́A�K���q�O�}�̐��Ƃ��܂߂Ă����A���m����o�����\���������Ă��炤�B
���U�����Ǘ�
�@�s�p�ӂȃq�O�}�̃G�T�i�R���|�X�g��S�~�j�Ȃǂ��ł��邾����������Ǘ����āA������q�O�}���~��Ă��Ă��������߂Ȃ��悤�ɍH�v����B�q�O�}��U������̂́A�Z��n�ɂ��揤�ƒn�ɂ���d���Ȃ��B�[�т�H�ׂȂ��킯�ɂ͂����Ȃ����낤�B������A���̂ɂ����ŗU�����ꂽ�q�O�}�����Ă��A�U�������ł͎������K���͌��ꂸ�A���͂�����Ȃ��B�Ƃ��낪�A��x�ł��H�ׂ����Ă��܂��ƁA�q�O�}�̍s���͔g��o�v�ƂȂ�A�����E��K�������Ĉ�������s���̃G�X�J���[�g���N�����\��������B�q�g�ւ̌x���S�����S�Ɍ��@�����Ă��܂��̂��B�����܂Ńq�O�}�������ω������Ă��܂�����A���ꂱ���Z�����������Ōx�@�ɂ����͂āA�_�����ɂ��ˎE�쏜�����Ȃ��̂ł͂Ȃ����낤���B
���n���^�[�̈琬
�@���R�Ȃ���A�Ō�̐�D�Ƃ��Ẵn���^�[�̕ߊl�\�̓A�b�v���]�܂�邪�A����͈꒩��[�Ɏ���������̂ł͂Ȃ��B�܂��A�����ŗ\���E���肵�Ė�肪�N����Ȃ��悤�ɂ���̂��A�q�O�}�̐����n�ɓ���Ƃ��������n�Ɨאڂ��ĕ�炷�Ƃ����A�q�O�}��̓S���ŁA�����ӂ��Ė�肪�N���Ă��܂��Ɖ�����Փx�E�J�́E�o����Ċ댯���Ƃ����ׂĒ��ˏオ��̂ŁA�܂��͂��������Ɋׂ�Ȃ����߂̕����O����Ɏ{���̂��挈���낤�B�ł������̂��Ƃ�����āA����ł��N���Ă��܂����ɑ��āA�Ō�̐�D�͑�ɗp����ׂ����̂��B
�@�����Ǝ�v�ǂ�����L�������肾���A�ׂ�������͑��ɂ����邩���m��Ȃ��B
�܂Ƃ�
�@�D�y�̃N�}���������f�B�A�Ō��������Ĕ��R�ƕs���ɂ����Ă���l���������A���₩�Ɍ��A���邢�͏�����Ă���l�����̃G���A�ɂ͂���B�q�O�}�̖ڌ����܂߁A���Ղ͕��E�܍��Ȃǂ��������ꍇ�A��q�O�}�̏o�v�F�m��Ƃ����\�����g�����A���̃G���A�ł́A�R���l�����q�O�}�̕����Ȃ��ꏊ��������̂�����قǂ��������ɏo��B�Ⴆ�A��A�����̉�Ŏ�����قŏW�܂�B����ƁA�����ɗ����l��������I�������̋��ŃN�}���������v�ƌ����A����ɑ��Ģ�N�}�����I����Ϗo�Ă��Ă�Ȃ��v������̔��A���\�傫���̂��t���Ă��ˁv�ƁA����ʼn�b���I���ɂȂ��āA���R�Ɨ\��̋c��ɓ������肷��B���Ɏ�_�Ƃł��闏�_�ō͔|�����f���g�R�[���ɑq�O�}�̖h�����F���Ȃ̂ŁA8���`9���͍��ׂƃq�g�ƃq�O�}���l�����Őh�����Đ��ݕ��������Ċ������Ă���悤�ȏ��B���̒��ŁA�l�X�Ȏ�@�Ńq�O�}�ɃX�g���X�������q�g�ƃN�}�̊댯�ȑ������N���Ȃ��悤�A�܂��N���Ă����̂Ɏ���Ȃ��悤��������݂Ă��邪�A���ۂ͎���d�̂悤�ȕ��������邩���m��Ȃ��B���̃G���A�̐l�B�̓q�O�}�̌o�ϔ�Q���d���͌��A�Q�b�̐F�������Z�����A�l�g��Q�̊댯�����y�����邢�͖������Ă��镔��������B�t�ɁA�D�y�̐l�́A���̓����̂̒m��Ȃ������X�^�[�̔@�����łɋ������đ����߂��̂悤�ɂ��v����B�ǂ���̏�Ԃ������Ƃ͎v��Ȃ����A���N�̂悤�ȃN�}�o�v��h��Ɏ��グ�����Ƃ��邾���ł͂Ȃ��A���낻�낱�̓����ɐ����A��Âɒm���Ė{�C�Ő܂荇����t���Ă������������Ă���̂����m��Ȃ��B
�@�D�y�I�����s�b�N�Ţ�X���ł���A�����������v�Ƃ����t���[�Y�����������A���̐v�v�z�ɍ����I�Ɍf����ꂽ���R�Ƃ̢������Ƃ��������Ƃ����̂͊܂܂�Ă��Ȃ������B�����̔��ӎ��͒����݂̔��w�������B�D�y�݂̂Ȃ炸�k�C���ł́A�_�n�тȂ蒬�Ȃ������Ă����Ƃ��̐v�v�z�E�v���O������v��]�V�Ȃ�����Ă���悤�Ɏv���B���R�Ȃ���A���ӂ̎R�ɂ̓q�O�}�Ƃ������b���������Ă���Ƃ����O��ŁA��������A�g�債�A�Ƃ��ɉ��C���Ă����˂Ȃ�Ȃ����낤�B����̢����������́A�o�ύ�����������Nj����Q�b�푈���J��L���钬�ł͂Ȃ��͂����B
�@
2011�N10��18���@���@���
2012�N�E�H�c�̃N�}�q�ꎖ�̂Ɋ�
�@����t�H�[�����Ŏ��^�����^�C�����������A������ی�c�̂Ƃ������A�܂���������c�̂̕����A���̊����Ɋւ��Ă��낢��ƕ]�_�߂������Ƃ���ׂ����Ƃ������āA���̂Ƃ�����̓J�`���Ɨ��āA�u���Ȃ��̌���ŃN�}��肪��������́H����Ȃ����Ă݂āB���͂��ł������v�ƌ�������A�ق荞���Ă������Ƃ�����B����������ƃX�g���[�g�Ɍ������������A���̐l���̈����l�ł͂Ȃ��̂��낤���A��^�̊��ی�E��������̐l�́A�ǂ������̎�̍���Ɋׂ�₷���悤���B
�@�L���̃c�L�m���O�}�������̃E�F�u�T�C�g�ɂ́u�������͓�������c�̂ł͂���܂���v�Ə����ςȂɖ��L���Ă��邪�A���̈Ӗ����悭�킩�����C�������B�ǂ����œǂ���m�������t����ׂĈӌ����������Ƃ́A����Ȃɓ���Ȃ��B�u�쐶������ی삵��B���R�����I�v����������̂́A�܂��A��낤�Ǝv���ΒN�ł��ł��邾�낤�B�������A���ۂɌ���ŃN�}�ƃq�g�̊Ԃŗ�������ĉ�������邱�Ƃ́A�����ȒP�Ȃ��Ƃł͂Ȃ����A�ӔC�����܂Ƃ��B�X�g���X���������A�J�͂��C�T���o����v��B�s�s���ɏZ��Łu�N�}�����v�Ȃ炢�����낤���A�Q�b�푈�̍őO���̌���ł��Ό������u�Ԃɑܒ@���ɋ����\�������Ă���B����ǂ��A�쐶�����Ή����邢�͕ی�Ǘ��Ƃ����̂́A���@�[�`�����ȃQ�[�����_�ɂȂ��Ă͂����Ȃ��B�����܂Ō���ł̎��H���v���B
�@������D�y�ŃN�}�����̋L�����V�������N�A�H�c�̃N�}�q��Ńq�O�}�ɂ��l�g���̂��N�������A����̕ی�c�̂��ǂ����炩���ł��āA�����������Ƃ��������ċ����Ă������炵���B�q�O�}�̒����ЂƂ����o�����Ȃ����ƈ�l�����Ȃ��c�̂��A�q�O�}�̖��ɑ��ĉ����w�E�������Ă����̂��͒肩�łȂ����A����͂���ȂɒP���ł��y���ł��Ȃ��Ǝv���B�����̒i���Ɋւ��āA���̎�����F�����������ߒ����������Ȃ��܂���(��q�j
�@���̎��̂̒���A���͏H�c���̂���l���瑊�k�������A�A�T�ȋC�����ŋꂢ������Ȃ��瑦���Ɂu���߂Ċm���ȎE�����̕��@�_���������܋c�_���Ă��������v�Ɠ������B�܂�A���y�����B�l��ϋɓI�ɏP���ĐH�Q���Ă��܂��قǐ��_���������������q�O�}���A����ȏ㓯���悤�Ȋ��Ő������Ă����ׂ��ł͂Ȃ��Ǝv�������A���������q�O�}���܂Ƃ߂Đ��\�������炷�������A�쐶�̃q�O�}�����Ă���������ł��e�Ղɑz���ł����B�q�O�}�̎�����20�`30�N�B���炭�A��������Ă�����Ǝ��炵�܂��ƌ����o���l���A�����ȒP�ɂ͏o�Ă��Ȃ����낤�B����ƁA�x���ꑁ����A���Ȃ��Ƃ��唼�̃N�}�͎E�������Ȃ��B����������Ȃ��Ȃ�B�Ȃ�A���̕s�K�ȃN�}�����ɁA�ł��邾���s���⋰�|�S�A�X�g���X�Ƌ�ɂ�^�����E���ė~�����Ƃ����̂��A���̓��������t�̈Ӗ��������B���\���̃q�O�}�����̂悤�ȏɒǂ����݁A�l����l�S���Ȃ�A����Ɏc�������\���̃q�O�}���E���˂Ȃ�Ȃ����낤�����ɑ��āA�P�Ɂu�E���ȁv�u���v�̘_���́A���܂�Ɍy���̂悤�Ɏv����B
�@�N�}�̏��������ȏ�ɏd�v�Ȃ��Ƃ́A���̎��̂��玄���������������A�����l���A�����w�Ԃ����B�S���Ȃ�ꂽ��l�̎�����̕��ɁA���͌h�ӂ�\����B����ȋ����̃N�}�����̂��߂ɖ������߂����Ă���āA���ӂ̂悤�ȋC���������N���B�����āA�ޏ���̎��������Ė��ʂɂ��Ă͂����Ȃ��Ǝv���B�Ȃ�A��������������B
�@���̎���́A�P�Ɏ����Ă����N�}�̖����⏬�����Ă��܂��Ă͂����Ȃ��̂ł͂Ȃ����B�N�}�Ƃ����쐶�����̖��Ƃ��āA�����Ɏ��{�����Ƃ��Ă̌��L�܂Ŋ܂߂����Ƃ��āA��̑S�̃q�g�̂ǂ����������낪���̎��̂��Ă��܂������ɏœ_�ĂȂ��Ă͂����Ȃ��悤�Ɋ�������B����Ŗ쐶�����ɑ��đ������ǂ�قǎ���Ă��邩�A����ŁA�ȒP�ɕ�������E��������C�k��l�R�́B�C�k�Ƃ��������Ȃ�Ă��Ƃ��Ƒ��݂��Ȃ��B�I�I�J�~���q�g���a�t���A�ƒ{�����ăC�k�ƌĂԂ悤�ɂȂ��������ŁA�����w�I�ɂ͌��݂����ׂẴC�k�̓I�I�J�~�̒P�Ȃ�ꈟ��ł���B��������ăq�g���q�g�̂��߂ɖ쐶����������������ǂ����肵�ė��p���邱�ƁA�����Ė��f�ȊQ�b�Ƃ��Ĕr�˂��邱�ƁB���̓�́A�\����̂̂��Ƃ̂悤�ȋC�����ĂȂ�Ȃ��B�I�I�J�~�͖{�B�ł��k�C���ł����łɃq�g����ł����Ă��܂������A�c���ꂽ���{�ݗ��̖쐶������Ƃǂ�����Đ܂荇�������ăq�g���������邩�́A���̋����̐��I�ɂ����钆�j�Ƃ��Ȃ�悤�Ɋ�������B
�@������炵�A�q�O�}�̒����ƂƂ��ɔ�Q�h�~���������Ă��钬�ł́A���炭���̎��̗��݂ō��N���ɎE�����q�O�}�Ɠ����قǂ̃q�O�}�����N�E���ꑱ���Ă���B������A���Ȃ�q�g�̃G�S�ɕ������s�s�Ȍ`�ŁB�H�c���ł��A�����̐��萶�����ɑ��āA��Ő���Ƌ^����悤�Ȃ��܂�ɖc��Ȑ��̃c�L�m���O�}���L�Q�쏜�ŕߎE����Ă��錻�����A�c�O�Ȃ��炠��B���������̌����������N�����Ă��邩�A�����ɏœ_�ĂĂ����Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��̂ł͂Ȃ����낤���B
�@�q�g�����̂��D�悾�\�\�\����͗L�Q�쏜�������Ȃ����̈�팈�܂蕶��ŁA�������ӂ���B���A�����ł��邢�͌y���ɎE���Ĕr�����邱�Ƃ��{���Ƀq�g����邱�ƂɂȂ��Ă���̂��ǂ����B�����ɁA�܂��^���]�n������B���L�������B�v��Ȃ��Ȃ�������̂Ă�A�������������B�͂����āA�N�}���E���C�k���E�����ƂŁA�q�g�͎���Ă���̂��B
�@70�N�ォ��k���X�E�F�[�f���ł́A�N�}�̕ߊl���Ǝ��E���������̒萫�I�W���������ڂ����B�J�����̖k�Ăł́A�쐶�����ւ̔��Q�Ɛl�퍷�ʂ�e���iKKK�̑䓪�Ȃǁj���A�����Ă����\���������B�܂�A�쐶�����̖����y�E���ɑ���q�g�̍U�����́A����̈ޏk�Ƃ����Ӗ��ɂ�����KKK���l�ł���A�����ɑ��鋖�e�͂̌����Ƃ����Ӗ��ɂ����Ď��E���Ɗ֘A����\��������B
�@�u����v�Ƃ����̂͗v����Ɂu������v�Ƃ��������ӎ��E���Ԉӎ������A���ꂪ�ޏk����ƁA���R�Ȃ���l�퍷�ʂ�C�W���ɂȂ���A�����̏ꍇ�A�r�����E�U�����Ɍ��т��B�t�Ɋg�����邱�Ƃɂ���āA���R�Ɂu�܂荇��������v�A�܂苤���̊��o�E�v�z�ɂȂ��邾�낤�B�ł������Ȋ���́u�����v�����A���̎����ŏ���ɓ����Ύ�������ƂȂ�B���̎��ɉƑ���F�l�������āA�n�悪�����Ďs�����������āA�l�ԂƂ������肪����BKKK�Ƃ͋t�ɂ���Ɋ�����L����ƁA���ӂ̃N�}��C�k��X�����≽���ƍL�����āA�l�ԏ���ȕ�炵������S�̂ƒ��a���Čp������q�g�̕�炵�ɂȂ��Ă����̂��Ǝv���B���ꂪ�A���Ȃ��Ƃ��n���Ƃ������̘f����̋����̐_���ł͂Ȃ����낤���B
�����j2015/08/14
�@�����̏Ɋւ��Ă͏H�c�̒m�l����̓d�b����ʂ������ł����B����̒c�̖̂��Ɠ��������o��������̂ł����A�m�l����̈���I�ȏ��Ō������������ƁA������Ȃ��甽�Ȃ���Ɏ���܂����B�����A������邹�Ȃ��C���ɂ������A���̕��͂ɂ������܂����ʂ��X�����C���ŁA�킯�̂킩��Ȃ�����ŕ��͂������̂��e�G�ɂȂ��Ă����Ǝv���܂��B�ŋ߁A�H�c�֍s���ăN�}�̐����̂��߂ɖz�������Ƃ����c�̂̕��Ƙb���@�����A�����̔ނ�̎v����w�͂����������A���Ȃ��Ƃ����̒c�̂Ɋւ��Ắu�����������Ƃ��������ċA���Ă������v�킯�ł��y���Ȃ킯�ł��Ȃ����Ƃ������ł��A�����ɒ����ƁA���l�т�\���グ�����Ǝv���܂��B���̌������Ɋւ��āA����͏\���C�����܂��B
�I�I�J�~�̍ē����Ɋւ���ӌ��@�@�@㯏m�F���������ی�W�҂���̖₢���킹�ɑ��Ă̈ӌ����j
�@�I�I�J�~�Ɍ��炸�A���Ԃ��ړ�����ꍇ�ɂ́A�����I�Ɏ��̎O�_����\���E�l�@�������Ȃ��K�v������B
�@�@�@�@�P�D�ړ������̊g�U�\�G���A���܂߁A���Ԍn�ւ̉e���i���ʂƕ���p�j
�@�@�@�@2�D�����c���E�Ǘ��ƁA�s���̎��Ԃ��N�����Ƃ��̋쒀���@
�@�@�@�@3�D�G���A�S�̂̃q�g�̎�e�\���Ɣ�Q�̕⏞
�����Ă���ɁA�G�]�I�I�J�~�̏ꍇ�́A4�Ƃ��āA
�@�@�@�@4.�k�C���ɐ��������G�]�I�I�J�~�ƊC�O����̈ړ��̌Q�͓��ꂩ�H�Ƃ�����肪����B
�P�ɂ��ẮA
�@�g�U�͈͂��܂߂��낢��ȗ\�������藧���A�M���ł���V�~�����[�V�������Ȃ��Ȃ����藧���Ȃ��B����́A�I�I�J�~���q�O�}���l���m�\�ŁA�w�K�ɂ���Ă��̊��ɓK�����������p�^�����l�����邩��ł�����B�C�O�́A�k�C���Ɠ��l�̋C�ہE�A���E�n�`�̊����ł̎��Ⴉ�琄�肷��̂ł͕s�\���ŁA���̃G���A�ɕ�炷�q�g�̕�炵��ӎ��E�m���E�Z�p�̂���悤�ɂ���āA�I�I�J�~�̓����͕ό����݂ɕω����邾�낤�B
�@���������āA��\�����Ƃ����O��ŁA2���l����K�v������B
�@�V�J�̐����������̋@�\���I�I�J�~�ړ��̌����͂̈�ƂȂ��Ă���悤�����A����Ɋւ��ẮA�M���ɑ���Ȃ��B�ꌩ�����Ƃ��炵�������ŁA���̌��ʂ��܂������Ȃ��Ƃ������Ȃ����낤���A���ʂ��R�����̂ł͂Ȃ����낤���B�V�J�̐��͐ϐ�p�^����A�������䂵���邪�A�͂����ăG�]�I�I�J�~�͂���ȂɌ��I�ɃV�J�̐����R���g���[�����Ă����̂��낤���A�����ɑ����̋^�O������B�Ⴆ�A�Â����猤�����s���Ă���k�āE���C�����A�C�����h�̃I�I�J�~�ƃ��[�X�E�A���̊W�̌����f�[�^���炷��A�I�I�J�~���V�J�̐��������R���g���[������̂ł͂Ȃ��A�V�J���I�I�J�~�̐��������R���g���[������Ƃ�����������������ɂȂ��Ă���B�i�����t�s�[�^�[�\���j
�@�܂��A�I�I�J�~�ɂ��V�J�̐������������ʂ́A��e��Ȃǂɂ��V�J�쏜�������Ȃ��Ȃ��v�Ƃ����O��ł����炩�͌��ʂ����҂ł�����̂́A�����I�ɂ́A�V�J�����݂̂悤�ɋ쏜����Ă���k�C���ł́A�قƂ�nj��ʂ�����Ȃ��Ɨ\���ł���B�܂�A�e��ɂ��ߊl�ł́A�K����背�x���̉���s�\�̂�������B�蕉���œ����Ăǂ����œ|���V�J��A����������܂ܓ����Ȃ��V�J�Ȃǂ��A�������o�Ă��܂��B���̃G���A�̃n���^�[�E�F��̈ӎ��E�����ɂ���邪�A����G���A�ł́A�x�e�����n���^�[�����C�t����100���̒e�ۂ��g��20���̃V�J��ߊl���A���S�҂�150���̃X���b�O�˂�3���̃V�J��N�Ԃɕߊl�������Ⴊ����B���̐�������A���̓�l�������̃V�J�̂ǂ��ɏe�e���������݁A�ǂ�قǂ̃_���[�W�킹�����͓ǂ߂Ȃ����A�t�@�W�[�Ȃ��瑊�����̃V�J���蕉���̂ƂȂ�A�l�m�ꂸ�ǂ����ɓ|��ĝˎ������Ɛ��@�ł���B���ۂɃq�O�}�̒��������Ă��āA�e�e�ɂ���Ď��Ǝv����V�J�̎��[�ɑ������邱�Ƃ͑����A���݂̂Ƃ��낻���̃V�J�̈ꕔ�̓q�O�}�����p���Ă�����̂́A���ɃI�I�J�~����b����A�I�I�J�~���V�J���[���q�O�}�Ƌ�������\�����������낤�B�܂�A�e�e�ɂ���ĕ����������͎��S�����V�J���I�I�J�~�͗��p���闦���A�����炭���ɍ����Ȃ邽�߁A�I�I�J�~�ɂ��V�J�̌̐��������ʂ͂قƂ�nj���Ȃ��A�Ƃ����̂����̍l�����B
�@�܂��A��̐��̒������ʂ��l����ꍇ�ɂ́A���݂Ȃ玀�ȂȂ��͂��̃V�J���I�I�J�~�������E�����Ƃ����ӂ��ɍl���Ȃ��Ă͂����Ȃ����A�ЂƓ~�̐ϐႪ���N���݂ł�12���ɔ��e��C���Ȃ�W���ϐႪ����N�́A�t��҂����Ɏ�Â��݂ł���悤�ȃt���t���̃V�J�������A�t��Ɏ��ʃV�J�̐������Ȃ葽���Ȃ�B�V�J�̉z�~�n�ւ̈ړ��Ƃ������ۂ́A�k���ł͂قƂ�ǎ��ɂ͊��m�ł��Ȃ��B
2�ɂ��āA
�@���b������ꐢ��̃I�I�J�~�ɂ́A���R�Ȃ���GPS���M�킪���������ׂ����낤���A�������Ɏ��R�ɐB��O��Ƃ���A�k�C���̊��ŃI�I�J�~�̌������2�����{�ƍl�����A���b���N4���ɂ͎q�I�I�J�~��3�`8���O��a������B�q�I�I�J�~�̐����͒������A���N�Ŗ�35�s���x�ɒB���邾�낤�B�܂������ɁA�I�X�̏ꍇ�͊��S�ɐ���������܂łɐ��N��v����B���R�ɐB�ɂ���Đ��Y���ꂽ�̂ɁA�ǂ̒i�K�łǂ̂悤�ɔ��M������邩����肾���A�����ɂ���q�I�I�J�~�Ƃ����킯�ɂ͂������A�܂��A�����̂̊����ꏊ����肵�A�s���|�C���g�ŕߊl���邱�Ƃ��A�I�I�J�~�̌x���S�E�m�\�����ăe���g���[�̍L�����l�������ƌ�����B�i�������q�O�}�ꓪ�A�s���|�C���g�ŕߊl�ł��Ȃ����k�C���ł͑����Ă���j�G�A���A���n���e�B���O�̎�@���A�p���邱�Ƃ��ł��Ȃ��n�`�E�A�����k�C���ɂ͑����B
�@�ȏォ��A��ꐢ��ȍ~�̌̂Ɋւ��āA�����I�ɓ�����c�����邱�Ƃ�����ɂȂ�͕̂K�����낤�B�ǂ͈̔͂ɉ����̃I�I�J�~���ǂ̂悤�ɐ������Ă��邩�킩��Ȃ���������Ǝv����B
�@���������āA�l�������́A���R�ɐB������������b�Ƃ������ƂɂȂ邪�i�I�X�̋����܂��̓��X�̔�D�j�A�ƂȂ�ƁA���R���̂̉\�����܂߁A�����I�ȃI�I�J�~�̕⋋���K�v�ɂȂ�B�Ƃ��낪�A�o��E�J�͈ȏ�̖��Ƃ��āA�����������V�K�̂��ݗ��̃p�b�N�Ɏ�����邩�ǂ������^�킵���A�P�ƌ̗��������ƂȂ�ƁA��^�b�̃V�J�ł͂Ȃ��A���̒��E���^�ٓ��ޓ��ւ̕�H�������܂�A�����ɉƒ{�ւ̔�Q�����J�i�_��t�B�������h��荂���Ȃ�\�����\���ɂ���B
�@�܂��A���Ƀp�b�N�ɓ���Ƃ��Ă��A�]���̃I�I�J�~�̎Љ�w�ɉ������s���Ƃ͂��Ȃ�Y����������\���������B�I�I�J�~�̐����j�ŁA�ɐB�i����E�o�Y�E�q��āj�̗v�f�̃E�F�C�g�͑傫���A���ꔲ���ŃI�I�J�~�̃p�b�N���ǂ̂悤�ɐU�镑�����A�ΊO�I�ɂ��i�p�b�N�́j�����I�ɂ��\����������Ă��Ȃ����߁A����ɗ\������ɂȂ�B
3�Ɋւ��āA
�@���ɃI�I�J�~�̂悤�ȑ�^���H�b�̕��b�ł́A�_�Ɣ�Q�i���_�j�A�y�b�g�����ւ̔�Q�ɉ����A���S���̂��܂ސl�g��Q�܂őz�肷��K�v�����邪�A�ߔN�A�q�O�}�̗L�Q�ߊl�����������A�܂����^�C�k���̃L�c�l��^�k�L�̋쏜�����~�܂肵�Ă���k�C���̌��炷��ƁA�쐶�����Ƃ̋����̎v�z���Z�����Ă��炸�A�I�I�J�~�̕��b�ɑ��ē����̃q�g�̎�e�͂͏����i�K�ɂ��B���Ă��Ȃ��ƌ��킴��Ȃ��B
�@���ی�E���a�����Ė쐶�����Ƃ̋����Ȃǂɂ͖��S�ȕ��ϓI�k�C���̐l�X�Ƃ͕ʂɁA�C�O�̗Ⴉ�玖���{�ӂɋ��e���C������������Ƃ���i�f�[�^�͑��l�̘_�����g�����j�A���̂悤�Ȏ��p������B
�@�J�i�_�C�A���o�[�^�B�ł�1982-1996�N��14�N�Ԃ�1633���̃E�V���I�I�J�~�̔�Q�ɂ������i�m�������ٌ�����Bulletin of
theShiretoko Museum 27: 1..8 (2006)��m���ɍē��������I�I�J�~���Ǘ��ł��邩�v�ēc�����j�B����116���^�N�Ƃ���������k�C���ɓK�p����킯�ɂ͂����Ȃ����낤���A�����Ƃ����_�ł͏\���Q�l�ɂ��ׂ��������낤�B
�@�܂��A�I�I�J�~�̌��ւ̍U�����͍����A�t�B�������h�S�y�ɐ�������100���قǂ̃I�I�J�~���A1996-1999�N��4�N�Ԃ�65��C�k���P�����ƕ���Ă���B�i���̔�Q�F14���^�N�j���ׂĂ̌��́A���݃I�I�J�~�̈ꈟ��Ƃ���Ă��邪�A�I�I�J�~�̃p�b�N�̃e���g���A���ȋC���E�K�������̍������ւ̍U�����Ɍ��т��Ă�����̂ƍl������B�i�������q�O�}�ƈقȂ�Ƃ��낾�낤�j
�@����ɁA�I�I�J�~�̓q�O�}���l�A���łɃq�g���P�������ł͂Ȃ����A�ɂ���čU�������邢�͂������ɋ߂��s���������ꍇ������ƍl�����A�l�g��Q�̃��x���̓q�O�}�̐l�g��Q�Ɣ�r�����郌�x���ɂ���B�J�i�_�ł�1969-2000�N��32�N�ԂɎq�����d������3�����܂߁C18���̃I�I�J�~�ɂ��l�g���̂��N�������Ƃ�����Ă���i0.56�l�^�N�j�i�ēc�j�B
�@���̑��A���R�ɐB��O��Ƃ������b�̏ꍇ�A�ȒP�ɗ\���ł��邱�Ƃ́A�����e�n�ɑ��݂���쌢�Ƃ̌��G���낤�B��q�����悤�ɁA���ׂẴC�k�̓I�I�J�~�̈���ɂ�����A���G�͗e�Ղɐ�������B������T���ƂȂ����̂́A�����ăI�I�J�~�����q�g�ɑ��Ă̌x���S���������A�q�g�Ƃ̋������������Ȃ�\���������B���ʓI�ɂ��̌��G�̂��邢�͂�����܂ރp�b�N�̓q�g���U�����₷���ƍl�����A�ނ���l�g��Q�E�y�b�g�ւ̔�Q�Ȃǂ𑝂₷�����ɌX�����Ƃ��A��r�I�����M���x�ŗ\�z�ł���̂ł͂Ȃ����B�i�I�I�J�~�͊�{�I�Ƀq�O�}���l�q�g���瓦����B���ނ̂̓C�k�̂ق����j
���J�i�_�ɂ�������G�͐[�������Ă���A��N������I�I�J�~�͉ߋ��ɃC�k�ƌ��G�����\���������v�Ƃ������e�̉Ȋw�_�������\���ꂽ���肾���A�A���X�J�ɂ�����I�I�J�~�ɂ��l�g��Q�ƁA���G�̐i�J�i�_�ɂ����邻�̐��ƁA�����g�͍��ق�����ƍl���Ă���B�f�[�^���������킹�Ă��Ȃ��̂ŁA�`�F�b�N���Ă��炢�������A���ɏ�̎��̌o���Ɋ�Â����_����������A�����ȃI�I�J�~����������A���X�J�ł́A�l�g��Q�������J�i�_���Ⴂ���x���ɂ���Ǝv���B
4�Ɋւ��āA
�@���݂̔�r�I�i�F�����炷��A�����k�C���ł����Ă��A�ʃG���A�̌̌Q�͕ʂɈ����̂����ʂɂȂ��Ă���B�i��F�C�g�E�A�T�N���}�X�Ȃǂ̋��ށB�����ނȂǁj���̊ϓ_�Ō����A�����̕��ފw�I�ȃG�]�I�I�J�~�Ƃ�����Ŋ����Ģ������Ƃ���̂́A���X���\�Ɏv����B���ފw�́A����Ӗ����ނ̂��߂̊w��ł���A�@�\�n�i�G�R�V�X�e���j�̃p�[�c�Ƃ��Č����ɓ����Ȃ��̂�����Ɋ܂܂��킯�ł͂Ȃ��Ǝ��͎v���B
�@�������A�G�]�I�I�J�~�ł��낤���k�ẴI�I�J�~�ł��낤���A�A�C���b�V���E���t�n�E���h�i�I�I�J�~���p�̌��j�ł��낤���A���R�ɕ����A���ꂼ��ߎ��I�ɏ]���̃G�]�I�I�J�~�̖����Ԍn�ʼnʂ����A�܂�A��背�x���ŃV�J���H���A��背�x���ŃE�V��C�k��q�g���P�����ƂɂȂ�Ǝv���B���̋߂��i�ߎ����j���ő���ɍ��߂�����T�n���������゠����̃I�I�J�~�Ƃ������ƂɂȂ邾�낤���A�V�J�ɑ�����ʂ��ő���ɋ��߂�A�����炭�A���b���铮���ɂ��قȂ�I��������B���́u�ߎ��I�Ɂv�Ƃ����������ɢ�k�C���̐��Ԍn�̕����v�Ƃ����悤�Ș_�����P�����������̂͌ꕾ�������͍�ׂ�����B
�@�����g�́A�C�O����̃I�I�J�~�ړ��ł́A���ꂪ�ǂ��̒n�悩��ł��O�������Ƃ����F�������Ă���B�����ɁA�쐶������ō����A���邢�͐��J��d�͂�͐�ɂ���ăq�g��������������Ɏ��S�����肷�邱�Ƃ���背�x���ŗe�F���ׂ��ƍl���Ă���B�����g�̃o�����X���o���炷��A�I�I�J�~�ɂ��l�g��Q���������Ƃ͌����Ďv���Ȃ����A���ꂪ�l�דI�ɕ��b�����O���킾�Ƃ���A���b��́E���@�ւɉȂ�����ӔC�͏d�傾�Ǝv���B
�P�`�S�ւ̎��Ȃ�̍l�@�������Ȃ������A���ɃI�I�J�~�̕��b�ɂ���ăG�]�V�J�̐����������̌��ʂ���背�x���Ŋ��҂ł����Ƃ��Ă��A���̂ق��̓_�ŁA���Ȃ��Ƃ����݁A�I�I�J�~���b�̒i�K�ł͂Ȃ��ƌ��_�����B
�@�֑��Ȃ邪�A���̓I�I�J�~���D�����B�A���X�J�ŕ�炵�āA���|�I�ȑ��݊����������̂��q�O�}�B�I�I�J�~�͂�����Ɛe�ߊ����N���B�ȑO�A�q�O�}���|�ǂ���������A�]�v�ɃI�I�J�~�ɂ�����悤�ȋC�������N�����B������A���|�ǂ��Ȃ��Ȃ������ł��A���̕�炷�J�Ƀq�O�}�Ƌ��ɐ����c�����I�I�J�~�̃p�b�N��������Ă�����ǂꂾ���������C�����ɂȂ邩�Ƃ��z�����邪�A����́A�q�O�}�̊�����I�I�J�~���b�Ƃ͕ʂ̎����̘b�B���l�̃��[�}���I�A��z�I�A��I��肾�B�A���X�J�̌���ʼn��x�ƂȂ��I�I�J�~�̃p�b�N�ɉ������Ɉ͂܂ꖰ��ɂ������Ƃ�����A���ْ̋��ƒo�ɂ̐S�n�悢��ۂ����ł��Y����Ȃ����A���̊��o�𖡂킢������A�܂��A���X�J�̌���֍s�������B�\����Ȃ����A�I�I�J�~���b�̋c�_�́A������Ƃ����I�I�J�~�t���[�N�����~�Ő���Ă���悤�ɂ���������Ƃ�������B���ɂR�Ɋւ��āA�֖��Ȋς�����B�܂�A�������ɐ^���ɃI�I�J�~���b��_���̂ł���A�q�O�}�ƃq�g�Ƃ̋�����i�߂邱�Ƃɐ�O���ׂ��̂悤�Ɏv���B�������������Ȃ���A���ׂĂ͍��ʂ��邾�낤�B���ꂭ�炢�A�q�O�}�̖��͌��ꐫ������A�I�I�J�~�̖��͂��Ƃ��b�̏o�����̂悤�Ɏv����B�k�C���̃q�g�̂�����E�ӎ��̏�Ԃ��ǂ������ӂ����́A�q�O�}�ƃq�g�̊Ԃɗ����Č���ł�����3�N�ł��������Ă݂�A�I�I�J�~�t���[�N�ɂ������ł���Ǝv���B
�@�����T�����x�A�h�b�O�Ɏd���Ă��̂́A�I�I�J�~�D��������ł͂Ȃ��A���݁A�q�O�}�ɑR���ׂ������������錢���l�����ꍇ�A�T���ȏ�ɍ����\�ȑ��_����������Ȃ��������炾�B�R���g���[�������ł���A���̌��قǒm�\�E�^���\�͂Ƃ��ɍ����A�q�O�}��Ƃŋ@�\���錢�͑��݂��Ȃ��ƌ��_�Â�������ŁA����Ɋւ��Ă̓��[�}���E��ł͂Ȃ��A�����܂ŗ�Âȕ��͂ƍl�@�E���f����ł͂���B�i���͂��܂���Ă���Ƃ���j
���M��������
2012/07/15 ���
���b�c�ƎR�F�̑�
�@2018�N1���A���b�c�R�n�̎��X�ɃX�v���[�ŗ����������ꂽ���Ⴊ�N�����B���ꂪ���������Ɏw�肳��Ă������ߎ��R�����@�̊ϓ_�������莋���ꂽ���A�����������̎��R�̑��`�ɑ���s�ׂ̐��ǂ��Ȃ̂��A�������c�_����]�n������B
�@���b�c�̎��X�Ɍu���s���N�ŏ����ꂽ�����̈Ӗ��͉���Ȃ����A�A�[�g�̊ϓ_���炷��Ƃ��̃r�r�b�h�ȐF�Â����Ƃ��������Ȃ��B�l�ɂ���Ă͂��̗��������|�p�I�ʼn��l�̂�����̂Ƃ��ĕ]�����邩���m��Ȃ��B�t�ɁA��������ƋC�����Q����l�����邾�낤�B�������A����͌l�̍D�݂�Z���X�̖��ŁA����������Ă��̗��������m�肷�鍪���ɂ��ے肷�鍪���ɂ��Ȃ�Ȃ��B
�@�X�v���[�ɂ�闎�����ƌ����j���[���[�N�̒n���S�Ⓦ���s�S���̍��ˉ��Ȃǂ��v�������Ԃ��A����炪���Ȃ̂́A���������̂ł͂Ȃ��A������̗������̌|�p�I�Ӌ`�ł��Ȃ��A���̃L�����o�X�ƂȂ����n���S��ǂɏ��L�҂�����Ƃ��낾�B���l�̂��̂ɏ���ɊG��`�����肵�Ă����̂��H�Ƃ������ɂȂ�B���R�A����͔F�߂��鎖�͂ǂ̍��ł����Ă����蓾�Ȃ��B
�@�ł͔��b�c�R�̎���ł͂ǂ��Ȃ̂��H�@���͂����ɂ́u���啨�v�Ƃ����T�O������ł���B���̂܂ܖu������̂��Ȃ����́v�ƂȂ邪�A���̑������ł͂܂��Â��B�����ł͂Ȃ��u�N�̂��̂ł�����v�Ƃ��������S�̂̋��L���Ƃ������������K�v���B����́A��C��͐�E�C�̐��ȂǂƓ��l�ŁA�l���Ƃ�����ɉ���������肷�錠���͌����F�߂��Ă��Ȃ��B�܂�A���b�c�̎��X���A�ق�̏����͎��̂��̂ł���B���Ȃ��̂��̂ł�����B������A�N�ł����Ă������������Ă͂����Ȃ��Ƃ��������ʂ�̗����ɂȂ�B
�@���R�ƌĂ�Ă�����̂́A�͂��C����C���������z�����A���̂قƂ�ǂ����啨�ŁA���͍����̋��L���Y�ł��邪�A����ɂ����ɂ͖����I�E�����I�ȐM�E�@���̖�肪����ł���B���{�ɂ����Ƃ��ƎR�x�M�������ė�R�E����݂��R�S�̂��M�̑ΏۂƂȂ��Ă������A�A�C�k�����Ȃǂ͂����Ɛ����ɖ����������R���E���R���ۂɑ���[���M�̊T�O�������Ă����B���b�c�R�ɂǂ������M�����������킩��Ȃ����A�ǂ��̒N���ǂ�Ȏv���ł��̎��X�Q�����Ă��������킩��Ȃ����A�P�ɏ��L�]�X�Ƃ����̂Ƃ͈قȂ鎟���Ńq�g�̂�����ɕ���┽����^�������Ƃ��l������B
�@�ł́A�j���X�v���[�̗������ł͂Ȃ��A�Ⴆ�Εx�m�R�ɋ��͂ȃ��[�U�[�ŊG��S���ʂ��o���s�ׂ͂ǂ����낤�H���[�U�[�̃X�C�b�`��ŃJ���t���ȊG��S�͏������Ƃ̐_�X�����x�m�R�ɖ߂邪�B�ł́A���F�ɕω�����J���t���ȃ��C�g�A�b�v�́H�@�����l���Ă����ƁA�v����ɁA���R���E���L���E���啨�̖{���̎p�Ȃ��悤�Ȕj��E�������E�f�ʁE���C�g�A�b�v�Ȃǂ́A�����I�ɂ����Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��s�ׂƂ������ƂɋC�Â��B
�@�ې��z�ł͔��b�c�̗������I�Ȏ�@���s�������悵�Ă����Ȃ��Ă���B���ہA�R�F�̑�̃��C�g�A�b�v�́A���R�����@�ɒ�G���邩�ۂ��������āA���b�c�̎��X�ւ̗������Ɖ���ς��Ȃ��B������Y�킾�Ǝv���l������A�����܂����Ǝv���l������Ǝv�����A���Ƃ��Ƃ̎��R�̑�̂���悤���Ђǂ����Ȃ��s�ׂł��邱�Ƃ����͊m�����B�{���̎R�F�̑��m��Ȃ��s���S���҂�����̋�_�ŋ����ɂ�邩�炱��Ȃ��ƂɂȂ�B�z�Ɨ₦����A����ɏƂ炵�o�������������H���Ȃ������܂��̎R�F�̑�B���ꂪ���~���̖{���̎p�����A�c�A�[�ŖK�ꂽ�l�͊F�A�ߏ�ȋr�F�ŃJ���t���Ƀ��C�g�A�b�v���ꂽ�����̕X�̂����܂���R�F�̑ꂾ�Ǝv�����݁A�{���̎R�F�̑�������鎖�͂Ȃ����낤�B�܂�ł��̂ւ�̃q�O�}��f�v���Ă��Ĕ����Ƀp���_�ӂ��Ƀy�C���g���ό��q���ĂъĂ���悤�Ȃ��̂����A���R�����������l�͔����ɓh��ꂽ�q�O�}���������킯����Ȃ��B
�@�����~���̊ό��U���łǂ����Ă����X���J���t���Ƀ��C�g�A�b�v���Đl�דI�Ɍ��z�I�ȕ��͋C����肽����A�ǂ����̍L�������ɐl�H�I�ɕX�̂��������A��������D���Ȃ悤�Ƀ��C�g�A�b�v����̂����낤�B �x┌ΕX���܂�A�w�_���X�e�܂�A�D�y��܂���͂��ߖk�C���e�n�̐��X���t�B�[�`���[�����C�x���g�ނ͂��̐ߓx�E�X�^���X�ł����Ȃ��A���ꂼ��̎������œ~�̊ό��ƂȂ��Ă���B
�@�R�F�̑�̏ꍇ�́A�s���̘J�́E�o��̊W�����ꂽ��������̃��C�g�A�b�v�͂���Ă��Ȃ����߁A�{���̎R�F�̑�t�@���͂��̓�������ĖK���������A���i�K�ł́A�~�̃C�x���g�ɍ��������̋���̍����x�Ɨe�F���Ă������Ǝv�����A���Ƃ��Ƃ��̑�Ɋւ���Ă����A�C�X�N���C�}�[�A�n��̐l�A����ɂ͌Â�����M�ƂƂ��ɂ��̒n�ɕ�炵�Ă����A�C�k�����ւ̔z���������͎��ׂ��Ǝv���B
�@���Ȃ݂ɁA�q�O�}��������Ƃ������啨�ŁA�ق�̏����͂��Ȃ��̂��̂ł�����A��������������������B�����̍��Y�ł�����B�܂��A�ߊl��{�����������錻�݂̖k�C���̏́A�A�C�k�����ɂƂ��Ă݂�A����̍ł������Ȑ_�łɊQ�b�Ƃ��ĎE���܂����Ă���ӂ��ɂ����f��Ȃ��B
|
|
|
|
 �@
�@ �@
�@